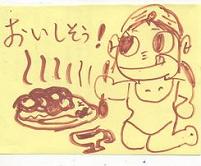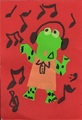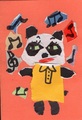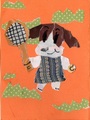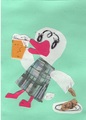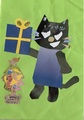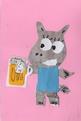2015/06/14 (Sun) 05:47:42
 お元気そうで何よりです
お元気そうで何よりです
仲良しの猫とネズミさんも・‥‥ニコニコです
昨日はサッカー日本女子代表は「C組で、日本2-1カメルーン」でどうにか勝ちました。
これで 日本女子代表が連勝したので、決勝トーナメント進出が決まりました。
皆さん応援ありがとう。
前半6分に鮫島彩(INAC神戸)が、同17分に左CKからの攻撃でFW菅沢優衣香(千葉)が頭で合わせ合計2点を取りました。
しかし試合終了間際に失点し、ひやりとさせられましたが、大きな体格のカメルーンの猛攻を良くしのぎきりました。
元気な紫陽花がニコニコです。
Re: Re: お早うございます - sisi
2021/03/03 (Wed) 18:34:58
こんな昔話があります。3月もいい気持ちですね。
動物の食物
昔々、お釈迦様は4月8日がお誕生日ですね。その時、天も地も我れ一人なので、上と下とを指しての誕生になりました。あらゆる仏様の事から、いろいろの良い事をお披露目になった方でした。インドの生まれですから色が真っ黒だって話もありますけどなる子の臨終のときには、人はもちろん、あらゆる動物が駆けつけたってどっち鼻血でございます。その時、雀は、これは大変だ。ご臨終の話だから。と言うので、手ぬぐいをかぶったまま飛んでいったらしい。そうすると、蛇は長い道をにょろにょろといき、いろいろなものが集まって行ったらしいんだけれど、蛇の後から行った帰るわ、「じれったい、あー、この、ご臨終だのにのそのそして。」と、ちょいと蛇の方蛇の歩くのを美子したらしい。そうすると、蛇も、あー、なにくそと言う気持ちだ。「そんなことして、ただでおくものか。」といきなり飛び越そうとしたカエルの足を呑んじゃった。それからは、まぁ、蛇はカエルを足から呑みます。まぁ、つばくろは、おしゃれして、口紅をつけたり、落ちてお化粧したり行ったらしい。それで、「お前はおしゃれで、こんな時を忘れているからな。」と言うので、「お前は、虫っきり食べさせられない。」って、雀は鍋墨だらけの手で、手ぬぐいかぶり、働いていたなりで行ったから「お前は米を食べなさい、一生お米を食べるんだ。」とお釈迦様が言ってなさったらしい。それが戒めのようにこの世に残ったと言う話でした。
雀孝行
燕は、むやみにおしゃればかりしていて、それに親の死ぐ目に、親が病気だと言うのに、「紅をつけて、おしろいつけて、おしゃれしたと言うわけだ。それだから、扶持をおえられない、雀は親が病気だっちば、すてんころりんかけて行ったって言うのが、穀物をもらった食ってられんだって言う。
Re: お早うございます - sisi
2021/03/28 (Sun) 09:15:40
 おはようございます、今日は雨ですね。こういう昔話もあります。
おはようございます、今日は雨ですね。こういう昔話もあります。
竜の絵
栃木県
むかし、一人の絵描きさんがありました。
ある時、自分の家の店看板に大きな竜を描いてあげました。
すると、その下から前の下駄屋から毎年一人ずつ不意に死人が出来て、もう一人でした。
死に絶えるばかりなってしまいました。近所の隣はもちろん、村人全員がみんな不思議に思い、恐ろしく感じてきました。
ところが、この話を聞いた物識な爺さんが、
「竜は人を呑むものだから、きっと真向かいの下駄屋の看板絵に見込まれたに違いない、それを防ぐには、ナメクジの絵を描いてあげるが良い。竜はナメクジが苦手だからな。」
と教えてくださいました。
「確かにナメクジが苦手だな。よし、早速描こう!」と、絵描きは、張り切りました。
下駄屋は、その通りにしますと、なるほどご利益があり、それからは何ごとも無くなったのでした。
おしまい
Re: お早うございます - sisi
2022/02/05 (Sat) 22:21:31
「アリの恩返し」
(富山県の昔話)
むかしむかし、ある村に、働き者の与兵衛が、おりました。
与兵衛は毎日、山仕事に行っては、木を切り、暮らした。
ある日、谷川で水を飲むと、1匹のアリが、苦しく溺れております。
「ああー、なんて可哀想なことだ。ほーれ、おらの腕に捕まりな。」
与兵衛は自分の伸ばした腕でアリを助けてあげました。
次の日、与兵衛がひと休みすると、何やら、自分の体が、もぞもぞと感じます。
アリがいきなり、与兵衛の体を這い上がってきた。なんと、与兵衛の耳元でささやきました。
「昨日は谷川からアリの殿様の姫を助けていただきありがとうございます。わたくしは、アリの殿様の家来と申します。早速、アリの殿様のところに連れて行きます。 是非、殿様からのお礼にしたいと言っております。」
アリの殿様の家来についていくと、小さな穴があった。「我々の村はこの中にあります。 目をつぶって、3つを数えてください。」とアリの殿様の家来が言いました。
「1つ、2つ、3つ。」と与兵衛は数えた。
与兵衛は目が開けると、あら不思議、ここはアリの村だった。
与兵衛の体がアリと同じく小さくなった。
アリの村を案内しながら、与兵衛を奥から奥まで連れて行った。
「ここは、アリ穴城でございます。こちらは食い物を貯めておく蔵で、そのこちらは子供たちが武士になるための学ぶ塾で、そのこちらは殿様の料理を出す調理場で、そのこちらは腰元や家来たちの部屋で、そのこちらは殿様の正室と姫の部屋で、最後に殿様の部屋と大広間でございます。」
大広間にいる殿様と正室と姫が与兵衛を迎えました。
「これこれは中へ入り、この度は、うちの姫を助けてくれてありがとう。助けてくれたお礼に何がいいかな、応えなさい。ところで名をなんと申す。」
「与兵衛といいます。おらは年すぎまして、嫁さんがほしいと思っております。嫁さんだけいれば、おらは一番幸せでいいです。」「おお、嫁さんか、それならは、うちの姫を嫁さんにしてやろう。安心しろ、アリからお前と同じく人間の姿にするからな。せっかくだから、嫁入り祝いとして、いいごちそうを用意するから、ゆっくり食ってくれ。」
姫はアリから美しい人間の姿に変えました。
「きれいな嫁さんだ。」と与兵衛は驚いた。
与兵衛とアリの姫はめでたく嫁入りすることができました。
与兵衛は、城からのいいごちそうを腹いっぱい食った。
元の体に戻った与兵衛は、自分の住む村へ、人間になったアリの嫁さんを連れて家に帰りました。
こうして、与兵衛と嫁さんは、山へ共働きで仲良く幸せに暮らしました。
これがアリの恩返しの話でした。
(おしまい)
Re: お早うございます - sisi
2025/02/12 (Wed) 00:57:24
江戸笑い話
夫婦喧嘩
「また隣で夫婦喧嘩を始めたらしい、困ったもんだ。毎日毎日の夫婦喧嘩に、もう仲裁に行くのも面倒で、全体、もとがやきもちから起こることだろう」「何、今日は酒から起こったそうさ」
里雀
禿たちが集まり、「わしらは、ちょっと心中して死ぬのでも、川へはまって死ぬのは嫌だ」と言えば、一人の禿が、「いやいや、他の心中じゃあとって、皆痛いぞ」「それでも、川へはまり、中に死人がいたら、怖いかな」
屏風の虎
変屈な武士が旦那寺へ行き、和尚を困らせようと思い、「和尚様、あの屏風に書いてござる虎を捕まえて、縄をかけてお渡し出されよ」と、懐中から縄を出す。和尚は、しばらく考えて、「いかにも縄をかけましょう。あの虎を庭へ追い出されたよ」
壁の落書き
ある町家のお内儀が、供の女を連れて行くところ、白壁に大きな一物をが書いてある。お内儀が眺めて、「おお、お飯があるの」と言えば、供の女は、「いいえ、あれは芹でございます」「私がお飯と言うたのは、いつ食べても食べ飽きないと言う心じゃが、芹とは、どういう心じゃ?」「はい、根まで入れてございます」
旦那「人と言うものは変わるので、小さい時に馬鹿なものは、成人すると利口になり、また、子供の時に利口なものは、大きくなると馬鹿になるものだ」と旦那が言えば、そばにいた男が、「それならば、ハバカリながら、旦那様は、お小さいときには、さぞお利口でございましたろう」
駕籠
背のいたって高い男と低い男とで駕籠を担いで行く。1、2丁行くと、乗り人が、「これでは前へひっくり返そうで危ない。前と後と変われ、変われ」と言うので、代わって、また2、3丁行くと、「これではまた、背骨がたまらぬ」「また、変わりましょうか?」「いや、それでは同じことだ。いっそ俺が出て担ごう」
火事
近火があったので、勘当されたせがれが駈けつけてお手伝いする。親父、せがれの心が治ったと勘当を許すと、せがれは喜び、タンスの羽織は袴を出してくれと言う。「この取り込みに何をする?」「ちょっと火元へ礼に行きます」落語・火事むすこの一原話
料理
四、五人より知った自慢はどこの料理がいい、いや、あそこが安いのと話すうちに1人が「なんと大黒屋は料理はいいし、安いし、娘がまたりこう者よ、そして固い娘で石のようだぜ」 「道理で俺も歯が立たなかった」
儒者
「予がごとき清き心をもって、かかる愚かなる無学者とは交われぬ」と、経書を抱き、深山に引っ込み、ただひとり心をすました顔で、日夜、書物を読んでいるところへ、大きな狼が来て、偶者を書物ぐるみ、ただひとくちに食ったとたんに反吐(ヘド)をはいて苦しむ。なかまの狼が来て、「なにゆえ苦しむ?」と問えば、「腐ったものを食った」
「経書」は、四書、五経など儒学の書物。
平目
「ゆうべ、うちの前の下水へ二尺ばかりの平目が泳いで来た。めずらしいことじゃないか」 「しかし、お前のうちの前の下水は、幅がわずか一尺ばかり。二尺の平目は大うそだな」 「いいや、堅になって」
きりぎりす
大醜(すべた)女の姉と、器量よしの妹が、薬師参りの道できりぎりすを買い、妹が手のひらへのせると、指に食いつかれる。
「姉さん、きりぎりすが食いつきました」
「なんのたいそうな。見せや」
と、姉が手のひらへのせれば、きりぎりす、顔を見て舌打ち。
松茸売り
田舎の親父が松茸を魚籠(びく)に入れて 「松茸、松茸」と町の中を売り歩いたが誰も待ったけど思わず買う人もいない。大通りへ出て大きな呉服屋を見つけた。ここで売ろうと中でも大きな松茸を一本持って入り「コレコレ」 と振り廻して見せれば手代が「小僧や大幅の白いちりめんを持っておいで」白いちりめんとはふんどし用の布のことである。
柿栗
晩秋のころ、山かげで柿と栗を話している。
「さてさて、栗殿は果報者だ。幾重も幾重も着物を着てござるが、俺ほど情けない実は ゴダラひとえ物の一枚で寒くなると赤い顔で力んでいますと涙ぐんで語れば、栗も気の毒になりひとえ物でも着ているはありがたい。 この松茸を見な。 この年になってもまだ ふんどし さえしねえ」
気丈
「この寒いに、よくまあ裸で歩くことだ。とんだ気丈な生まれたな」「なあに、全身を顔だと思えばいいのさ」
寒国(かんごく)
「これ、こなたは国は、どこじゃ?」
「はい、わしが生まれたところは北国でござる」「ひどく寒いところではないか」「さようでござる。江戸などでは土用のうち、冷水を売りますが、わしどもの国では、どこもかしこも雪だらけで、どの土用の打ち水が入ってる辻
2016/01/07 (Thu) 10:05:48
 お元気そうですね
お元気そうですね
昨日から暦では、小寒に入り段々冷え込みも厳しくなってきました。
私たちは今朝はセリ、ナズナなどを詰めた「春の七草セット」でお粥を頂きます。
「七草粥」の歴史は古く、平安時代から行われていたようです。
七草粥は、この一年の無病息災を願って食べるものですが、同時にお正月のご馳走で疲れた胃腸を休めるために食べます、
食べた後は体がポカポカと何時までも暖かです。
私たちは2日には、皆さんと一緒に神戸の生田神社へ初詣して来ました。
Re: お早うございます - sisi
2020/09/30 (Wed) 21:06:55
どうもありがとうございます
種子島の昔話があります。
なえのはじまり
むかし、地震のことを「なえ」と言いました。
ところで、どうして何が起こるのかといいますと…… .。
それはそれは長いなえと言う魚がいて、その長さと言ったら考えられないくらいなのですが、このなえが、ぐるりと地球を1周しています。
このなえの魚は、自分の尾を自分の口でくわえて、地球とちょうどタガのように占めています。が、このなえの魚も、時々、自分の尾を加えはずすことがあります。
すると、地の弱いところが割れたり、ずれたり、山が崩れたりして、なえが起こります。ところが、日本の国で1カ所だけ、京都だけは、なえがありません。といいますのは、このなえの頭がちょうど京都になっていて、その一番のところに経塚があります。そして、なえの魚が少しでも油断をして、尾を加えはずしたりすると、経塚がそのすごい重さで、なえの魚の頭をおさえます。それでなえの魚は慌てて、はずした尾を加えます。
今でもそうですが、地震が来ると、人々は皆、「きょうづか、きょうづか、きょうづか。」と唱えます。
油断して尾っぽを加えはずしたなえの魚は、その声で、はっと我に返って、尾を加えます。すると、たちまち地震は止みます。
なえのはじまりは、まずこういう次第ですが、皆さんも、地震のときは、
「きょうづか、きょうづか、きょうづか。」と唱えることになりますね。
(おしまい)
こういうおもしろ話
Re: お早うございます - sisi
2020/12/06 (Sun) 15:15:57
こんな話あります。玖島稲荷
長崎大村市
大村の氏神大村神社は、花びらが5段に咲き乱れる大村桜と言う国の天然記念物で有名でした。このお宮の本殿の後、杉の林に囲まれ、大きな楠の下に玖島稲荷の祠があります。この祠は、元は西大村の三城の城跡にあったものをここへ移した。
元亀元年の7月20日、三城が、武雄の後藤貴明、諫早の西郷純堯、平戸の松浦隆信の連合軍に、不意に襲われました。
後藤貴明は、もともと大村家に生まれた人で、ここの城主になろうと思っていました。ところが、にわかに武雄にやられ、島原の大村純忠が迎えられ領主になったので、不平に絶えず、大村領内を自分の手に握ろうと企んで、近くの藩にかせいを頼んだのが戦のおこりでした。
この時、松浦勢は、千台の小舟に乗って、伊の浦の瀬戸から、大村湾に入り、海上から迫り、貴明と純堯は、南北から三城を挟み撃ちにしました。
この時、城内には殿様の大村純忠が、たった7人の家来と共に残っていた。後は召使いやお年寄り、子供などを合わせて、70人そこそこでした。寄せ手は、1700人から大軍でした。ただひともみと、三城のふもとに迫りました。
しかし、貴明が馬を進めて、城に近づくと、お城には行く1000本となく、旗指物が昼が入り、あちらの石垣、こちらの森影には、知人、隙間もない鎧甲に身を固めた兵士が、ありのように固めているのでした。
「はて、お城の中には、物見の兵士の言うところによると、確かに手薄なはずだったが。」と、貴明は、命擦り、しげしげとうち眺めました。
その旗さし物や鎧武者と見えたのは、ここのお城の後の森に茂っているこの速草木で、口を見せたのは、みんなこの森に住んでいる、四郎左衛門と言う古狐の仕業でした。この狐には、この後の森に住んでいたもので、何10匹と言う子供やいく何100匹と言う子分を持っていました。「三城危うし」と見るや、すぐ子分や子供孫どもを集め、ある時は敵の陣中に入り込んで引っ掻き回し、あるときは敵軍の様子を調べて、純忠に報告したりしたものでした。さて、富永又助と言うものがありました。純忠のご機嫌を損ねて、お目通りもできぬ身分になっていましたが、
四郎左衛門に教えられて、鈴田峠の方から攻め込んできた大渡野軍兵衛の本陣へ、紛れ込みました。軍兵衛は本野村の大渡野に住む豪傑で、この頃「おわたにごんべい来た」と言えば泣く子も黙るほど、恐れられていた大将でした。また助けは、降参した真似をして、「私が、三城の方、道案内しましょう」と言うと、軍兵衛は喜んで、また助けを先頭に立たせ、自分も後から、馬に乗って進んでいきました。武部郷の昼も暗いほど木の茂った細い坂道にかかった時、またつけば、いきなり軍兵衛の油断を見て、脇腹を短刀で突き刺しました。「おのれ、図られたか、あーチクショ~。」と叫びながら、軍兵衛は馬から落ちてしまいました。「軍兵衛撃ち取り…。」のうわさで、敵陣は、にわかにうき腰になりました。兵士たちは諫早のほうにどんどん逃げ出した。そのうちに、三城の方には兵士が集まり、松浦の船も臼島の沖で焼き討ちにあったと言う噂が立ちました。「この合戦勝ち目なし」と見てとった貴明も、虚しく兵士をひいて、武生のほうに引き上げてしまいました。純忠は、また助けの手をとって、喜びました。軍兵衛の撃たれた所には、誰が立てたか、今でも大きな石が、苔に埋もれて、立っています。
さて、四郎左衛門狐も、この日の合戦で、足を負傷して、びっこになってしまいました。
しかしみんなから「四郎左衛門殿」と敬われるようになり、この後も三城を守っていました。殿様が、行列を整え、よその国に旅立ちになる時、自分もたくさんの子分を連れてお供しました。それも家老格になって、かみしもをつけ、カゴに乗って出かけました。子分のちょっと子供も、それぞれ槍持ちやハサミ箱持ちに分けてぞろぞろ行列に加わったものであります。純忠の子供の喜前が今の大村神社のところにある玖島城を築いた時、四郎左衛門の住処は、今の玖島稲荷のところに移されて、三城には、分家の祠を残すと残すことにしました。
明治になってから、樟のうを取るために、大きな楠を倒そうとすると、神主さんの枕元に、白髪になった四郎左衛門が現れて、「祠は、決して壊してくれるな」と言ったそうだ。そこでこのお稲荷様は、今も残っていて、毎年お祭りとして賑やかに行われていました。
(おしまい
Re: Re: お早うございます - sisi
2020/12/06 (Sun) 15:26:27
こんな話あります。長い長い話
(香川県の昔話)
その1
むかしむかしのあったそうな。
大名屋敷の米倉の中へ、ネズミがたくさんはいっていました。それが、1匹ずつ外へ出てきます。
チューチューチュー
と言うてた。はじめのが、飛び出してきたんでした。次のも、
チューチューチュー
と鳴いて飛び出してきたんでした。そのまた次のも、
チューチューチュー
を飛び出してきた。またまたその次も、
チューチューチュー
またまたまたその次も、
チューチューチューチューチューチューチュー
またまたまたまたその次も、どんどん続く。
チューチューチューチューチューチューチュー
大変な無限で来てしまうネズミでした。
その2
むかしむかし、山の中の池のそばに、どんぐりの木が生えていました。もう秋が来ましたね、風が吹いてきて、1つずつ力落ちては池の中4落ち込むんでした。池の中には岩がありました。
ドブンカチリ、ドブンカチリ、ドブンカチリ。
と音がしていて、次から次へと落ちてきます。
ドブンカチリ、ドブンカチリ、ドブンカチリ、
ドブンカチリ、ドブンカチリ、ドブンカチリ。
なんと音がしても落ち続きます。
その3
むかしむかし、長崎からの重箱に入れて赤飯を持って来ました。
天からなんと不思議に、ふんどしが降りてきました。
なぜふんどしが降りてきたのかな。
これはさっぱりわからないー。
(おしまい)
Re: お早うございます - sisi
2024/08/21 (Wed) 20:38:52
 「土瓶と茶瓶と藁」(兵庫県の昔話)
「土瓶と茶瓶と藁」(兵庫県の昔話)
むかし、一本の橋に土瓶と茶瓶が出会った。
土瓶が橋を渡ると、「この橋は俺が渡る!茶瓶は後戻りしろ」
茶瓶が橋を渡ると、「なにィ!この橋は俺が渡る、土瓶は後戻りしろ」と二人は喧嘩して橋から足を滑ると、川に土瓶がドビーン!茶瓶がチャビーン!とした。流れてドビーンチャビーン、ドビーンチャビーン。
土瓶と茶瓶と友達の藁を連れて伊勢まいりに帰るとき、川に橋がない。
仕方なく藁が橋になって、先に土瓶と茶瓶が渡ると、二人は体が重く、藁は絶えず、渡る二人を川に落ち、ドビーンチャビーン、ドビーンチャビーンと流れ、おまけに藁も川に落ちた。(おしまい)
Re: お早うございます - sisi
2024/12/09 (Mon) 00:45:15
「楠さん楠さん」(長崎県五島市の昔話)
むかし、一人の若い猟師が住んでおり、ここあたりでは年が押し詰まっていると必ず富江の領主様にイノシシを一匹献上することになった。「今年もイノシシ献上しなければ」こう言って、若い猟師は山のイノシシの通りそうな道に柵を作った。どうしても、うまい具合イノシシがかかりません。「明日はいよいよ大晦日だ今日中には一匹捕まえなければ」と言って朝から家を出かけようとすると、嫁さんが「今日は赤ん坊が生まれるかもしれないよ、出かけないでくださいね、一人では心細いから」と頼みました。しかし、猟師は「除夜の鐘が鳴るまでにはどうしてもイノシシを納めなければ辛抱してくれ」と言い残して、気が進まないまま家を出た山の方に登っていくとにわかに空が真っ暗に曇り雨が降り出した。ずぶ濡れになり走っていくと道端に一本の大きな楠があって根っこのところは大きなほら穴になっています。「これはかっこうの雨宿り場だ」と、「楠さん、楠さん、雨が止むまでどうかこの後あなたの木のほら穴中に宿を貸して下さらんかと言うと クスはいいともいいと思うとこういった具合に大きな枝を二、三度は横に譲りました。。体を横にして寝てしまいました 雨は前よりも激しく降った しばらくすると外の方で ガヤガヤ 話す声がするので目を覚ますと人もなく 耳をすますと「楠さん楠さん、こんばんは、山下にお産がありますので一緒に行きませんか」すると楠は「前から待っていたお産んだから、行きたいのは山々だから、今日はあいにくお客さんがある。 私が出かけたら客が濡れて困るから行かれないお前たちだけ言っておいでよ 」「それは残念」今度は ガヤガヤと山を降っていく様子でした。猟師はこれを聞いて、「はて、俺の家ことか知らんな、この土砂降りとは、ここを出ても、行かれん」と、思案すると、またガヤガヤ帰って来た様子です。「楠さん、楠さん、生まれたのは男の子でしたよ」「それはそれはご苦労さん」「ところが残念なことに その子は7つの年の3月3日までの寿命でそれから先は生きられません」と言うと遠くの方へ行ってしまいました。 「はて、その子は俺の子かもしれん、大変なことを聞いてしまったな」と若い猟師は雨の中に飛び出してずぶ濡れになって家に帰ってきました。うちでは、玉のような赤ん坊が生まれて、嫁はほっとしているところでした。 よかったと夫婦して喜びあいました。 花よ蝶よその子のも可愛がって育っていましたが 月日経つのは早いもので いつのまにか7年の月日過ぎて3月の3日になってしまいました。 いつか楠のほら穴の中で聞いたことを思い出し、嫁に嫁に七つの重箱 いっぱいにごちそう作って詰めさせました。 そうして息子を膝元近くに呼んで家たちは後から来る お前はこの重箱を担いで先に食べに出ておいでと言いました。 すると 、生まれつき素直な息子はそれを聞くと、その重箱を担いで家を出て行きました。 まず菜の花咲いている畑を横切りました。 次には梅の林を通った。その次には梨の花の咲いた 舌を通りました。 おしまいに桃の花がいっぱい咲いている丘の上に出ました。 向こうは広々とした青い海でした。 息子はそこの岩の上に腰を下ろし、重箱を膝の上に乗せて蓋を取って食べ始めた。すると、向こうの海が白く泡立ち、むくむくと化け物が現れて、やがて化け物は丘の上に這い上がってきて、そして、息子の様子を見て俺にも食わせろと言って、重箱の中のごちそう食べ始めました。そうして一つの重箱の蓋を取って、みんな食べてしまうと化け物はお腹をさすりながら、お前を食うつもりで海の中からできてきたが ごちそう食べ過ぎて腹がいっぱいになってしもうた。「川にお前には八十八まで寿命をやるから、お前には八十八のお日様が拝めるぞ」こう言って海の中に飛び込んでしまいました。 (おしまい)
Re: お早うございます - sisi
2024/12/17 (Tue) 16:58:55
 「わらびの恩」(岩手県の昔話)
「わらびの恩」(岩手県の昔話)
むかしむかしの暖かい春、ある山奥の茅畑にヘビが気持ちよく昼寝しています。
ところが、ヘビの体にチクッと刺され、とんがった茅が生えて、「痛い痛いよ〜」と泣いた。茅に刺されたままのヘビは全然抜けられなくなり顔が苦しんだ。それを見た友達のネズミ、モグラ、カエルがかわいそうなヘビを心配した。三匹で「ヘビよ、ヘビよ、茅畑に昼寝してわらびの恩を忘れたか」と三回唱えた。すると、茅畑にわらびがニョキニョキと生えだした。わらびがヘビの体を支えながら茅より伸びてきて命拾いで助かった。これも友達が唱えたおかげでもある。「みんなありがとうな、これもわらびの恩だ」とヘビは嬉しくて、友達に感謝した。(おしまい)
Re: お早うございます - sisi
2024/12/19 (Thu) 21:27:34
 「蛇の巾着」(愛知県豊田市の昔話)
「蛇の巾着」(愛知県豊田市の昔話)
むかし、歌の上手な人がいて、歌合うたって、通ったけどな。蛇が惚れて、蛇が惚れちゃった。帰りだが、どんなところだが、家に呼び込んで、それから、何だったいなあ、記念に財布の巾着をくれた。そしたら、巾着から銭を出して使った。使っても使っても、不思議に減らないという。(おしまい)
Re: お早うございます - sisi
2025/02/09 (Sun) 17:52:43
こんにちは、最近は寒さが続き、雪もよく降っております。
江戸笑い話でもしましょう
分け取り
むかし、巾着切りが5・6人寄り合い、ほうぼうで取ったものを分けようとする時、中でもひときわ重い財布が見えない。「これは合点のいかぬ。この中に手癖の悪いものはないか?」
押し込み
むかし、泥坊たちが相談し、「とかく、小さいところは良い仕事にならない」と、越後屋へ入ると決めた。「人に傷つけては、呉服物など汚れて銭にならず。片っ端から縛って猿ぐつわをはめ、柱へくくりつけてから、思いのまま呉服ものを持ち出そう」と申し合わせたところ、「それは、押し込み」と出てくる手代たちが来た男まで次々と縛って、猿ぐつわをはめ、柱へくくりつけたが、後から後から出てきて、縛り作せず、そのうちに夜が明けて、カラスが、「カアカア」
大力
原題は角力取り
むかし、「角力取りのところに泥坊は入った」「そして、どうした?」「角力取りは大力だ。泥坊が入ったと見るや、むっくと起き、庭へ出て、大きな石の手水鉢を小脇にかいこみ、餅を引き伸ばすように引き伸ばし、引きちぎっては投げ、また、ちぎっては投げ」
菅丞相
むかし、時平(じへい)が讒言によって流され給い、「さてさて、にくき時平かな。何として時平めを取り殺しいたもの」と、雷神となって、時平(四へい)が参内する伺い、頭上へ落ちて、時平を真っ二つに引き裂き給えば、仁平(二へい)が二人出来た。
餅をびょうという
むかし、長兵衛という男が両国あたりへ商いに行き、家に帰って向かい「さてさて、ほうぼうを歩けば、いろいろ言葉が変わるものだ。餅をびょうと言うところがあったので覚えてきた。誰か来たら、餅をびょうと言うから、よく覚えていて出してやれ」と、餅を十ばかり、買ってきて戸棚入れて誰が来ないかと間所へ権兵衛と言う男が久しぶりに訪ねてきた。「権兵衛さん、よくおいでなされた。そうそう、お上がりください」「あまり久しくお尋ね申さの上、ちょっとお寄り申しました。まず、どなた様にもご機嫌よくて、おめでとうございます」「さぁ、久しぶりじゃー。まず、お上がりください。あぁ、何もごあいそうがない。これこれ、なんぞあげい、おお思い出した。びょうがある。びょうを出してやる」「はいはい」と言って、女房が戸棚から出すと、餅がかびているので、「もしもし、びょうは、びょうじゃが、仮病になりました」「はてさて、仮病になったか、厄病に出してやれ」権兵衛がそれを聞いて、「仮病の厄病のとおっしゃるのでは、私は、臆病にいたしましょう」
通仁(つうじん)
むかし、「茶屋の娘分は、ただ者じゃない。確かに女郎上がりだ。諸事扱いぶりが手慣れたもの。隣の薪屋の娘と並ぶとわかりやす。女郎と地者とは碁石と言うものだ」と話すのを聞いた男は、家へ帰り、近所の人に「お前は物知りだが女郎と地者とは碁石だと申す人がありましたが、何のことでござります?」「はて、知れたこと。白ウと、黒ウと」
注…地者は、芸娼妓に対して、シロウト女を言う
建立
むかし、門口へ托鉢の坊主が来て、デッチが銭一文放り出してやる。後でまた1人くると、また放り出してやる。続いて、また1人来る。また銭を放り出して、デッチ、気がつき、「しまった。今の四文銭(しもんせん)だ。釣りをよこせ」と言えば、坊主、振り返り、「ツリガネえの建立」
茶碗
むかし、道具屋が来て「もし、面白い軸がございますが、お召しになさいませんか」「なになに、はあ、木庵和尚だな。いいものらしいが、意地悪の姑で、嫁(読め)にくい」「いや、姑だから、古くて値打ちものでござります」「そんなら、求めておきましょう」「ついでにこの萩の茶碗もお召しくだされば」「なになに、いやいや、これはいかん、姑は、また堪忍だが、これは出戻りの嫁だ」「なぜでござります」「もう割れている」
蕎麦屋
むかし、蕎麦屋の出前待ちが急いで行くのを呼び止めて、「お前、もっと静かに行けよ、落として道具でも壊したから叱られるのだろう。急がないと、そばでも延びるか」「いいいや」「そんなら、なぜ急ぐ?」「そばが、かけ(駈け)だ」
2013/07/09 (Tue) 15:11:09
Re: 暑中お見舞い申し上げます - sisi
2020/12/06 (Sun) 16:37:57
面白い話あります。
「おすわり地蔵さま」
山形県西置賜郡
むかし、羽前国(山形県)の朝日山の麓の小さな村に権兵衛と言う夫婦ものが住んでおった。
村のそばを、一本の川が流れておった。この川はひどい暴れ川で、毎年のように大水が出ては、村の田畑を押し流してしまう。
村人たちは、ほとほと困っており、どうすることもできなくなった。
その年もまた、大水が出て、せっかく実った田畑が、泥の海になってしもうた。
権兵衛は、泥田をぼんやり眺めておるみんなに、「堤防作るぞ。そうすれば、泥田にならずに済む。」と言うだが、
村人たちは、「堤防など、いくら作ったって、大水が出れば、たちまち流されるに決まってる。無駄なことだ。」「堤防は作るといっても、一体、何年かかる気だ。」
と言って、誰も相手にしてくれませんでした。
ところが権兵衛夫婦は、それから毎日、二人だけでモッコを担ぎ、堤防を作り始めた。村人たちは川の岸で、二人を横目でみては、「無駄な事だ。」と、笑っておった。でも、1年が過ぎ、2年が経つと、堤防は堤防は、少しずつできてきた。
「えらいもんだ。塵も積もれば山となると言うが、人の力は恐ろしいもんだ。」
「オラも手伝う。」
と、一緒に力を貸してくれる人が、1人増えて、2人増えて、3年目には30人にもなったので、堤防は、ぐんぐん伸びていきました。
といっても、長い川岸に、堤防を築き終わるには、あと何年かかるかはわからない。やがて村人たちは、気長な仕事にあきれて、次の年には、1人減り、2人減りしていき、5年目には、また権兵衛夫婦の2人きりになってしもうた。
そして、7年目の秋、ひどい雨風が続いておった朝の事でした。「大水だ。大水だ!」と言う声に、村人たちが飛び起きて、表に飛び出すと、「堤防が崩れる!このまま崩れる!」と、権兵衛と母親が、気が狂ったように、堤防の上を走っていくのが見えた。
「そっちには行くな!堤防が崩れたら、一緒に水飲まれるぞ!」
村人たちは、必死に叫んで、止めたが、権兵衛と母親が、下の堤防の方へ、どんどんかけていってしまった。
高みのほうに逃げて、どうなることかと、一晩過ごした村人たちに、次の朝、やっと水がおさまると、恐る恐る、村に帰ってきた。すると、権兵衛の堤防は、びくともせずに、村を自ら防いでおった。「よかった、よかった。この堤防のおかげで助かった。「と言いながら、村人たちは、権兵衛が走っていた、川下の方へ行ってみたが、権兵衛夫婦は、どこを探してもいなかった。そのかわり、堤防が、今にも切れそうになったあたりに、昨日までなかった、見上げるばかりの大石が、川っぷちにでんとはまり込んで、川の流れを、おしかえしておった。まるで石が、自分の体で、堤防の切れ目を、かばっているようだった。「これは、権兵衛どんたちが石になり、堤防を守ってくれたかもしれない。」誰言うとなしにそう言うと、その石で地蔵様を彫って、権兵衛夫婦をまつわることになった。石屋の金吉が、のみを持って、地蔵様を刻みにかかったが、不思議なことに、のみを持つ手が、勝手に動いて、たちまち、5メートルの見事なお地蔵さまを彫り上げた。そして、さらに不思議なことに、地蔵様が出来上がったとき、金吉は、満足そうな顔をして、死んでおった。「これは、えらいことじゃ。」と、村では早速、地蔵様を、町の寺に収めることにしたが、何しろ5メートルもあるお地蔵さまだから、運ぶにも運べん。
地蔵様を取り巻いて、どうしたものかと考えておると、不意に地蔵様が口を聞いた。
「オラ、自分で歩く。だけど、人に見られるのは辛いから、みんなの家の中に入ってくれ。」
村人は、たまげて家の中に飛び込み、ピタリと頭をしめて、息を凝らしていると、ドスンドスンと、地蔵様が歩き出す音が聞こえた。児童様は、一晩中歩き続けたが、何といっても、重いから重い体だから、なかなか道がはかどらない。白鷹町の玄僧坂(げそざか)までやってきたとときには、東の空が白みかけてきた。
「これは、急がなきゃ。それにしてもくたびれたから、ここらで一休みしましょうか。」と言って、立ち止まっていると、向こうから赤ん坊を背負った女の人がやってきた。
「これこれ、こんなに朝早く、どこへ行くんだ。」
と地蔵様が聞くと、女の人はびっくりして、「子供の足が立たないので、百日の願掛けしても今日がちょうど百日目。でも人に見られたら、ダメだと言うから、お地蔵さまにでおうたからには、ダメになったべはあ。」
と言って、悲しい顔をした。すると地蔵様は、でんと腰をおろし、赤ん坊を膝に抱き上げて、足をさすって言うた。
「よしよし。それでは、オラの足と、とりかえっこだ。」
途端に赤ん坊は、ケラケラ笑い、地蔵様の膝から飛び降りると、ちょこちょこ歩き出した。地蔵様のほうは、その時から動けなくなり、玄僧坂に座りきりになったそうな。
今でも、子供の足が立つようにと、お参りに来る人が大勢おって、お祭りの日には、大きな草鞋をお供えする。
(おしまい)
赤小豆洗いぎつね
茨城県
むかし、細谷通町という今は水戸市の新舟渡と御蔵との間の川ばたに、赤小豆洗いというところがありました。そのあたりに狐が住んでいて、雨の夜など、ザック、ザック、と赤小豆を洗う音がたてながら、
「赤小豆磨きましょか、人取って食いましょか。」
ある時、塩谷五郎次という武士が、夜更けに庭先でしょんべんをしていたところ、垣根の木陰から狐が出てきて、
「赤小豆磨きましょか、人取って食いましょか。」
と、歌いながらひょんひょんひょんひょんと跳ね上がって踊りだしました。五郎次もこれを見るとつりこまれて、同じように両手を高く差し上げ手首を折り曲げて踊りだしたから、狐はうまく五郎次を化かすことができたと思ったのでしょう。ひょんひょんひょんひょん踊りながらだんだんとごろつきに近づいてきました。
五郎次も踊りながら間合を測って、狐が跳ね上がったところをさっと刀でなぎはらいました。狐は、「ぎゃっ。」と悲鳴をあげてくれました。これを次は後も向かずにそのまま家に入り、翌日探しましたら、頭のはげた年老いた狐が胴を真っ二つに切られて死んでいました。
(おしまい)
天狗松の話 昔々、高鍋の小丸に、1人の百姓が住んでおり、百姓は、5つの男の子が降りました。ある夕暮れ、男の子たちは、駄々をこね、母親を困らせました。気の短い母親は、たまりかねて、子供を外へ突き出したまま声を固く閉めてしまった。子供はしきりに泣き続けていましたが、しばらくすると、鳴き声が段々遠ざかった。母親が驚いてかけていくと、子供は庭の松木の上で泣いていました。
母親は顔色変え、早く降りてー、登ったままじゃ危ないよ。と呼びました。するとその時、何か黒い鳥のようなものがむくむく動き出し、その途端に子供の着物の付け紐が下がってきた。母親は慌ててそのツケ紐を握りましたが、何の手応えもない。そのうちに怪しい黒い鳥のようなものが子供を抱き上げたまま、するするとその高く舞い上がった。母親の手元には、着物からちぎれた付け紐が残ったばかりだ。母親はあまりのことに涙も出ず、ぼんやり立っていきました。そこに畑から父親が帰ってきました。母親は父親に恐ろしい出来事を話しました。2人は嘆き悲しみました。それから3年の月日が過ぎたある朝のこと、母親はうらの畑で大根を抜いてみると、お母さんよ、ご無沙汰していましたが、お母さんはお元気ですか。と高い空の上から声が聞こえてきました。びっくりした母親が空を見上げると高い空の中ほどに懐かしい子供の姿が見えました。戻ってきてくれたのか、さぁ、早く降りて、早く降りて。 お母さん、今日は天狗様の使いの途中だよ。 やっぱり、お前は天狗にさらわれたね。 お母さん、もう私は人間の子供ではない、天狗様から術をいただいたから人間の子供に返されるんですが、1つお願いがあります。あの庭の松木が枯れていて、大事にしてくださいと、あの松の木が栄ゆるかぎり、私もお母さんもお父さんもみんな達者で幸せにしてください。子供はもう別れの言葉を言い残すと、また東の空を目指して、家のように早くかけて行ったのでした。おい待ってくれ、待ってくれ。母親は、天狗になった我が子の姿を追いながら、いつまでもこう呼び続けた。それからと言うもの、この百姓の家の松の木を天狗松と呼ぶようになった。終わり
昔々、あるところに正直な婆さんが住んでいました。ばあさんの家には、1匹の犬を飼っていましたばあさんはこの犬をとても可愛がりどこへ行っても連れて行きました。ある日のこと、婆さんは犬を連れて、山の畑へ登りました。婆さんが、畑の草むしりをして、犬が吠えました。畑の片隅をしきりに足で書き上げていました。ここほれわんわんここほれワンワンと吠えた。そこで婆さんが畑の隅を掘りました。これは金のツボじゃないか。と、ばあさんはびっくりした。ツボの中からは宝物がどさりと入ってきた。婆さんは犬のおかげで急に大金持ちになりました。正直婆さんの隣には欲張りなおばあさんがいましたこれこれ小竹原さん、ここほれワンワンの犬を貸してくれないか。欲張りな婆さんは、そう言って、無理に嫌がるの山の後頃連れて行きました。おいはよ、ツボの中からは宝物がどっさりと入ってきた。婆さんは犬のおかげで急に大金持ちになりました。正直婆さんの隣には欲張りなおばあさんがいましたこれこれおたけ婆さん、ここほれワンワンの犬を貸してくれないか。欲張りな婆さんは、そう言って、無理に嫌がる犬を山の畑へ連れて行きました。 おいはよ、掘れ。ほれほれ。いくら欲張りな婆さんがけしかけても、犬は吠えません。ここほれわんわんここほれわんわん欲張りな婆さんはどこを掘っても何も出ませんでした。怒った欲張りな婆さんは、犬を殺してしまいました。 あー、かわいそうなことしたな。んん正直な婆さんは死んだ犬を持って帰りました。そして家の庭の隅に丁寧な埋めてやりましたすると、庭の隅からもくもくとにょきにょきとたけのこが出てきました。たけのこはぐんぐん伸びて家の上に出ました。とうとう天竺の金倉母を突き破ってしまいました。さぁ大変なこと。毎日毎日、天竺の金倉からたくさんの小判が落ちてきました。またまた、正直な婆さんは、大金持ちになりました。隣の欲張りな婆さんは、そっとたけのこを1本盗んで植えました。たけのこはぐんぐん伸びていきましたが、欲張りな婆さんは微笑んで待っていました。ところが、今度のたけのこは、天竺の便所を突き破ってしまった。どーんどーんと、欲張りな婆さんは毎日糞かぶりでした。そこで、この欲張りな婆さんは、どこかへ逃げていきました。人真似しても人真似しても糞をかぶる誰かがそう言って、欲張りな婆さんを笑いました。 終わり
黄金の精 昔々、あるところに一人の山伏が住んでいた、立派な白髭の山伏でした。この山伏は、黄金の壺のありかを知っていた。そこで欲深い村人が山伏のところへ黄金の壺のありかを聞きに行きました。すると山伏は笑いながら、 やめたいたほうがいいよ。黄金の精神に当てると、目がうつぶるがな。 と言いました。山伏さん、教えてくれよ。 と男は熱心に頼みました。しかし山伏は黄金の壺のありかを教えてくれない。あきらめられない男は、あちこちの裏を駆け回り、坪のありかを探していました。ところが白ひげのやまぼうしの方でも、よく金男がツボを探しまわっていることを聞くと、だんだん心配し始めた。この白ひげの山伏だって、黄金の壺を掘って見たくてたまらない。そこで山伏は、男と相談して、2人で壺を掘り出す約束しました。一本松目当てに朝日輝く夕日てるところ。これが山伏の指図でした。いよいよツボのありかの畑で掘リ方が始まった。深くなるにつれて、井戸のように水が湧き、たくさんの人手が必要だ。翼にくらんだ男と山伏は、自分たちの持ち金を投げ出して、ツボを掘り続けました。1日2日、ようやく2週間が経ち、ツボを入れた石櫃を掘り当てた。穴の底から人足の声が聞こえた。山伏どん、宝のツボがありました。と言った。待て待て、お前らは上あがれ。山伏と男は、縄ばしごをつたって穴の底へ降りていきました。2人は穴の底まで来ると、おい、命つぶれ。と言いあいながら、手探りで壺のふたをこじ開けようとしました。泥土で硬くしまったツボの蓋が、少し開きかかりました。その時、よく深な男が、 あっ! と悲鳴あげた。山伏は思わず目を開いた。二人とも黄金の精でメクラになってしまいました。恐ろしくなった人足どもは壺を見ようともせず、どんどん土を穴の中に埋めてしまった。黄金千無量。黄金の壺は誰も見たものはいませんでした。終わり
山ノ上の荒五郎
(石川県の昔話)
むかし、輪島の山ノ上というところに、五郎次郎という男がおりました。
五郎次郎は怪力で、あたりに比べ者のないほどでしたから、村人は荒五郎と呼んでいました。荒五郎は小屋くらいなら、肩に乗せて楽に運ぶ事もできました。
ある日、荒五郎は村の家たちの戸を叩いて言い触らしました。
「明日は、蛇の池に行って、蛇の口とらえてみようか。お前ら、蛇の子を食ったことがあるか、俺は明日やってみせる。」
すると、どの戸口にも同じような返事がありました。
「ほんまにするのか、怪しいなぁ。」
そこで、荒五郎は名前に知れた強力者の手前、どうしても、やってみせぬわけにはゆかなくなりました。
夜が明け、荒五郎は蛇の池に出かけました。大手を振って、肩をいからし、胸を張りその格好は、まさに英雄でした。
あちこちの窓からこの英雄を見送る顔が見えます。
それから小半時もすると,荒五郎は蛇の子をぶら下げて戻ってきました村人はもう珍しそうに、荒五郎の家へついていきました。
家へ着き,荒五郎は村人の前で,蛇の子の串焼きにして食べました。
「どんなかな。」
「へぇ。」
というわけで、村人も今更ながら感心をしました。
それから2 、3日たったある晩こと、蛇の池の大蛇が荒五郎の家にやってきました。顔面を朱にして、ものすごい怒りの様子でした。
「荒五郎、お前の命はもらったぞ。この子の仇だ。」
「なんだと,やれるもんならやってみろ。」
荒五郎が言うと、大蛇はますます怒り,おどりかかりました。
その勢いが口に言われぬほど凄まじく、とうとう大蛇が真っ二つに割れて、家を一気呑みにしてしまいました。
何事も、ものに限りがあるものでした。
(おしまい)
ムジナの失敗
(石川県の昔話)
むかし、寛政の頃。
町野の鈴屋に男と娘がいて、2人はいつの間に仲良くなり、毎晩、宮森というところであいびきしました。
そのうち、娘は子供をはらんでしまいました。こっそり会っていたわけですから、親に知れると大変になります。
そこで娘が言いました。「とうとう、こんなことになってしもうた。死ぬより他に道は無いわね。」
すると、男が言いました。「お前に死なれたら、わしだって、生きる甲斐が無い。お前だけを死なそう。」
こうして2人は固く約束して帰りました。
やがて、約束の夜がやってきました娘が宮森のはずれに待っていると、男も姿を見せました。松の木の間に一本の縄をつるして、2人はその両足に首をゆわえました。1、2の合図で、2人は大石の上野から飛び降りました。ところが、不思議なことに、男の体が妙に軽く、そのため娘の足が地面についてしまいました。
娘は変に思い、空高く吊し上がった男をみれば、これはまた不思議、男のはずが男ではなく、1匹のムジナがぶら下がっていました。頭をぐったりされて、すでにこの世のものではありません。
娘はびっくり仰天、我が家へかけ戻りました。
ことの起こりは、このムジナもやはり娘に恋していたのでした。
ムジナは宮森の主でした。その晩、実の男が死ぬのを恐れて、約束の場所へ来ないのを知ると、男に化けて娘を騙そうとしたわけだ。
(おしまい)
福童丸
(石川県の昔話)
むかしむかし、櫛比の庄鬼屋の神様が、ある日、寺中尾の福童丸を呼んでいました。」陸奥国には素晴らしい牛馬があるそうだから、買い入れてきてくれ。「そこで、福童丸は神様のおおせに従って、旅に出ました。陸奥国への道中は、聞いてたよりもはるかに長く、退屈でした。それでも国境が見えるあたりまでやってきました。
福童丸が陸奥国へ入ると、「福童丸、牛馬をひいて行ってください。去年は牛の年、今年は妙法蓮華の寅年。年も良いし日も良いぞ。」と誰かの歌声が聞こえました。
山を越え、ハララゴの入りと言う所へ来ると、出し抜けに、1人の男が現れて、
「わしは権太郎兵衛だが、お前はどこへ行くんだ。」と言いました。
福童丸が訳を話すと、権太郎兵衛は、「それは遠いとこ。さぁ、こっちへ来てこい。」と言って、千畳敷もある広い部屋へ案内しました。そこには蝶々や菊の花の形の珍しい栗の実が酒の肴に大和盛られて、その傍に、虎の木の根元ごとこしらえた大杯に、酒があふれんばかりたたえられてありました。
何十人の下僕が絶え間なく、福堂丸にかしずきました。福童丸は六七四十二杯も大杯をいただいてしまいました。
「権太郎兵衛さん、えらいご馳走になりました。」
「なになに、はるばる来てくれたからお前には、まだ、足りないと思うてるから、もっとやってください。」
「いいえ、わしはもう、こっちでたくさんでしたよ。」
「そんなら、福童丸、せめてはこれでも取っといて下さい。」
と言って、権太郎兵衛は金貨の298枚を差し出しました。福童丸は、いただいて、
「ところで牧場はどこですか。」と訪ねました。
権太郎兵衛は後の山を指して言いました。
「あそこへ行ったら、お前の好きのを、連れてください。」
そこで、福童のはツルツル山を登りました。1枚の扉を開けて、見たこともない見事な馬が立っています。2つ目は月輪のように輝き、前足ははるか飯の山の頂をカパカパと踏まえ、後ろ足を酒の泉を踏み下ろすと言う、誠に鬼屋の杜の神様がのりうつったかと思うような神馬でした。
次に、2枚の扉を開けて、これまた、素晴らしい牛がシロエという草の名前の米をニトリニトリかみしめております。
福童丸は傍のイイザサという笹の名前をはらいよけて、その牛に、「ヘンベイ」と問うてみると、
「コンメイ」と答えました。
これは不思議とまた、「ヘンベイ」と問うてみると、「コンメイ」と答えました。
福童丸はもう一度、イイザサをはらいよけて、「ヘンベイ」と問いました。
すると、牛は、「夏の日は照るに照る。月に3度の利益。」と答えました。
いよいよ、不思議に思い、イイザサをはらいよけて、4度と言いました。
すると、牛は、「権太郎兵衛の一人娘の婿になれ。」と答えました。
福童丸は大変喜ぶと今は再び、牛の様子を伺いました。
あっぱれ見事な足たちで目は月輪のように輝き、角の向きは風や火の禍(わざわい)を知らせるという。中でも、その尾といったら、まるで、法華経八の巻を押し下ろしたような、誠に神様らしい牛でした。
これも、仏様の権現かとも思われた。
そこで、福童丸は、権太郎兵衛の、美しい1人娘を嫁にもらって、1枚の紙馬と2枚の羽塩買って、鬼の神様の下へ帰りました。それから、福童丸は美しい嫁と幸せに暮らしました。
権現の牛と馬は村の田んぼを耕しました。牛と馬は耕すとき、「一束四斗八升」と言いました。
すると、稲は木のように高く伸びて、黄金なす稲穂が実ました。おかげさまで、村がずいぶん栄えて、みんなの幸福な日を送るようになりました
今でも鬼屋神社のゾンベラ祭りで、このお話を囃子太鼓で舞い踊るそうな。
(おしまい)
Re: 暑中お見舞い申し上げます - sisi
2024/03/29 (Fri) 23:33:36
りんき梅
(三重県の昔話)
むかしむかし、一身田に地主であった男がいました。その男は長年連れ添った妻をよそに密かにもう一人の女の所へ通っていた。夫を愛していた妻は愛されている間は、そんな事は知らずにいたが、そのうちに夫の素振りの違いからなんとなくおかしい感じ始め、やがて、よそに思う女のいるところを知っていた。妻は嫉妬のために怒り狂い、挙句の果てに、刃物を持ち出、夫を殺し自分も小竹とした。とうとう夫を庭のすみの梅の根っこのほうに追い詰め、恨みを込めて刃物を吐きだしたのだが、夫は危ういところで体を交わし、梅の木の後ろへ逃れた。妻の突き出した刃物はズボリと梅の幹に突き刺さった。抜こうとしたが抜けない。それを見た夫は妻の念力の恐ろしさに身震いして、その場にへたりこんでしまった。妻はそのうちに我に返り、己の嫉妬の心の底深いことを知り、我が身を恥じ、そのまま夫の前から姿を消した。その後、発心して、専修寺に入り、刃物突きが出た梅を境内に移し植えて、りんき(嫉妬)の戒めとしたそうな。(おしまい)
(参考出典:東海の民話・語り継ぐ68話、中日新聞本社刊)
Re: 暑中お見舞い申し上げます - sisi
2024/08/04 (Sun) 10:00:39
最近はかなりの猛暑が続いております。水分補給と冷房しましょうね。
「寝富貴どん」(長崎県の昔話)
むかし、ある男が、イカや魚たちの漁に出たが、イカや魚たちもあまりつかず、船に寝ておりました。すると、船の底には、こつこつこつこつとあたるものがあった。おどろいたら、「カワウソどもじゃあるまいし」と思ってみると、ひょうたんでした。それを拾い上げてみると、その人に何か沈んでいるので、引き上げてみると、千両箱が出てきた。その千両箱の浮いたものがひょうたんと一緒でした。これで、その男は大金持ちになり、寝富貴(ねふき)どんという名をよびました。おしまい
Re: 暑中お見舞い申し上げます - sisi
2024/08/13 (Tue) 16:40:03
 夏は怪談昔話です。
夏は怪談昔話です。
「ドアノブと電話」(宮崎県の昔話)
むかし、宮崎のある小学校に、一人の公務員が夜中になっても校内を見まわりした。
午前0時になると、校長室のドアノブがくるりとくるりと回った。
午前3時になると、校内の全室の電話が鳴り始めり、うるさい音だ。
回るドアノブと鳴る電話は夜明けまで続いた。公務員はうるさく布団をかぶった。(おしまい)
Re: 暑中お見舞い申し上げます - sisi
2024/08/14 (Wed) 09:26:20
明日は終戦記念日。今回は戦争にちなむ日本の民話を紹介いたします。
「夢でものを貸す」(滋賀県の昔話)
むかし、農業出身の男は大東亜戦争の時に。夜の夢に弟が来て「俺は善光寺参りをしなんだのが心残りは、是非お参りたいから兄貴の白い数珠を貸してくれ」と言う。「いいとも、持っていけ」と言って目が覚めた。不思議に思って仏壇の中の箱を調べると、中の白いサンゴの数珠がなかった。妻に尋ねても触ったこともないと言う。それから七日ほどして、また弟が夢に現れた。「おかげで念願の善光寺にお詣りしてきた。数珠を返すよ」と言う。目が覚めて仏壇の箱の中を見ると、数珠はちゃんと入っていた信じられないよほど不思議なことであった。男がいとこにこの話をしたらいとこも夢を見たと言う。善光寺にお参りして、大勢の人と共に本土に坐っていると前のほうに男の弟がいた。「お前もきたのか」と声かけると「思いに思って善光寺に来たのが、俺はこの数珠が気に入らない。兄貴の持っている白い数珠を貸して欲しい」と言いながら、手に数珠をまさぐっていた。それは糸が緩み珠も粗末な黒い数珠だった。その後は男のところへ弟の戦死の知らせが届いたと言う。(おしまい)
Re: 暑中お見舞い申し上げます - sisi
2024/08/19 (Mon) 22:10:59
 天狗のコマ 静岡県伊豆市の昔話
天狗のコマ 静岡県伊豆市の昔話
むかし、あるお寺に、一丁という小僧さんがいました。なかなかのいたずら者でお経読むのもいい加減、寺の仕事はそっちのけ、暇さえあれば、コマ回しに夢中でした。ところがこのコマ回しがなかなかの腕前で一度だって負けたことない。ある晩のこと、一丁さんが便所から出てきて、長い廊下を歩き、すると、バサバサバサバサと不意に大きな羽ばたきの音がして、「小僧、こっちへ来い」あっという間に、一丁さんの体は空へ持ち上げられました。一丁さんはびっくり仰天。どしんと一丁さんは、地面に投げ出された。そーっと、目を開けると、辺りは真っ暗で何も見えない。ガヤガヤと誰か大勢いるようです。その時、暗がりのあちらこちらから怒鳴り声が聞こえた。「ほら、小僧、天狗になれ」「天狗になれ」「さあ、さあ、さあ、天狗になれ」一丁さんは震えた。ブルブルと「いやじゃいやじゃ、天狗は嫌いじゃ」すると、天狗がいちどに..笑いました。「天狗は嫌だと、いいや、小僧、天狗にしてくれ」天狗にされるとは、情けない。はて、どうするか。ところが、「あっ、そうだ」一丁さんはコマを持っていたことを、思い出した。一丁さんはコマを回しながら、誰だって負けない。「天狗さん、コマ回ししましょう。私が負けたら、天狗になってもいいけど」と、言いました。よし。天狗は立ち上がった。「そら、行くぞ。」シューと暗闇の中から天狗のコマが飛んできた。一丁さんも負けずにコマを取り出すと、ビューと投げつけた。パチ。パチ、パチ。あっという間に、天狗のコマは、引き飛ばされた。「これは強いぞ」ヒューピューと天狗たちは次々と駒を投げましたが、一丁さんには勝てません。「ええい、しゃくだ。」「小僧、負けたぞ」天狗たちはザワザワと立ち上がり、天狗に負けた、コマを一丁さんのふところへねじこみました。「わはははは、見事なことにしてやられたわ」天狗笑いが起こると大きな羽ばたきがして、天狗の姿は消えてしまいました。夜が明けると、「一丁さん、よおーい。」「小僧、やーい」見ると、向こうから、和尚さんや村人たちがやってきた。「どうしたことじゃ、一丁さん、きょとーんとして」「あれまぁ、ふところに、たあんと何を入れてるのかな」気がつくと、一丁さんのふところにはいっぱい押し込まれていた天狗のコマはいつの間にか、椎茸になってしまいました。(おしまい)
2012/06/05 (Tue) 08:52:52
 ☆お(^O^)☆は(^o^)☆よ(^0^)☆う(^ー^☆♪ございます。
☆お(^O^)☆は(^o^)☆よ(^0^)☆う(^ー^☆♪ございます。
自分で描いた絵ですが・好きな一枚です・・。
再びのお届けかも?
今日の笑顔の宅配です。
Re: えつこの部屋 - sisi
2012/06/06 (Wed) 17:01:24
 遅れてすいません、ありがとうございます、幸せいっぱいの作品ですね、笑顔が届いていますよ。
遅れてすいません、ありがとうございます、幸せいっぱいの作品ですね、笑顔が届いていますよ。
これは、黒犬がジュースを飲んでいます、ワンワン!
Re: えつこの部屋 - sisi
2012/06/18 (Mon) 00:48:06
お知らせ、きのうまで開催された芦屋のギャラリー・ポウの白黒展で飾った、あのジュースの黒犬のはりえの原画が売れました、お買い上げありがとうございました!
Re: えつこの部屋 - sisi
2021/01/06 (Wed) 21:59:07
 可愛い昔話あります、ムジナです。
可愛い昔話あります、ムジナです。
ムジナの星見
(長野県の昔話)
ムジナと言うのは、人を騙したりすると言うあまり評判良い動物ではありません。
さてむかし、信濃の国のムジナでは、星を眺めるの出そうな。この土地の夜空があんまり美しいだろうか。ムジナは犀川べりの岩かどに立って、のけぞるようにして星を見つめていました。星は東から西へとそっと静かに動いていくから、ムジナもだんだんのけぞって、ついにはポトンと犀川へ落ちてしまうと言う。犀川の魚を取るための仕掛けの竹すにムジナの死んだのが引っかかったりすると、
「あー、昨夜の星がきれいだなぁ。」と村人は言うそうな。
(おしまい)
もうひとつ長野県の昔話あります。
河童とザザ虫
長野県の木曽地方
むかし、川奉行の六兵衛が、馬に乗って天竜川を見回っていると、水の中から河童が現れ、いきなり馬のしっぽに飛びついた。六兵衛は、馬もろとも、危なく川の中へ引っ張りこまれそうになったが、馬にムチをくれて、やっと、屋敷まで引き返した。ところが河童は、馬のしっぽが手に巻きついて抜けなくなり、ついに六兵衛の厩の前まで引き込まれてしまっていました。河童は、飼い葉おけの中に隠れていたが、六兵衛に見つかってしまいました。
「川の魚ばかりか、今まで取って食おうとしたが、タチの悪い河童は、生かしておけぬ。」
危なく殺されそうになった河童は、「どうか命ばかりはお許しください。その代わり、酒の肴にもってこいの珍味を持ってきますので約束します。」
と、六兵衛に向かって手を合わせました。酒の好きな六兵衛が、河童を許してやると、その晩、カッパは、ざるいっぱいのザザ虫を川からとってきました。「こんなものが食えるのか?」
ざるの中で、もぞもぞと動いているザザ虫を見て、六兵衛は顔をしかめました。「はい、見かけによらずは、なかなかの味でございます。」河童は、ザザ虫を鍋でいって、六兵衛にすすめた。
「なんだ、今までのないイケるうまさだ。」
六兵衛は、舌鼓を打ちながら、晩酌を重ねたような。もちろん河童も晩酌へ付き合った。
今でも天竜川のザザ虫は、伊那谷の珍味とされていました。
(おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2022/01/04 (Tue) 19:51:47
こんばんは、寅年にふさわしい昔話をご紹介いたしましょう。
「虎とイタチ」
(新潟県の昔話)
むかしむかしのある山の中に、虎とイタチが出会いました。虎がある時、大きい声で威張って言うた。「この山の中で、おらが、いち早く走り、かけっくらで、俺に勝ったもんはいないからな。」イタチは、「おいおい、虎どんよ、お前は大変な勢いであるが、だけど、オラとかけっくらをするのか。」「何、イタチか、生意気なことを言うな。よし、勝負だ。」2人は、かけっくらを始めた。その時、虎が飛び出すのが早いか、イタチは、虎の尻尾につかまって、ぶら下がっていました。しばらく経つと、虎が、止まって後ろの方を見て、「イタチのような、小さいこの様して、オラとかけっくらをするなんて、なんだ、影も形もない。」と言うた。「おいおい、虎どん、それは困るな、俺はここにいるよ。」と、自分より先の方で声がしたんだが、虎は、たまげて飛び出した。こうして、虎が止まって後を見るたびに、イタチは、いつも虎の尻尾から降りて、虎の先にいました。さすがの虎も、イタチ、の知恵には、かなわない、とうとう負けてしもうた。 (おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2022/01/05 (Wed) 18:38:50
 今日は寒くなりましたね。十二支に選ばなかった昔話を紹介します。
今日は寒くなりましたね。十二支に選ばなかった昔話を紹介します。
「熊とタニシ」
(大阪府枚方市の昔話)
むかしむかし、河内の国の枚方は津田の国見山あたりのところに、十二支になれなかった熊とタニシが、おった。
元旦になり、熊とタニシは,神社へ初詣にいくことにした。
熊はなぜか、尻尾が長くたれている。
二人は十二支になれない悔しさを話しながら歩いた。
「熊どん、十二支たちは足が速いから,オラたちは足が遅いからべべになってしもうた。」
「ああ,タニシどん、十二番目になれへんとは悔しい。」
「熊どん、オラと神社まで競争せえへんか。」
「アホなこと言うな。タニシどんが,のろのろやから勝てるないやろ。おらのほうが速いからな。」
「わからへんで,おらのほうが速いかもしれへんで。」
「ほな,タニシどん、おらと勝負したろうか。」
「熊どん、ええとも!」
というわけで、熊とタニシは、神社まで、どっちが足速いのか競争した。
熊は余裕で走った。一方、タニシは、ホンマは相変わらず足速くないが、頭の使うことは上手いけど、熊のたれたしっぽに口でかじりついたことを、熊は気づかないようにしている。
熊は、「とうとうタニシがいないぞ、もうあきらめたか。これでオラの勝ちや!」と、楽々走った。
ところが急に吹雪がきて、熊は寒がりながら走り続けた。だが、熊の尻尾にかみつくタニシは吹雪にあって耐えられない。
「な,なんや、かみつく力がたえない〜。もうあかん。」
神社まであと一歩に着くところだが、さらにはげしい吹雪がきて、とうとうタニシは、熊の尻尾が、プチンときれて、神社まで飛ばされて落ちてきて、まさか、熊より着いてしまった。熊も神社に着いた。
「はて,なんで、タニシどんが神社に・・・。」
「熊どん、尻尾が短くなったけど、どないしたんや。」
「あれれ,いつの間に・・・。」と、熊もさっぱりわからんかった。
なぜ熊の尻尾は短かったのも、はじまりかもしれませんね。 (おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2022/01/22 (Sat) 06:41:30
「手振り地蔵」
(兵庫県西宮市の昔話)
むかしの平成のころかな。
女子大生二人が学校の休日に車でドライブへ出かけます。
六甲山あたりのあるところに、お地蔵さんのような手をあげながらボールを持つ少女の立っている銅像がありまして、これを手振り地蔵と呼ばれたそうな。
助手席にいる女は車窓を見ると、身振り地蔵の後ろの風景などを見ると、何らかでバイバイしているような手を横に振っているように見えてしまいます。
でも、運転手の女は、手振り地蔵がこっちにおいでおいでとしているみたいに手を縦に振るように見えてしまう。
帰りには、思わない交通事故に遭いました。不思議そうで恐ろしい話でした。
おしまい
Re: えつこの部屋 - sisi
2022/01/29 (Sat) 20:42:46
 こんばんは、怖い話もあります。
こんばんは、怖い話もあります。
「岩魚坊主」
岐阜県中津川市の昔話
むかしむかし、中津川にたくさんの岩魚が泳いでいた。日照り続きで、淵の水が減ってしまい、3人の男は淵に毒を流して魚を殺しました。そこで小屋の囲炉裏に鍋をかけて、煮込んだ。すると、どこから来たのか1人の坊さんは訪ねて来て、3人に言ったそうだ。
「これこれ、魚を取ることは、やめなさい。」
「坊さんには関係ない、魚を取ることが、おらたちの自由だ!」
「魚に毒を流すことは、みんな殺されてしまうから可哀想だ。」
3人は坊さんから聞いたことが気味が悪そう。
男は少し震えながら、坊さんに団子を差し出した。
「ところで坊さん、よかったら団子を食わねえか。」
「すまないな、いただきます。」
坊さんは男からもらった団子をパクリと飲み込んだ。
3人の男は、魚に毒を流すことをやめた。
次の朝、3人の男は、あれだけ坊さんの言われたことをやぶり、再びあきらめず、淵に毒を流した。次々と水面に岩魚たちを浮き死んで、最後の淵に誰も見たことない大きな岩魚があり、毒を流して、とうとう死んでしもうた。3人の男は、酒盛りしながら、たくさん取った魚をたらふく食べた。
床に坊さんが食べた団子がコロコロ転がったが、あの団子が岩魚の目ん玉になった。袋に入っている団子達もみんな目ん玉だった。3人の男はますます気味悪く恐ろしかった。
その次の朝、3人は目が覚めず、とうとう死んでしもうた。
きっと、岩魚を殺して食べたたたりに違いない。
あの坊さんの正体は、最後の淵に住む大きな岩魚の主でした。
(おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2022/02/01 (Tue) 19:21:52
「節分の山の神」
(長野県の昔話)
むかしむかし、山師の子分たちが山へ行き、小屋を建て泊まりました。
節分の日には、家へ来たいと思ったけれど、日にちを間違えて、節分の晩に泊まった。
そうして、夕飯を食べたら、みんなは眠った。それでも、親方は一人だけ眠らず、火をどんどん炊いた。
そのうちに、背の一丈のある爺さんが、そこへ来た。そうして、ものも言わねえで、座って、妙だ。と思い、親方も口を聞かねえで、黙った。そしたら、そのうちに、だんだん白んできて、夜が明けそうになった。そしたら、若い女が背中から子供を降ろして、
「さて、降りて乳でも飲んでいこう。今夜はいい年とりにしょうと思ってきたでも、邪魔者がいて、いい年はできなかった。」
と、そう言った。そうして、乳をくれて、女が出ていった。そしたら、背の高い爺さんが、
「お前たちは、節分の年取りの晩というのに、どうして山に泊まったの。おらが来たからよかったが、おらが来なければ、今出ていった若い女にみんな食われてしまったんだ。」
「あれはなんだ。」
「あれは山鬼だ。おらは山の主だ。山の主は山の神のことだ。おらをおっかねえと思うやら知らないが、今出たのに昨夜に食われてしまったんだ。」
「おかげさまで、ありがとうございます。なんのお礼するか。」
「お礼はいらない。」
とそう言って、そのまま消え去りました。
(おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2022/03/10 (Thu) 22:12:54
明日3月11日金曜日で起きた宮城の三陸の東日本大震災の発生した場所。三陸の昔話を紹介しましょう。
あの
聟入り 南三陸町 昔々、あるところに、働き嫌いな怠け者の男がいました。毎日ごろごろ寝てばかりいて、いいことないのかな。とぶつぶつ言った。ある日のこと、怠け者の男は、彼方へ行って赤い小さな提灯1つ買いました。その足で森の中のある八幡神社へ行って、誰もいないのか。と屋根に登りました。瓦の中に巣を作っている鳩が1匹おりまして、ふところさ入れて降りてきました。その夜のこと、怠け者男は、それを持って、長者の家の庭の杉の木へ登りました。この木は長者の家の氏神様の神木でした。長女は、いつも夜中になると、しょんべんしたくなり起きました。目は覚まして、お布団から出てくると、 長者さん長者さん。 と言う声がしました。 なんだ今ごろ。 と長者は首はかしげていましたすると、杉の木の上でいる怠け者の男は鼻は手を手でつまんで、俺は誰だか知ってるか。と言いました。俺にはわからない。長者が答えると、 オラはこの氏神さんは長者とこの一人娘さ、いい聟ぱやっぺとおもってなや。空からここの杉の木さ下ってきたのだや。 と怠け者の男は、威張って言います。 それはすまない。 ンダべんだべ。 んで、おらどこさくる聟は誰だ。 と長者は聞きました。怠け者の男は一段と声張り上げて、 それは隣の男がいい。と言い、そして端の足の小さなちょうちんを糸で結び、手から放した。パタパタパタと森のほうに飛んでいった。ポーポーと鳴き声がしばらく聞こえた。長者は、 本当に氏神さんのお告げか。 とつぶやいた。その明くる日の朝の事、長者は村のおばあさんば喜んで怠け者の男の家へいってもらった。 隣の長者さんが、お前ば聟さ欲しいと言ってるのだが。母さんが言いますと、オラのものでいいのならば、聟さいくべや。 と怠け者の男が言いました。それから男は長者の家へ行って、楽に暮らした。 人は頭で出世するのだから。 とつぶやいていていたと言うことだ。終わり
狐とりの弥左衛門 牡鹿郡 昔々,鯰江(なまえ)六太夫と言う笛の名人が降りまして、気ままな殿様の怒りに触れて、島流しになりました。6大佑はいつもしぐれになると笛を持って浜辺にたたずむのでした。遠くぼんやりと自分の住んでいた陸地を眺めて、それから笛を吹きました。ある日のこと、6太夫が笛持って、浜辺にたつと、どこからともなく13、4歳の童子がやってきた。 6太夫や六太夫や。 と童子が言います。 なんだかどこのわらしだ、見たことないなぁ。 6大佑は不思議に思って聞きました。 おらはこの島の狐だ。 あれ狐なのか。 六太夫は驚いて声をあげました。 六太夫やオラはいつも笛を聞くのが楽しみでね、6大佑がこの島に流されてきてから毎日笛を吹くものだ。と言い、それからかなしげにこう言ったのでした。六太夫やその笛も俺は今晩きりで聞けなくなるものだ。 どうしたんだ、童子。 六太夫は訪ねました。 実は明日の朝、ここさ弥左衛門が流れてくるよ。 弥左衛門って誰だ。 狐とりの名人だ。この男さかかると、どんな狐でも逃げることができないことだ、弥左衛門が殿様の山に入って狐を取ったので、ここは島流しになったのだ。とわらしは、打ちしおれるばかり。 明日の朝の事、童子にはわかるのか。 来年のこともわかるよ。と童子が言います。 六太夫や,今まで笛を聴かせてもらったお礼にオラが源平合戦の有機ばみせすべ。 と童子は,激しい源平合戦の様子をまのあたりにみせた。それが進むと、 六太夫や、今度の月夜の晩にここさきて、一生懸命笛を吹いてみなさい。 と言います。そして、 六太夫や、それではオラがはいくす。しばらくここで不要吹いてください、俺は笛を聴きながら洞穴へ戻って、明日、弥左衛門に取られるのを待っている。と言い、幾度も幾度も振り返って草むらの中に姿を消した。 おかしなことをあればあるものか。 六太夫はそうつぶやいてて、上を口に当てたのでした。明くる朝の事、狐鳥の弥左衛門が来て、古狐を捕まえたと言う噂を聞きました。やっぱり本当だったのか。六太夫は狐の肉を食べろと言われても、首を横に振るのでした。月夜の晩のこと、六太夫は童子の言ったとおり、浜辺に来て一生懸命ふよう吹きました。笛の音は海の面を渡って、遠くまで流れていったのでした。 自分でもよく吹けたなや。 六太夫も快い疲れがきて、やがて眠ってしまった。その同じ月夜のことを、殿様は用事があって、お城のある町から海岸に来ていました。ふと、耳をすますと、美しい笛の音が流れてくるのでした。今まで聞いたこともない位の美しさでした。これこれ、あの笛は誰が吹いているのだ。と家臣の者に問うたのです。 太郎様、俺もさっきから聴き惚れておりました。でも誰も知らないというのが。と答えるのでした。やがてそれがここより30里もある海の上のはるかから聞こえてくるものと知ると、さらにさらに驚くばかりだ。 これはきっと名人が吹いたんだな、なんでまた島へ流したのだ。 と自分の気ままからしたことなど忘れて、すぐ召し帰せと命じました。六太夫はいよいよ、自分の住処に戻ることになり、狐取りの弥左衛門から狐の毛皮を譲り受けて、穴を掘り、埋めました。その上に石をのせ、狐の塚と名付けたのでした。六太夫は船の出るまで、その塚の前で笛を吹き続けていました。 終わり
人買譚「ひとかいたん」南三陸町
昔々、あるところに貧しい家があり、そこには10歳になる娘がいました。 不作も困る。 と世話する人があって、娘は売られてしまいました。娘は知らない他国先で、ご飯炊きながらの子守の仕事として使われていました。夕暮れになると、娘は、お母さんといって母親は恋しくなって泣くのでした。あんまり泣くものですから、そこの旦那さんも お前は10歳か。 と暇ばやると、言ってくれた。 これからお前は、人買いで売られてはだめだ。と言って聞かせ、外にやることになったのでした娘は幾度も幾度もお礼を言って、自分の里へ戻っていった。いよいよ明日は郷に着くと言う日でした。娘は船を乗るため港の旅籠さ泊まった。そう旅籠は人買いの男が泊まっていました。 旅籠のおんつあん、娘いねえがなや と旅籠の主人に言いました。 いねえことはねえが、まだ年とってねえものなや。 歳はいくつ。10歳なったばかり。と言って、娘の泊まっている部屋の障子を穴あけて、覗いてみたのでした。 まだ小さいやつか。 そうか。 俺は買うことする と相談がまとまっていた。それを聞くと、娘は恐ろしさにブルブルと震えているばかりでした。明くる朝、旅籠の主人は、これ娘これ娘、里へ戻る船はあるからそれを乗りなさい、俺も行ってけっからなや と言います。娘は泣くばかりでした。人買いの男と旅籠の主人と娘が船さ乗りました。だんだんと港が遠くなっていきました。夕暮れになると、小さな島が近くなりました。 ここの島さ休むぺ。 と人買いの男は真っ先に飛び降り、島さ上がりました。手には太い綱を持っています。これで船を木さ結ぼうとするのでした。すると、旅籠の主人はいきなり懐伝え、持っていた小さい方のでぷっつりと網を切ってしまったので、どこへ行くのだ、旅籠のおんつあん と人買いの男は、叫び声をあげますが旅籠の主人は素知らぬ顔をして船を漕ぎ出した。そしてそのまま娘をこの里へ送り届けて人買いの男からもらった銭を置いて、 こっちの家でこれから困っても娘は売ってはダメだぞ。 と言っていたと言うことだ。終わり
河童の詫び,南三陸町
昔々、本吉郡の河童はいたずら好きで里のみんなから嫌われてしまいました。 とってもオラ部落さおけねえから。 ととうとう追い出されてしまった。本吉のかっぱは、こんな汚い部落さいねえす。 と憎まれ口を聞いて、仙台の城下町に出てきた。旅籠に泊まっていると、暑い暑いとみんながいます。その年は例年にない暑い夏でした。すると本吉のカッパは、 おらが涼しくするよ。 と言って術を使い曇りの日を続かさせたのでした。お日様は顔を隠してしまった。街の人々は しのぎ良い夏だ。 と喜んだ。本吉のカッパは、秋まで遊んで土産物をたくさんもらい、里に帰りました。藤田、俺はこんなに宮城ものもらってきたぞ。頭胸を張って、里の入り口まで来ました。すると、里の人々が、いっぱい集まって行きました。で迎えに来た。カッパがいました。里の1人が戻るのは待っていたのだと言いました。カッパは土産ものは1つもやらないぞと言いました。物などいらない。と里のひとりが、カッパをいきなり殴りつけました。 何するんだ。 河童が言うと、 このばかかっぱ、術ばかり使って曇リ日ば続かせたんだ。里の田んぼを枯れてしまった。 と他の里の1人がまた殴りつけました。本吉のカッパは悪かったと、里の人々に詫びを入れたと言うことでした。終わり
ムジナの話,南三陸町
昔々、今日の公家が家来れば52匹連れて、地方巡察と言って村々をまわってきました。公家は立派な髭を増やしてそっくり返ってきました。階上村の肝入の家さ,止まることになった。 公家さん,泊まった記念に掛け物を書いてください。 とその家の主人が頼みますと, 書いてください と公家は守護符として手書きされた。 公家さんなに食べます と聞きますと、私は肉と魚かな。と答えました。大漁されたばかりのイワシを食べてください。 と主人は言いました。
公家は家来に給仕するといい、襖を閉め切り、食事をしました。毎日毎日、イワシを食っても食っても飽きる様子もなく大好物になってしまいました。もっと持ってください。とたくさん食べました。ある日のこと、私どっち泊まっている公家は、来てから30日にもなるのに、1階も風呂は入りませんねぇ。と家の主人が村の年寄りに不思議に思い話をしました。おかしな9夏は無理に無理でも案内してよ。と年寄りは言いますので、家の主人は とっても良い風呂ですから と無理に、風呂をすすめました。公家は全部の戸を閉めて入っていきました。家の主人はそっと節穴から覗き込みました。すると、公家の姿ではなく、一頭のムジナが風呂を入っていいて、太いしっぽまでも見えてしまいました。ムジナの仕業かと驚いていると、たちまち下の公家さんになって出てきました。私の目の間違いかな。と家の主は自分を疑ってしまっていました。公家さんはいよいよ出発されることになりました 浜街道を通って気仙沼行きます。 と家の主人が勧めたのですが、公家さんは、 私は陸が嫌だから。 と言い、舟で鹿折まで行きました。その後年寄りは、陸へ行けば犬に襲われるから海へ行ったぞ。 と言いました。この公家は京都のあるお寺に住んでいた古いムジナであったと言うことだ。今も公家さんの宿泊した階上村(ハシカミムラ)にも片浜にも、ムジナの掛物が残っているそうな。終わり
黒船 南三陸町 昔々、ある日のこと、志津川の沖の方から一層の黒塗りの船が入ってきました。その船は、今まで見たことない美しい飾りでした。しかも笛や太鼓の賑やかに囃子をたてていました。 なんだこれ。 と浜の人たちは不思議を感じ、かけて行ってみると船がいっぱいに大きな畑や小さな畑を片して、8、9歳位の子供たちが美しい手甲脚絆(てっこうきゃはん)に身を固め、小手には鈴をつけて笛や太鼓に合わせて身振りおかしく小さな太鼓を鳴らしながら踊ってているのが見えました。船から1日一夜中、囃子の音が聞こえていたのですがどうしたわけかばったりとその音が止んでしまった。浜の人たちは顔を見合わせてますます不思議に思い感じ、恐るほど小舟を漕ぎ出して黒塗りのか船に近づいてきました。しかし、あれほどにぎやかに、囃子で踊っていた子供たちはこの姿は見当たらない。人のいた気配さえ感じられなかった。 不思議なことがあるのか。 と浜の1人が見ると、黒ずんだ大きな古い船の中にはただ一体の御神体が安置してあるだけでした。 これはきっと、神様が俺たちの浜がいいと思ってお泊りになったのか。 と浜の人はいいました。この浜の祭りの日は、囃子を真似てトリ囃子といって黒船を飾り、その上に浜の子供たちをのせ、浜じゅう総出で町じゅうを引きまわしていました。終わり
Re: えつこの部屋 - sisi
2024/05/17 (Fri) 23:06:29
「警官に化けた狸」(愛媛県の昔話)
むかし、狸が、ばあさんの家の沢山の柿を吊るしているやつを狙い、ついてきた。
タヌキが警官に化けました。「こんにちは、おばあさん、その吊るしている柿は見事じゃ。いい色してるなー。あの柿を一輪ぐらい、わしにくれないか。」
「ああ、ええとも、おまわりさんなら、喜んで」とおばあさんが一輪の吊るし柿を降ろしてやり、狸に渡した。そしたら、吊るし柿を首飾りにした狸が帰るとき、狸の右足が道端でトラバサミの罠に引っ掛かってしまった。そう、あのおばあさんは、最初から狸が警官に化けたことの匂いでわかってしまいました。(おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2024/07/08 (Mon) 07:03:09
おはようございます。
袋下げ (長野県の昔話)
むかし長野の大町にある一人の侍がおった。
侍が、昼間、街道を通っていたら、いきなり、木の上から白い袋をすっぽりかぶせられた。侍は、すぐさま、袋を脱ぎ捨てて、机の上ににらみつけた。すると、ガサガサと葉っぱの音がして、タヌキが顔を出した。侍は小さな刀を、タヌキめがけて投げつけた。小さな刀は、タヌキを飾って落ちた。タヌキは、体を丸めて他の枝に飛び移り、逃げていった。侍は独り言を言って、スタスタ歩いた。「タヌキの袋下げだ」(おしまい)
Re: えつこの部屋 - sisi
2024/07/11 (Thu) 02:24:04
これは笑わせる昔話です。
「チーズ知らず」(沖縄県の昔話)
むかし、店のおじいさんが、終戦間近に、喜如嘉(きじょか)のイザジキという浜辺からチーズを拾ってきて、親類同士で分け合って、少しずつ食べました。
おじいさんは、拾った役得として少し多めに食べたらしい。しばらくすると、おじいさんの妹にあたる母が、「あぁ、気分悪い」と、寝込んでしまった。それを見たおじいさんが、「私が、一番多く食べたんだから、私が早く死ぬんだなぁ」と嘆いたと言う。その後、みんな、なんでもなかったので、全然死んでなかった。それで大笑い、みんな本当にチーズとは知らなかったことだ。(おしまい)
2013/04/30 (Tue) 09:45:50
 行頭折り込み
行頭折り込み
お題の頭を取って文にする遊びが流行った頃の作品です
文:ゆうま&ぱられる
貼り絵&構成:ぱられる
Re: 行頭折り込み - sisi
2020/12/06 (Sun) 16:17:16
こんな面白い話あります。
白米城
むかしむかし、山の上に小さな城があった。
にわかに隣の国から攻められて、えらい難儀な戦さを続いた。城主は、(こちらも難儀で隣の国の軍勢もこう長い城攻めでは、さぞ、疲れておる。今一息頑張れば,攻め手もあきらめて,囲みをとくやも知れぬ。)と,思ったところへ,一人の家来は,そそくさとかきつけて、『殿様,大変でございます。」じっと,殿様の顔を見上げると,さも悔しくそうに,「大事な時に,城の水がなくなりました。」「なに,水がないだとー。」知らせを聞いて,殿様は,さっと顔色が変わった。
「この城の水は,わしらの命と同じだ。いよいよ落城かー。」唇噛んで,目を瞑り,あとは一言もおっしゃらぬ。そばの大将の一人はが言うた。「殿様、このうえに,皆々討死と覚悟を決め,すぐさま、敵の中へ討って出ることにいたしましょう。」殿様の許しを受けた大将が、最後の合戦を、味方の兵に知らせようと、本丸から下へ降りたときじゃ。百姓あがりの馬引きの男が、ひょこっと現れて、「旦那様、死ぬこたぁ、いつだってできますだよ。わしに,ちっと、考えがありますでー。」と、大将の耳にささやいた。すると、大将は、しばらく、いぶかしそうにしておったが、「よし、ものはためしということもある。それでは、城にあるお米を、集めよう。」お城中に集めたお米が、残らず、馬を洗う大きなタライの中に、入れられた。白い米の入った大きなタライに、お城の中から持ち出すと、外には、馬が並んで待っていた。
そこには南向きの日の当たるところで、敵の陣地からは,一番よく見えるところでした。馬の世話をする家来たちは、タライの中から、手桶で白米を救うと、ザーザーと、馬の背中にも、横っ腹にも、尻にも、ぶっかけた。この様子を遠くから見ておった敵方、驚いたって、「お城では水がなくなって、もうそろそろ、降参すると思っておった。それなのに、あのように、惜しげもなく水を使って、馬を洗うとはー。」びっくり仰天してしもうた。これはかなわぬと、攻めるものをやめて,さっさと自分たちの国へ,ひきあげたそうな。敵の陣地から見ると、馬にふりかけておる米が、お日様にキラキラ光り、ちょうど、水に見えたんじゃ。このことがあってから、誰いうことなく、この小さな山城のことを、白米城とよぶそうな。 おしまい
ステレンキョウ
むかしむかし、奉行所の前に,高札がたって、大勢の人が集まってた。漁師の浜介が通り、(一体、何事だ。)と、そばへよっていったが字が読めないで,人に聞くと、
けさがた、この浜で、奇妙な魚がとれた。その魚の名前が分からぬので、いいあてた者には,金子百両をあたえる。
と、書いてあるそうな。
(魚のことならー。)と、浜介は,早速、奉行さまの前に出て、みせでもらった。
(なるほど、これは,見たことねえ魚だ。)びっくりすると、奉行さまが、「これ、浜介とやら、それなる魚の名は、なんと申す。」突然聞かれて、浜介は、「テレスコと申します。」と、うっかり言うてしもうた。「テレスコと申すか。テレスコ・・・。なるほど、よく知らせてくれた。褒美をとらすぞ。」というわけで、浜介は、百両という大金をもらい、とぶように、女房のところへ帰った。さて、それから、ひと月ほどだった。あとのことでした。
また、奉行所の前に、高札がたって,大勢の人が、集まってる。高札には,
不思議な魚がおるが、名前がわからぬ、名前をいいあてた者には、褒美として、金子百両をあたえる。
と、前と同じようなことが書いた。浜介は,また奉行さまの前に出て、魚を見せてもらった。「浜介、そこなる魚の名はー。」「これは,ステレンキョウと申します。」浜介が、いい終わるか終わらぬに、奉行さまは,きつい声で、「ここな、ふらち者めがっ。これなる魚は,前の魚を干したものじゃ。浜介、そのほう、前には、その魚をテレスコと申し、今日は、ステレンキョウと申したな。お上をあざむき、またも金子を狙うとは、重ね重ねのふとどき者、打ち首の刑をもらうぞ。」というわけで、浜介は、牢屋に入られた。
今日は、いよいよ,打ち首になる日のことだ。お白洲にひきだされた浜介は,これが最後の別れというので、女房や子供に、ひと目会うことも許された。「これ浜介,あとに残る妻や子に,何か言い残す事はないか。」「はい、お奉行さま。」浜介は、後ろ手に縛られたまま、女房と子供のほうを向くと、しみじみと言うた。「いいか、お前たちは、これから先、たとえ、どんなことあろうと、決して,イカの干したのをスルメというでないぞ。」言いおわると,浜介の日焼けした頰に涙が流れた。そのとき,奉行さまはポンと膝を叩いて,「それっ,急いで縄を解け。」と,家来に言いつけて、縄を解かせると、今度は、自分が、ハラハラと涙を流して,「これ浜介、わしが悪かった。イカ干せばスルメ、テレスコ干せばステレンキョウになるのか、なるほどなー。」というわけで、浜介はまた、褒美に百両をもらい、女房と子供を連れて仲良く家へ帰りました。
おしまい
Re: 行頭折り込み - sisi
2022/07/13 (Wed) 22:38:25
どうもこんばんは。お元気ですか7月はもう既に入ってます。こんな昔話もあります。
3つの櫛(くし)
仙台市
昔々、あるところに伊勢参りに行くことになった男がいました。行ってくるからな。と男は旅立つことにすると、母親が、これは串が3つあるから、困ったことがあったら頼んでみてな。と言って3つの串をくれたのでした。その男は行く日か日を重ねて、原にさしかかりました。 どこか泊まる家は無いのか。と前を見ると、灯りのともっている小さな家を見つけました。頭叩くと、旅のものですが一晩泊めてください。と頼むと、優しそうな婆さんが出てきて、あーいいですよと言い、家へあがれと言ってくれました。男は晩飯までいただきました。朝早いものですからといって寝てしまいました。真夜中になると、すうすうと何か音がします。男はその音で目が覚めました。何かなぁ。と男は不思議そうに破れ障子からそっと中を覗いてみると、あっと声を立てているところでした。優しそうな顔の婆さんはすっかり鬼婆の顔顔に変わり、立膝をして、レバーをといでいるのでした。あの男は若いから美味そうだとつぶやいていた。その辺には人の骨が散らばっていました。男はブルブル震えながら、気は落ち着ければと思って、 あー、便所行きたい。 と言いました。すると鬼婆は、 便所行くなら縄を腰に結んでいけ。 と言いました。 わかりました。 と男はわざと平気な顔しました。男は便所に行って、自分の腰の縄をとき、代わりにホウキに結びつけそのまま一散に逃げ出した。鬼婆は縄を引き、まだなのか。 と言っていましたした。返事がないので鬼婆が来て、初めて騙されたことを知りました。こら待て待て。 出刃を光らせ、男の背後を追いかけました。追いつかれそうになって、男はふところから1つの串を取り出し、ぽんと投げて、 大きな大きな山になれ。 と叫びました。するとたちまち山ができて、鬼婆との間がさえぎられました。鬼婆はやっとこやっとこ登ってきて、また追って聞きました。また追いつかれそうな男は、2つ目の串をポンと投げ、大きな大きな川になれ。と叫びました。たちまちの水が流れて川ができました。鬼婆それでも、ザブザブと川へ渡って追ってきました。男は逃げながら3つ目の口をポンと投げると、大きな大きな穴になれ。 と叫びました。 たちまち、大きな穴ができましたが、鬼婆は穴の中に駆け込み、登り始めた。その時川の水が溢れて..あんなに流れ込んでしまったのでした。たすけてたすけて円と鬼婆叫びながら穴の底に埋まっていたのでした。男はそれから無事に伊勢参りを済ませたと言うことでした。終わり
しょんべんたれ
宮城県
昔々、馬子が旅人を馬に乗せて街道を通っていました。旅人は年寄りで頭がすっかりあげてしまいました。 阿武隈を渡ってけろ。 と旅人はいました。馬子は、いわれるとおりに、川の中に馬を引き入れて、ジャブジャブと流れを着ていきました。すると、馬子は川の真ん中でしょんべんをしたくなりました。お客さん、ちょっとしょんべんするからね。あと旨を止めようとすると、馬子さん、そいつはだめだ。川の中には川の神様がいますからしょんべんするとバチが当たりますよ。と旅人がいました。真子はそう言われると、仕方なくジャブジャブと流を切っていきました。すると、馬子は川の真ん中でしょんべんをしたくなりました。お客さん、ちょっとしょんべんするからね。と馬を止めようとすると、馬子さん、そいつはだめだ。川の中には川の神様がいますからしょんべんするとバチが当たりますよ。と旅人が言いました。馬子はそう言われると、仕方なく向う岸まで我慢しました。街道に出ると、 んではここでするべ と馬子は、道端でしょんべんをしようとすると、又旅人は、これこれ馬子さん、街道にも神様がいますよ、そんなことしょんべんすればバチが当たりますからやめてください。と言いました。うまくは困ってしまいました。しょんべんをすることができないので、いてもたってもいられなくない位になったりました。まもなく、旅人は、ちょっと休みたい。と言い、馬から降りて街道の脇の松の木の下に腰をおろしました。タバコを吸いたくなりました。馬子は、そっと松の木の上に登って旅人のはげた頭の上にジャージャーとしょんべんを食べたのでした。旅人は、あり、こんなにいい天気なのに、なんでまた雨が降ってきたのか。と上を見上げると、なんと馬子がしょんべんをしていました。なんだ、この馬め、人の頭に向かってしょんべんかけるなんて。ここさ降りて謝れ、謝れ。 と言いました。馬子は机の上から平気な顔でこう言いました。お客さん、俺はしょんべんがもれそうで我慢できなかった。川の中には神様がいるからバチが当たるからダメなのだ。街道にも神様がいるからダメなのだ。俺は死にそうで我慢できない。お客さんの頭に上がないからな。俺がかけたのだ。バチ当たることもないと思ったから。終わり 仙台市
弁之の土 宮城郡 昔々、野々島さ弁之助という男が住んでいました。正直男ですが、頭がおかしく里人たちは弁之と呼んでいます。
弁之の4つの時、父はなくなり、母親と2人きりで暮らしました。弁之は、毎日、母親の焼いてくれるやきもちを背負い、付近を売り歩くことにした。
「2文だからな。」
と母親によく言い聞かせられているので、弁之は、「やきもちニ文、二文。」と呼んでいた。里人がからかって、「弁之、3文負けてな。」と言っても ダメだだめだ。 と首を横に振った。またある日のこと。弁之は船でタバコを吸い、船べりで、ポンと吸い殻を叩いたので、煙間のカリ首が体中に落ちた。船は順風で走り、便の母、今落としたところの船紅山刀で印をつけました。乗り合いの男が、便の店辺の辺、なんでまたそこを左端のと傷に傷など作っておくなのかあくとうとうとからだ。
おしまい
だんぶり長じゃ
岩手県
昔々、二戸郡の母山村に、左衛門太郎と言う百姓が住んでいました。ある日、女将さんと一緒に、山の畑で働いていました。今お昼を食べてから、左衛門太郎は昼寝してうとうと眠りました。良い気持ちで寝て入った頃、どこからかだんぶりが飛んできて、左衛門太郎の口に尾を入れたかと思うと、向こうの岩のほうに飛んでいきました。行ったかと思うと、すぐまたゆっくり帰ってきて、口の中に尻尾を入れます。こうして頑張りは、2、3回同じことを繰り返したと思うと、どこからか飛んでいってしまいました。女将さんはこの様子を見て、なんと、不思議なことをだと思い、やがて、左衛門太郎が目を覚まして、女将さんに話しました。
「ちょっと眠たい間に、不思議な夢を見たんだ。なんでもだんぶりのようなものが飛んできて、とてもおいしい酒を口に入れてはかえり、口に入れてはかえりしたんだ。だんぶりは、大きな岩のあるところから、運んできたが、もっと飲みたいなーと思った、目が覚めた。本当に不思議な夢だった。」
女将さんは手を打って喜び、
「さてさて、その夢はめでたいことですと、その男ぶりの飛んできたところは、私がよくわかっていますよ。といいます。サイモン太郎にびっくりして、「お前さんが、私の夢を見たことをわかるはずはないだろう。「 と言いますので、女将さんは、 「いや本当ですよ。あなたが寝ている間に、こういうことがあったんだ。「 と詳しく話しました。
2人は連れだって岩の方に行って見ますと、だんぶりの飛んできたほうに、大きな岩がありました。そしてそこには綺麗な泉がこんこんとわいてた。左衛門太郎が早速、手にすくって飲んでいますと、夢で見たあのおいしいおいしい酒に間違いはありません。
「これはきっと、腹の神様が私たちにお授けくださったのだろう。「
「そうそう、あの男振りは、きっと、腹の神様のお使いには違いない。「
「ありがたいことだ。「
二人は大変喜び、この泉のほとりに家を建てて、そのお酒を売り始めました。不思議なお酒の話が、村々に伝わってゆき、遠くからも、たくさんの人が買いに行きました。毎日毎日くんでおりますが、くんでもくんでも泉の水はなくなりません。左衛門太郎たちには、しばらくするうち、たいした大金持ちになり、人々からは、だんぶり長者と呼ぶようになった。終わり
Re: 行頭折り込み - sisi
2022/07/16 (Sat) 10:45:21
「おらびそうけ」 (佐賀県の昔話)
むかしむかし、ある山に炭焼き男が、寝ないで炭焼きをしました。
朝になると、「あーあー。」と大きなあくびをした。
すると、向こうの方の山からも、
「あーあー。」と、あくびするものがいた。
炭焼きの男は、「俺の真似をするな!」と怒鳴った。
向こう側の山からも、「俺の真似をするな!」と、言い返してきた。
炭焼きの男は、それならと、歌をでたらめに歌った。
山の方から、
「でたらめの歌なんか歌うな!」と、怒鳴り返した。この妖怪の仕業は、おらびそうけという山の響く妖怪でした。
(おしまい)
(参考出典:母と子の図書室・おばけ文庫・ぬらりひょん、山田野理夫/著、太平出版社)
Re: 行頭折り込み - sisi
2022/07/16 (Sat) 14:46:00
鷺の湯 (岡山県美作市の昔話)
むかし、美作は沢田の中に、円仁という坊さんが歩くとき、何やら、湯気を見つけると、そこには、一羽の美しい白鷺が毎日飛んできてから疲れて休んでいるので、不思議に思ってみると、そこには湯気の立つお湯が湧き出ていました。白鷺が傷ついた体にお湯を浴びて傷を治したいたのでした。その白鷺のおかげで、温泉を発見した円仁から湯郷の人々へ伝わり、白鷺に感謝して、昔は猟師に出ても決して白鷺へは銃口を向けなかったといわれる。これを鷺の湯といいます。こんな質の素晴らしい湯は、湯郷温泉のひとつでもあります。今でも、JR姫新線(きしんせん)の林田駅を降りると、鷺の湯があるそうですよ。 (おしまい)
Re: 行頭折り込み - sisi
2022/09/24 (Sat) 19:02:28
 ご無沙汰しています。
ご無沙汰しています。
昔話です。
小判の虫干し
むかし、寝太郎と母がいた。
寝てばかりせんと、山へ働け。と母に怒られ、寝太郎は外に出た。
海の見える山へ登り、昼寝をしょうと・・・
寝太郎のそばにネズミたちが虫干しのため、小判を運んだ。
ネズミのお宝 小判の虫干し 猫のいない間に ホイホイ と歌った。
山の一面に置いた小判はキラキラ光った。
それを見た寝太郎は楽しく眺めた。
日が暮れると、ネズミたちが虫干しした小判を引き返した。
寝太郎は仕事せず家に帰り、母に叱られた。
トントン!若い娘が来て、寝太郎が小判の虫干しを見張ったお礼に小判をさしあげた。(おしまい)
Re: 行頭折り込み - sisi
2022/10/03 (Mon) 06:59:21
カツオのつくり身
高知県須崎市の昔話
土佐の海には、カツオがよくとれる。
むかし、土佐は須崎の津野山というところに若いカツオ売りの男がやってきた。
そこには津野山にすむじいさんがきて、カツオをどうやって食うのかと聞いた。
「カツオはな、つくり身にして、ちょっと置くがいい。」
「え〜、それは初耳だな。」
じいさんは、家の庭にある松の木のもとに行き、買ったカツオを置いた。
3日がたつと、なんと、カツオにウジ虫がわいてきた。
じいさんは、「これこれ、カツオのつくり身に芽が出たぞ。」といった。
じいさんは、芽が出たつくり身を食べた。
(おしまい)
Re: 行頭折り込み - sisi
2024/01/16 (Tue) 00:16:14
「鶴とガチョウの八幡まいり」(大阪府枚方市の昔話)
むかし、仲のええ鶴とガチョウが石清水の八幡さまにお参りした。ええこと願って拝んでます。
二人は八幡まいりをすましたあと、牧野の里へ家に帰るところ、樟葉の里で歩くとき・・・。
草むらから狩りの男がそっと来て、鶴とガチョウの姿をのぞいた。
そのとき、男は弓矢を引いて、二人を狙った。
鶴は飛び出して運良く逃げたんや。
ガチョウは体が重いから運悪く飛べなかったので、とうとう狩りの男に捕まったんや。
男はガチョウを鍋にして死んでしまった。
鶴はガチョウのことを悲しんで、「ガチョウ、ガチョウ!」と泣きながら飛んでしまった。(おしまい)
Re: 行頭折り込み - sisi
2024/01/21 (Sun) 09:40:47
「犬と鶴」(大阪府枚方市の昔話)
むかし、枚方は養父丘というところに犬と鶴がおった。
お互いにせっせと畑仕事をした。
犬は、「鶴どん、今夜はオラの家ヘ晩酌しないか」と鶴を喜んで誘った。
犬の家で鶴を招き、晩酌した。
「鶴どんに見せたいもんがある、オラが集めた平皿やで、色も形もええ、さあさあ、この平皿で酒飲んでや」
平皿の酒を犬が舐めながら飲みほぐした。
一方、鶴は自分のくちばしで突付いても平皿の酒は飲みなかった。
「なんや、鶴どん、平皿の酒は気に入らなかったのか、ああ、もったいない、せっかくやから、オラが代わりに飲んだるで」と犬は鶴の分を飲んでしもうた。
「なあ、犬どん、今度はお礼として、明日の晩、オラの家ヘ晩酌しないか」と鶴が犬を誘って喜んだ。
次の晩、鶴の家ヘ犬を招いた。
「犬どん、これはな、オラが集めた首長いツボや。さあさあ、このツボの酒を遠慮なく飲んでくれ。」
鶴はツボの酒に自分のくちばしを入れて飲みほぐした。
一方、犬はツボの酒をどうやって飲むのか、わからなくなった。
「犬どん、ツボの酒が気に入らなかったのか。ああ、もったいない、せっかくやから、オラが代わりに飲んだるで」と鶴は犬の分まで飲んでしもうた。
これはまんまと返されてしもうた。(おしまい)
Re: 行頭折り込み - sisi
2024/01/28 (Sun) 12:33:44
「蝉と白ギツネ」(大阪府枚方市の昔話)
むかし、枚方は北楠葉のところにメスの白ギツネが住んでおった。
夏の暑い日、白ギツネが歩いていくと、木の高いところにいる蝉の鳴き声が聞こえた。そこで考えた白ギツネは遊女に化けて、蝉を狙った。
「あーら、蝉はん、あんたの鳴き声がいい音色で気に入ったわ、どうかお付き合いしてほしいから、降りてくれませんか、美味しいご馳走も待ってます。ねえ、降りてください」
「そうやな、ええやろ」
白ギツネは手ぬぐいを敷いて、蝉が降りてきた。
その蝉をいきなり白ギツネが食った。と思いきや、なんと、羽だけつけたフンが蝉を似せようとしたもので、騙されてしもうた。「うー、臭い」と白ギツネは悔しがった。
「あんた、白ギツネやろ、わしはな、遠くの匂いでわかるんや。ハハハア!」と蝉は降りることできないから、お見通しだ。まあ、こりゃ一本とられましたわ。(おしまい)
Re: 行頭折り込み - sisi
2024/03/01 (Fri) 00:35:23
 「雪地蔵」(北海道の昔話)
「雪地蔵」(北海道の昔話)
むかし、強い風が吹く日のことです。「お地蔵さま、街お使いに行ってきます。暗くなる前に帰ります。」せん吉は、毎日こうして、お地蔵さんにご挨拶をしているのです。ぴゅーぴゅー!町からの帰り道、急に雪が降り始めました。
ゴォーゴォー!
風はますます強くなり、あっという間に吹雪になった。「前が見えない。」
目も口も開けていられないほどの大吹雪です。ズボッズボッ!「もう歩けない。」それでもせん吉は頑張って進みました。「あれ、ここはどこだ?道がわからない。家はどっちだ?どうしよう。」
そのうちに吹雪の中に黒い影がぼんやりと見えました。「あれはなんだ。」せん吉は目をパチパチさせました。「誰かいる!おーい!おーい!」
「待ってくれ。一緒に行こう。」せん吉は大声で呼び出しました。ゴォーゴォー!「落ち着いた!」と思っても、黒い影はどんどん行ってしまいました。「絶対ついていく!」せん吉は、転んでは起き上がり、雪だらけになって追いかけた。一体どれだけ歩いたことでしょうか。急に吹雪が止み、目の前に木が見えた。
「せん吉ー。」
「母さん、ただいま!」「お鼻とほっぺが真っ赤だよ。」「よく帰ってきたね。」みんなが喜んだ。せん吉は、(さっきまで前を歩いていた人は、どこに行ったんだろう。)と思いました。
家の帰り道、お地蔵さんの祠の前を通りかかると、「見て!」せん吉がお地蔵さんの所へ続く足跡を見つけました。
祠の扉を開けると・・・。
いつもの場所に、白い雪をかぶったお地蔵さんが笑っていました。「ああ、ありがとうございます。町へおつかいに行って来ますって、お地蔵さんに言って出かけたから。それを聞いていたお地蔵さんが、心配して連れてきてくれたんだ。」せん吉は、涙を流してお礼を言いました。
せん吉が吹雪の中で黒い影を追いかけたことを話すと、「不思議なこともあるもんだ。ありがたいね。お地蔵さんのおかげだよ。」お母さんもお礼を言いました。
それから、このお地蔵さんは幸地蔵と呼ばれるようになりました。(おしまい)
(参考出典:童心社紙芝居・ゆきじぞう、重松みさ/著)
2014/08/16 (Sat) 22:49:08
Re: Re: 月 - sisi
2021/01/03 (Sun) 08:34:55
新年あけましておめでとうございます、2021年は丑年。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
新春にふさわしいような面白い昔話もあります。
「あやしい大岩」
(新潟県)
むかし、越後の国のある山の近くの村に、釣りの上手い男がいました。男は毎日釣りへ行く時、いつも近くの山の渓流へ行きます。渓流には多くの釣り人たちがやってきます。木陰や岩の下、流れの曲がり角など、それぞれ自分の釣り場を決めて、糸を垂らしているようでした。男は渓流にやってくると、自分の釣り場と決めている岩の上に、座りました。そしてツリーとたらし、どうしたことなのか、その日の昼過ぎになっても、一尾も釣れませんでした。そこで男は場所を変えることにして、近くを諦め、少し坂を登る渓流へ変更すると山陰に突き出た大きな岩がありました。なんだか変わった岩でした。表面が土色で油で磨いたようなツヤをしていました。
「いい場所だ、ここなら釣れても大丈夫。」男は大岩の上に、座り込んで、釣りとたらした。しばらくして、雑木林の中から若者の男が降りてきて、淵の向こう岸で釣りを始めた。ところが若者は、どうしたのか、すぐに釣竿をおさめて、こちらに向かい、何事か口走りました。淵の水の音は静かだけど、少しの声も聞こえない。そこから早く外へ行けと言うふうに、酒に手を横に振って合図をしながら、慌てて向こうの雑木林の中を登っていきました。「あの男は、何を言ってるのかわからない。驚いて去っていたが、何にもないじゃないか。」
男は半分笑いながら、つぶやきました。
それからしばらくして、釣り糸を垂らしましたが、やっぱり魚は釣れない。先程の若者のことも、なんとなく気になった。「今日はだめだ、これでやめ、帰るしかない。」男は釣道具を手早く片付け、先程の若者を大事にして、何を言ったのか気になり、それを聞いてみたいと思い、渓流を渡り、崖の上に出て、若者が先を歩き、男は早足で近づき、「先程は失礼しました。何かあったんですか。」と尋ねました若者は、ジロジロ見つめると、ため息のような大きな息を吐き、「あなたはもしかして、何も知らなかったのですか。」反対にたずね返した。「何も知らない?」男は口ごもりした。「あなたが座っていたあの淵の大岩が急に両眼を開いて、大きな口を少しずつ開けてあくびをすると、また目をつぶってました。赤子の頭ほどもある、その目玉の赤いこと、私は恐ろしくて、ものも言えなかったでした。あれは、山の中に住む大きながまがえるでしょうか。」若者は身震いをすると、そこでまた大きなため息を吐いたのは、なんと、あの大岩の正体は、ガマガエルでした。
あー、恐ろしかった。
(おしまい)
Re: Re: Re: 月 - sisi
2021/01/10 (Sun) 19:14:49
とんでもないような昔話もありました。
「猫と犬と河童」
(長崎県の昔話)
むかし、長崎の小浜に、大変怠け男がいまして、嫁はもらいましたが、働く気は全くない、朝からだらしなく寝込んだり、飼っている猫や犬の遊びまくりな暮らしでした。
見かねた伯父が元手は出すから少しは働いてみろと言うと、男はやっとその気を起こして、そして魚売りをやってみようと考えた男は、魚の市場へ出かけますと、獲れたばっかりの一番大きな鯛を1尾仕入れて魚に土がついているので海辺で洗うと、魚が急に暴れ出して逃げてしまった。男が家に帰ると、また伯父がやってきて、もう一度元手を出してくれたので、今度は慎重に仕事をしようと考えました。翌日、仕事探しに家を出ると、見知らぬ男が近づいてきて、妙なことを言った。自分は竜宮からの使いもので、男迎えに来ました。男は、
「滝宮へはいちど行ってみたいと思っているが、海底にあるので行くことができない。」と言うと、使いの男は自分と一緒なら何も心配することは無いと言い、目を閉じ、手を引いて海に入って、男を海底にある竜宮へ案内しました。竜宮につくと、美しい乙姫が出迎えてくれた。男は乙姫に、「あなたは、私の使いである体を伸ばしてくれた恩人でもあります。」
とお礼を言われ、指輪を渡されました。その指輪は、指につけて右に回すと米蔵と金蔵が出てきて、左に回すと大きな家が出ると言う魔法の不思議な指輪でした。男はその指輪をもらい、喜んで家に帰ると、そして指にはめた指輪を左に回すと、目の前に大きな2階建ての家が現れた。次に右に回すと、今度はお金がザクザクと溜まり、金蔵と米倉が現れた。男は夢中になり、もう一つ金蔵を出そうと思い、力込めて指輪を回すと、蔵は現れたが、その金蔵は空っぽでした。男は空っぽの蔵の中へ櫃を置くと、そこへ指輪を大事にしまっておくことにした。ある日、男の留守中に嫁が蔵の中に入り、櫃の中に隠してある指を見つけ、ちょうどそこへ沖の島から飴屋がやってきたので、指輪を飴玉等と理解してもらいました。家に帰った男は、蔵の中の筆を開けてびっくりした。そして嫁の話を聞くと、烈火の如く怒りだした。「あの指輪は、宝物の魔法の指輪だ。この家も蔵もみんなあの指輪のおかげだ。それを飴玉と取り替えてしまうなんて、どうしてくれるんだ。」
男と嫁の大喧嘩のやりとりをそばで聞いていた猫と犬は、その指を取り返してくれば、今までよりもっと可愛がってもらえるに違いない、おいら達で取り返してこようと相談して、沖の島へ出かけていきました。島へ渡ってみると、飴屋の家はすぐに見つかりました。
様子を伺い、飴屋は行商に出ているのかと留守番でした。猫が家の中へ入り、幸いなことに目の前の棚の上に指輪が置いてありました。ところが、指輪をどちらが持って帰るかと段になると、猫も犬も功名を立てたいあまりに、自分が持って行くと言って譲らない。結局、指輪を発見した猫が持って帰ることになり、猫はしっかり指輪を加え、わき目もふらずに海へ泳いだ。
すると途中、おいしそうな魚がピチピチとした体を動かして目の前を通りかかった。猫がたまらなくなって思わず口を開き、指輪は海の中へ落ちていった。そこでまた海の中で猫と犬の喧嘩が始まり、その時、2匹の間に、河童が顔を出し、河童はなぜか真っ赤な顔して怒り出した。
「お前ら、あんなもんを海底へ落とした困るから、何か引っかかって、まぶしくて、危なくて、潜ることも居ることもできないから、早く拾って持って帰ってくれ。」
ところが猫も犬も水の中に潜ることができません。そこ河童に取ってきてもらうと今度は犬が指輪を口にくわえ、猫を背に乗せて、走って家に帰ってきました。
そして、指輪を男に手渡し、男は喜び嫁においしい料理を作らせ、猫と犬に満腹してもらうごちそうをしてやりました。みんな幸せになりましたね。 (おしまい)
Re: 月 - sisi
2022/05/28 (Sat) 13:07:52
「猿寺」 (東京都中野区の昔話)
むかし、元禄の頃の話。
江戸は神楽坂にある松源寺があり、その境内には、いつも野生の子猿が遊びに来ている。
ある時、そのお寺の和尚の留守の間に小僧や悪童たちが猿を捕まえられて、浅草橋場に住む檀家の武蔵家に売り渡した。
翌年の春になると、和尚は向島の花見に招かれました。竹谷の渡しに差し掛かったが、そこには花見する人々で、ごった返し。今も和尚が船に乗り込もうとした時、衣の裾を持って話さずものがある。見るといつもの寺へ遊びに来ていたあの子猿でした。不審に思う所へ武蔵屋が駆けつけてきて、「おーい、私の猿が逃げた!」と言いました。武蔵屋の持ち分を聞いているうちに、お客さんを満員した船が岸を離れた。「しまった、乗り遅れたわい。」と言っているうちに、川の中ほどまで行った船は、二、三度大きく揺らいだと思うと、あっという間に転覆した。多数の人たちが死に騒ぎとなった。あの時、もし子猿が引き留めなければ、和尚は一命を落としたところであった。和尚は武蔵屋に乞うて子猿を連れ帰り、大事に飼いました。
今でも中野の上高田にある松源寺を猿寺とよび、あの子猿の石像も残っておったそうな
。 (おしまい)
Re: 月 - sisi
2022/05/30 (Mon) 03:31:58
北方と南方の村境
(広島県の昔話)
むかしむかし、本当の話かどうかはっきりしたいませんが、それはとにかくとしてお聞きください。面白いですから。
お話といいますのは、東南です。
豊田の本郷の奥に、広い野原を挟んで2つの村がありました。野原には牛や馬が離されて、美しい草原の中を駆け巡って遊んでおりました。草原の真ん中には1本の松木がそびえて、その松の木を境にして、北の方が北方、南の方が南方と分かれた。
広島県の地図を出してごらんなさい。山陽本線の河内駅と本郷駅の間、下のほうに、つまり南に寄ったところに北方、南方の地名がありました。
ところがある年の事、この辺にひどい干ばつがあって、南方と北方の村境の目印になっていた松の木が枯れてしまいました。さぁ、こうなると面倒が起こってきました。村境の目印がなくなったのですから、2つの村の人たちは、どちらも負けずに少しでも余計に自分の村のものにしようと、野原のあちこちで争いはじめた。
「この松の根元が証拠だ、ここまではわしら村のの土地だ。」「いや、その根元は昔からあったものだ。あの松の根元が境じゃ。」「こりゃそうじゃ、ここのところの草はわしらの村の馬が食べていた。」
とにかくこんな言い争いが、毎日毎日、朝から晩まで続きましたので、平和の住みよい村も騒がしくなって、村人たちは落ち着いて仕事に手がつきません。
とうとう庄屋さんどうしたが話し合いをして、村境を決めることにしましたが、どうにもいい考えがありません。そこで馬の駆け比べをして、村境を決めることにしました。北方のものは北の端から、南方のものは南の端から、それぞれ一番鶏が鳴くのを合図に駆け出して、両方の馬の出会ったところを境にしょうという。これからはどちらの村人も、文句の言いようがありません。それがよかろうと話し合いはすらすらと運び、かけくらべも明日と言うことになりました。北方の人たちは、村一番の馬を選びだすと、これも村一番の乗り手という若者を庄屋さんの家へ泊まらせて、ご馳走を食べさせるやら、馬の足を撫でるやら、大騒ぎでした。
南方の人たちもみんな庄屋さんの家に集まって、よりだした馬と若者を囲んで、一生懸命励ましています。しかし、庄屋さんはじっくりと考えて、「馬も若者も今年は早めに出させろ、明日疲れるからな、ご馳走が食べたければ明日うんと走って、少しでも余計にこっちの土地にしてくれ、そうしたら、たらふくご馳走食べさせるぞ。」と言いながら、1羽の雄鶏をよんで、「お前さんには今夜うんとご馳走を食べさせてやるが、明日鳴き遅れでもしたら大変だからな。」と豆だの、とうもろこしだの、たいそうご馳走を食べさせるのでした。北方のものはだれも鶏の事には気がつきません。それどころか、馬と若者の方ばかり気をとられて、その夜は鶏に餌をやるのさえ忘れてしまいました。明くる日になり、北方の鶏は何もう食べないで寝たので、お腹が空いて夜明け前には目が覚めてしまいました。そして早く何か食べさせろ!と大きな声で泣き叫びました。それ、と村人は若者を呼び起こして馬に乗せましたが、前の日遅くまでご馳走を食べていた若者は寝ぼけてしまったて、とんでもない方向へ走っていってしまいました。それにひきかえ、南方の若者は早めに目を覚ましました。すっかり支度を整えて鶏が鳴くのを待っていました。が、お腹がいっぱいでぐっすり眠ってしまった鶏は、夜がが明けても泣きません。我慢しきれず、とうとうたたき起こして鳴かせると、一目散に駆け出しました。でも、何も食べさせていない馬はすぐにヘトヘトになってしまい、思うように走りません。
北方の若者はしばらくして、はっと目を覚ましましたが、とんでもないところへ来ているのに気がつき、まわれ右をして馬にひとムチあてました。馬はたくさんご馳走を食べて元気が良いので、さっきよりも早く駆け出しました。
そして、勝負は、南方の馬がやっと野原の真ん中あたりに来た時、ものすごい勢いで北方の馬がやってきました。そしてちょうど真ん中あたりで出会いました。
(おしまい)
「ノミと旅人とおばあさん」
(広島県三次市の昔話)
むかしむかし、あるところに吉三と言う、村からむらへ、町から町へ薬を売って歩く商人がありました。吉三は毎年決まったように旅を出て日が暮れたら、宿に泊まって、また隣の村へと出かけて行きます。昔の事ですから、村には宿のないところもありましたが、そんなときには村の百姓さんの家に泊めてもらいます。
ある日の事でした。吉三は山はずれの小さな村へやってきました。商売も済んだので、一軒の家に泊めてもらうことにしました。その家には、欲の深そうなおばあさんがただ一人住んでいました。吉三はお礼にたくさんの薬をおばあさんにやり、寝ようと床の中に入りますと、床の中にはそれはたくさんのノミがいて、とても眠れそうにありません。けれどもせっかく泊めてくれたおばあさんに、ノミがいるから眠れないとも言えず、とうとうその晩は、一睡もできないままに夜が明けてしまいました。吉三は、それから隣の村まで行って、また帰りにこの家に泊めてもらわなくてはならない。
そうしなければ、山深い夜道を歩いて狼にでも食われてしまう。明くる朝、吉三は眠そうなはれぼったい目をこすり、おばあさんに言いました。なんとかノミを退治してもらっておかなければ、帰りにまたこんなことではたまらないと思いました。「おばあさん、あんたは大損をしてますよ。」と話しかけますと、欲深いおばあさんは膝をのりだして、「何かいいもうけでもありますかいの。」
と聞いています。そこで吉三は、「おばあさんとこには、たくさんのノミがウヨウヨしてますが、ノミは万病を治すという薬になるんで、私の国ではたいそう高い金をだして買い集めてるんですよ。おばあさんはなぜ売らない。」
と言いました。するとおばあさんは目を丸くして、
「へぇー、ノミが薬になるとは初めて聞きました。薬屋さんのあんたが言うんだからまさか嘘では無いでしょうね、帰りにあんたがこの家へ泊ってんまでに、たくさん取っておきましょう。」
こう言って、吉三は隣村へ出かけました。
2、3日隣村で商売をした吉三は、帰り道におばあさんの家に泊めてもらうことにしました。おばあさんがよほど念入りにノミを取ったと見えて、その晩、1匹のノミも出て来ません。吉三は気持ちよく眠りました。明くる朝、待ってましたとばかりおばあさんが、「吉三さん、約束通りこんなにノミを取りましたよ。」と言いながら、紙を包み広げてみますと、よくもまぁこんなに思えるほど、たくさんのノミがいました。吉三は、「ほう、これはたくさん取ったものですね。1000匹もいるでしょうね。」と言いますと、欲深いおばあさんは、ノミがお金になると聞いているものですから、「何を言いますさん、1000匹どころか10,000匹もいますよ、吉三さんの前で教えてみましょう。」と紙包みを広げて、始めました。
教えるはしから、ノミはぴょんぴょんと逃げてしまい、100匹も数えたと思った頃10,000といたノミは1匹もいなくなってしまいました。そこで吉三は言いました。
「おばあさん、今度来る時までに、50匹ずつ串に刺しておいてください。そうしておかないととても教えることはできませんよ、今度来た時もらって帰りましょう。どうもお世話になりました。」
こうして吉三はまた旅を続けました。
ノミが薬になるなんて、とんでもない話でした。
おばあさんの欲深い気持ちも汚なければ、おばあさんをこんなことで騙そうとした吉三の心持ちも、ノミ以上に汚いではありません。
(おしまい)
Re: 月 - sisi
2022/06/18 (Sat) 09:15:28
 こんにちは、怖い話です。
こんにちは、怖い話です。
首なしライダー
(茨城県の昔話)
むかし、筑波山では、毎日スピードを狂うライダーたちが夜中にやって来て、暴走しているらしい。ある時、アベックで2人乗りをしていたライダーが反対車線を猛スピードで来る何かを見ました。その、人らしきものはすれ違いざまに、ほんの一瞬だけちらっとこっちを見ました。男の人は前を見ていたのでよくわからなかったけど、後の女の人の様子がおかしいので男の人が、「どうしたの?」と尋ねると、「今の人、顔がなかった・・・。」と言った。
(おしまい)
Re: 月 - sisi
2024/01/30 (Tue) 01:38:14
「熊とカワウソ」(大阪府枚方市の昔話)
むかしむかし、枚方は出屋敷というところに、くいしんぼな熊がおった。熊は、この場所の木の実や畑の野菜を盗んで、みんな食べてしまい、土地の動物たちは熊のことが怖がって捕まることができへんかった。それでも困ってしもうた。
熊はその後、みんな食べたから、な~んも食べるものがない。そこに歩いているのが、カワウソが魚を売りに来た。熊はカワウソの魚がたまらなかったので、声をかけた。
「うまそうな魚がたまらへんな~」
「おいおい、お金がないと、食べられへんで」
「ほな、ナンボはするんや」
「1尾一文」
「オラは金あらへんから、どこで釣ったらええんや」
「これだけは二人だけの秘密やからな、よーく聞けよ、お隣りの山田池という大きな池があるんや、魚はいくらでも取れる」
「どないして釣るのか」
「それは、自分の尻尾で釣るんや、簡単なことさ、夜のうちに山田池へ尻尾を垂らして釣り、朝明けになり、池の氷が張るまで、じっと待ったら、魚がたくさん来るんや」
「ありがとう!釣るぞ、釣るぞ!」
熊は山田池の水に自分の尻尾を垂らして氷になるまで釣るのを朝明けまで待った。じっと待っても熊の体が凍えながら我慢をした。
朝になると、氷ができて、いよいよ熊の尻尾を引っ張ります。「これはたくさん釣れたぞ!うー重い!」と思ったら、尻尾が重くて必死に引っ張ったが、とうとう引きちぎってしまった。引いたら、熊の尻尾は短くなった。
「尻尾で魚を釣れるわけ無いやろヒヒヒ」と笑いながらカワウソだから嘘ついて教えたんや。(おしまい)
2016/01/04 (Mon) 10:45:46
 sisiさん
sisiさん
新年おめでとうございます。
佳き新春をお迎えのことと存じます
今年もよろしくお願いします。
テレサテンの似顔絵も素敵 歌も大好きですぅ。
歌も大好きですぅ。
仮屋崎省吾さんの作品が松山城を彩りましたぁ。
Re: 初春 - sisi
2020/12/02 (Wed) 16:34:09
華さんありがとうございます。こんな昔話あります。
デシコシ鳥
(香川県の昔話)
むかしむかし。
ある村に和尚さんと小僧さんがおりました。
ある日、小僧が山へ行っていも掘りに行きました。
小僧は、和尚さん思いで知ったから、芋のおいしそうなところは和尚さんに上げて、自分の芋の尻の砂まじりのところを食べました。和尚さんは、芋を食べたとき、あまりにも美味しくてたまらなかったので、小僧はどんなにうまいところを食べているかと思い、
小僧の腹を切って中を見ました。すると腹の中には、お芋のクズや尻の悪いところばかりが入っていきました。それで和尚さんは鳥になってしもうて、弟子こいし、弟子こいしと鳴いているそうだ。デシコシ鳥は田植えごろによく鳴いています。人によっては、ホトトギスだと言う人もあります。
(おしまい)
田舎の黒鳥
(石川県の昔話)
むかし、鵜川の三田に四郎右衛門というものがおりました。都へ登り、某中将とが申す貴族の屋敷に仕えて、庭はき掃除をしていました。
四郎右衛門は誠に愉快な男で、また、歌うと言ったら、三度の飯より好きな男でしたから、暇さえあれば、ホウキを逆さに、大きな声で歌を歌いながら、踊っていました。
ある日、某中将の姫君がこれを聞きつけました。みすをかかげて見れば、男の格好がまるで気違い沙汰でしたから、つい、罵っていました。
「お前の声は、田舎の黒鳥そっくりだよ、早く、仕事でもやり。」
すると、四郎右衛門は歌で持って答えました。
「羽うち揃えてた時は、中将姫の下に見る。」ところが悪いことに、2人の様子を姫の母君が見てしまいました。そして母君が言いました。
「姫、その他の仕草は、我ら貴族にあるまじきこと、このままには置かれません。ささ、今すぐにも、この屋敷を出てもらいましょう。」
姫君はしきりに許しをこいますが、受けられず、それで今は仕方なく自分の屋敷を出ました。けれど、どこへ行くあてもないので、ただ泣きながら門の外をさまようばかりでした。四郎右衛門はこれをいとも哀れに思い、
「もしよかったら、俺の里へ行きませんか。」と言いました。
それではというわけで、姫君は連れだって能登の諸橋につきました。
その時は船路を取ったので、元に着いたところ、今でも姫崎と呼んでいます。
2人はそこから山田川を遡り、程良い場所に住居を構えました。2人は美しく暮らしました。
ほどなく、息子が生まれましたが、村人はそれにちなんで、ここは産田(さんでん)と言うようになりました。今の三田がその名前でした。
(おしまい)
Re: 初春 - sisi
2024/01/28 (Sun) 23:21:09
「鶏の田植え」(大阪府枚方市の昔話)
むかし、枚方は出屋敷というところに、雄鶏と雌鳥という鶏の夫婦と息子のひよこが住んでおった。6月に入ると、鶏の夫婦が広い田んぼに田植えを始めた。ひよこも手伝った。そこには田んぼの裏にいる白鷺と犬と猫の仕事もしないぐうたらな三匹がおった。「おーい、お前らも田植えを手伝ってくれへんか」と雄鶏は三匹を誘っても、「無理やな」「あ〜そうやな」「田植えやったら腰が痛くなるで〜」と無駄やった。夫婦とひよこは、毎日汗流しながら、楽しく田植えを続けた。寝てばかりのぐうたら三匹は、「相変わらず懲りないなぁ」と言った。そして秋を迎えた。夫婦とひよこが植えた田んぼの稲がますます黄金色に実ってきた。お隣りの雀の家族は、「鶏はん、いつも稲がえらい実ってきたわ」と感心した。稲の収穫が米に生まれ変わり、鶏の家族は、張り切って、たくさん握り飯を作った。作りすぎた握り飯はな、鶏が食べるだけではなく、お隣りの雀の家族に差し上げたり、あったか握り飯の匂いからきたぐうたらな三匹もあげて、えらい喜び、むしゃむしゃ食った。鶏の握り飯はホンマにうまかったそうな。(おしまい)
クリスマス2013 - sisi
2013/11/27 (Wed) 21:14:26
Re: クリスマス2013 - sisi
2020/12/12 (Sat) 13:07:03
こんな話あります。
宝の下の鶴、宮崎市、昔、大淀川の下北の高台に七兵衛という男がいました。ある日、七兵衛が高台の崖の上で馬草を刈ると、大淀川の宝の下という淵に一話の鶴が舞い降りた。これは、きれいな鶴だ。役人に知らせなければ、ご褒美もらえるかもなぁ。と七兵衛はこうつぶやくと、鎌を投げ捨ててお城へ出かけていきました。七兵衛の知らせによって、狩野好きな役人がやってきて、一発のもとに鶴を仕止めてしまったので、ご褒美のお金をいただきました。
ところがこれを知った村人たちは七兵衛は、強欲な人間で昔から宝の下に魔神ガ住んでると言って、だれもよって行かない所なのに、今の七兵衛のやつは、あの祟りが来るかもしれない。とうわさをしていました。村人たちの噂はたがわずに、そのあたりが起きてしまいましたその日の夜になると、七兵衛は夜中に夢に怯えてふらふらと床を抜け出して彷徨始めました。七兵衛は血の気を失いブルブルと怪しい起こりに取り付かれていました。もちろん寝静まった家の人は、誰1人としてそれに気づきませんでした。夜明け近くになり、厩の2階に寝ていた下男ノ与吉は不気味な噂の声に目を覚ましました。何の音だ。と恐る恐る様子を降りて行ったのですが、ところが与吉はすっかり驚いてしまった。厩の片隅に血のしたたる鎌を投げ出して、全身血まみれになった七兵衛が倒れていた。七兵衛は草刈鎌で、自分の首をかき切ったのですが、死にきれずあたりをのたうちまわっていた。騒ぎに起こされた家の人たちが、慌ただしくかけてきましたが、まもなく七兵衛の息はたえてしまいました。それだけではない。ツルの祟りはその夜も続き、七兵衛の家に飼っていた猫や鶏が姿を消し、元気な馬も一夜のうちに死んでしまいました。 あれは宝の下の魔神が怒りだし、鶴の祟りに間違いない。
恐れる村人たちのすすめで七兵衛一家は土地を離立てれた。
そして、宝の下の崖に、小さな祠をて奉りました。終わり
Re: クリスマス2013 - sisi
2022/06/23 (Thu) 23:16:46
「七福神の井戸」
(青森県黒石市の昔話)
むかしの明治5年の11月4日のことである。青森は、黒石の町はずれの野際の部落に、水のみ百姓の岩次郎というものがおり、その娘におたみと言う働き者がいた。16歳である。この岩次郎のところに近頃、米と小判が湧く言う。隣近所の者はそれを聞いて、変な陰口を叩くものもいた。「岩次郎のやつ、働き者だと思い、朝晩、よそのものをかすめて、ため込んだのでは無いのか。白米だの拒んだの、湧いてくるなんて、聞いたことない。」もちろん、岩次郎は、そんなことをする男ではない。朝から晩まで田畑で働いた暮らしは一向に良くならなかった。だが、人のものを盗んだまで、楽をしようと思う心など、これっぽっちもない、いたって正直者でした。おたみにしても同じこと。家のためにも、そろそろ娘の話も出ている自分のためにも、もう少しましな暮らしをしたいと毎日頑張っていたが、よそのものに手をつけることだけは神仏に誓ってすることがなかった。
その日の朝早く、おたみは水汲みに行こうと、つるべのところに袋が1つあった。口が開いてあったので見ると、中には白米一升ぐらいとその上に小判が1枚のっていた。この袋は心では見たこともない絹でできていた。隣近所に聞いてみたが誰も知らないという。どこから来たか騒いでいるうちにその日はくれた。
翌日、おたみはまた、朝早く井戸へ行ったらなんと、昨日と同じものが同じところにあるのではないか。
「父ちゃん、また、同じどこに、同じ物が出てるよ。」
おたみは、すっとんと声を上げて家の鍵かけむしろ大付飛ばしして走り込んでいった。「どれどれ。」父も母も、草履も履かずに走ってきたが、やっぱり同じところに同じものがあるではないか。「おらたちさ、くれるのかな。誰が、だれがこんなこと、するのかな。」いろいろ言ってみた。触ってみると、綺麗な白米と小判でした。
次の日は、あまりいい天気ではなかったが、どこの家でも作業場で稲こきをしていた。おたみも西側に小窓を一つしかない作業場で一生懸命いなこぎしていた。お昼過ぎ、どーん、どーん、どーんと底鳴りするような気がした。おたみは耳をすましたが、気のせいだろうと思い、そのまま仕事を続けた。そのうち、「ドサッ。」「チャリン。」という音と一緒にあの小窓から、またも白米一升と小判一枚投げ込まれたのである。びっくりしたおたみが小窓に駆け寄った時、外には何も見えなかった。ただ裏のサワラの木がかすかに揺れた。
「おたみー、おたみー。」
と、何か困ったような声で呼ばれているような気がして、みみをすますと、声は井戸の中から聞こえてくるようになった。おっかない半分で、小田実が井戸の中を覗くと、なんと、中には美しく着飾った女が立っていました。その顔は全く弁天様のようでした。女は、おたみに言った。「私は川の神ですが、心配しなくてもいい。おたみ、私と一緒においで、あと一時もすれば、またあなたをここへ返してあげます。あなたに頼みたいことがあります。それが終わったら御礼もうします。さあ。」その声を聞いていたおたみは、いや、もうなんにもないうちに魂が引きずりこまれるようになり、女と連れ立って井戸の中へ入っていった。入ったところを見回すと、そこはまるで殿様屋敷みたいに思われるほどが広く大きく、あたりには、米俵に小判に魚が山山々積まれていた。そしてまたあの女の声がしました。「ここにいるのは、みんな私の兄弟でございます。」よく見ると、その人たちは、七福神そっくりでした。大黒様に恵比寿様に毘沙門天様に福禄寿様に寿老人様に布袋様にそれにあの弁天様。みんな笑顔なのに毘沙門天様だけは怒ったような顔に見えた。7人揃って、「ようこそ、おたみ、さあどうぞ。」と喜んで迎えてくれた。弁天様は言った。「おたみ、私たちの所では、今日、お祝いがある日なので、でもこの通り、女は私1人だけで、とても手がまわりかねるのですよ。すまないがお手伝いしてください。」頼まれたおたみは、それが全く当たり前みたいに思い、早速、お酌したり、ご馳走を運んだ。無理に杯でお付き合いもさせられた。おたみの仕事が止まったきりで、おかしいと思っても外へ出てみた岩次郎は、おたみが井戸端で、眠るように倒れているのを見つけた。急いで娘を家の中へ運び、青くなって手当てしました。まもなくおたみは正気にかえった。驚いたことに、おたみが手のひらを開くと、両手に1枚ずつ小判が握られていた。おたみから、話を聞いた岩次郎も妻も、もったいないことだというので、それから毎日1度、お神酒と白米のご飯をあげることにしました。ところが、それから、4、5日したある朝早く、またも井戸の中から、弁天様が出てきて、「おたみ、白米はお供えしなくても良い。お神酒だけ良いのじゃ。お供えした後のお神酒は、決してよその人で飲ませないで、あなたたち三人だけ飲みなさい。約束ですよ。」と言って姿を消した。おたみの話は野際の部落じゅうに広まり、そのうちに、おたみにあやかろうとする者も出たが、どうしたものか、おたみは、その後、他人の前に出ると誰が誰やら見分けがつかなくなり、男の人を見ると、「毘沙門天様、大黒様。」と言って、両手を合わせ、女の人を見ると、「弁天様、弁天様。」と言って拝み、後は一言も口が聞けなくなったという。おたみはその後、1年もたたない秋の十五夜の前日、ぽっくり死んでしまいました。岩次郎は、あれから、一度にお神酒を欠かしたことがなかったし、岩次郎の死後も、この井戸は、おたみ井戸とか、七福神の井戸とよばれ、長く祭られていたという。
おしまい
Re: クリスマス2013 - sisi
2022/07/03 (Sun) 09:57:45
 おはようございます。
おはようございます。
こんなお話がありますよ。
「滝壺に沈んだ刀」 (大阪府箕面市の昔話)
むかしむかし、ある山に。
1人の侍が箕面の滝へ見物にやってきました。「おー、こりゃ、見事な滝や。帰り道からええ機会でよかった。滝の水も冷たいな。気持ちいいな、水浴びするぞ。」
侍は刀を置いて、思い切って水浴びをしました。
すると、置いてた刀はいきなり、猿が盗んだ。
「おーい、猿よ、それはわしの大事な刀や、返してくれ!返さなければ、滝に沈めるぞ!」
刀を持っていく猿は侍が追いかけてきた。
あの猿の走りはなんて速いこと。
なんと、猿の手が崖の下から滝壺の水面に刀を落としてしまい、見えないほど沈んでしまった。
「わ、わしの刀が」と、侍はショックおこし、仕方なく、ザブン!と、滝壺の水面に潜り込んだ。刀は武士にとっての一番の命である。潜る侍は刀が見つかったと思い、なんと木の枝だった。途中水面から上がった侍は、目の前に不動様がいました。侍はすぐに不動様に向かって拝むと、「不動様、わしの大切な命の刀が、あの滝に落としてしまいました。刀がないと武士はもう終わりです。どうか、わしの刀を出てくるようお願いします。あれ、不動様、汚れてますね、わしがキレイにしましょう。」
侍は雑草を抜いた。不動様の汚れた体に布巾の代わりに雑草でキレイに拭き取ると、最後に不動様の足の裏をしっかり磨くと、不動様がくすぐるほどケラケラ笑った。
「不動様がしゃべった。」と侍はびっくりした。
「お前の話はよく聞いた。いいか、今から17日間、わしのお祈りをするんだ、垂水村の泉に行き、そこには刀が流れていくんや。」
「あ、ありがとうございます。」
侍は早速、17日間の祈りをしてから、不動様の言われたこと信じ、千里山の麓の垂水村に行きました。垂水村の泉に着くと、なんと、侍の刀が見つかった。「あったぞ!わしの大事な刀や!」と、侍は涙を流しながら、武士を続けることが安心できました。
あの今まで流れていた刀は箕面の滝壺の底に吹田の江坂にある垂水神社に通っていた。ほんまに刀が見つかったのも不思議なことだ。
(おしまい)
この画像似顔絵は、タレントの雪平莉左です。
Re: クリスマス2013 - sisi
2022/10/20 (Thu) 16:26:53
「ザオンドの河童」(福島県南会津町の昔話)
ザオンドというのは、南会津の阿賀野川源流の荒海川の中に岩場がある。ザオンドにいるのは河童がいました。
むかし、ザオンドの河童が馬を取ろうとしたところ、馬の方が強くて逆にうまやへ馬の尻尾を引っ張り込んでし まった。
馬の主は、飼葉桶をひっくり返していたそのなかに河童が隠れているところを見つかってしまった。馬の主は河童を捕えると、顔面をぶん殴った。「どうかお願いします。これから決してあなたさまに悪戯をしないから勘弁してください。」と河童は涙を流してあやまる。馬の主から仕方なく許してやると、スパコ (寸白)の薬の処法を伝授して去ったという。当家では近いころまで河童秘伝の家伝薬を出して いた。 (おしまい)
Re: クリスマス2013 - sisi
2022/11/17 (Thu) 06:44:34
おはようございます。
キツツキと雀
滋賀県
大昔、鳥の親が病気で、もうだめだから、子供たちみんな呼んで、ほんで、使いが、そこら中に走った。そしたら雀は、それを聞いてすぐ、着のみ着のままで、「大変だ」と飛んでいった。キツツキは、「早く来いと言われても、私は紅につけたり、お歯黒をつけたり、赤前垂れしたりせんならんし、なかなか行けない。」と言って、美しい化粧してから行ったのでした。鳥の子供たちは、みんなよったけれど、いくら待っても、キツツキは来ず、親は、
「もうあかん、言うことがあるから。」と言うて枕元によせて、
「お前らよく聞いとけ、この親の悪いのに、キツツキの怠け者は、来ない、きたら言っとけ。お前は一日に木の中の虫を3匹とって、1匹は神様に、1匹はご先祖様にあげて、日に1匹より食うな。」スズメには、「なりふり構わず一番先に来てくれてすまない。これから先は、ひもじいめはさせていかん、稲穂が出たら、それを食え。冬には人ののきで何でもとって食え。」と言って、親は死んだので、ほんで雀は今でも、何でも食べ物があって、ひもじいめはさせないから、遅れたキツツキは、親の死に親の死に目に会えない。ほんで一日に1匹の虫でおらんならんのやし、木を突いて取らんならんもんに、晩になると、頭やらクチバシがいたんで、「クチバシがいたいよ。」「頭いたや。」
というて、今で泣きます。
おしまい
Re: クリスマス2013 - sisi
2023/06/11 (Sun) 08:54:21
 ご無沙汰していますお元気ですか。タコと猫を話します。
ご無沙汰していますお元気ですか。タコと猫を話します。
むかし、松の木の下に猫がおった。
猫は陸の上にタコが昼寝しているのを見つけた。
猫は、ちょうど、お腹がすいたので、昼寝しているうちのタコの足を1本ずつ食いちぎったが、たまらなくうまかった。二本目もこれまたうまい。三本目、四本目もほっぺた落ちるほどうまい。五本目、六本目、七本目も、「こりゃうまいにゃん」と食べて幸せだ。あっという間に、タコの足が残り一本となり、猫はお腹いっぱいになるが、最後の一本を食いちぎろうとしたが、なんと、タコが目を覚ました。猫は驚いて逃げようとしたがもう遅い、タコの一本足が猫を締め付け捕まってしまい、海の中へ沈んでしもうた。猫はとうとう死んでしもうた。(おしまい)
これは舞台女優、グラビアアイドルの佐藤望美の似顔絵を描き上げた。
Re: クリスマス2013 - sisi
2023/08/06 (Sun) 20:05:30
ご無沙汰しています。
明日は花の日です。8月7日でゴロ合わせです。
夏の花にちなむ昔話です。
朝顔
東京都の昔話
むかし、江戸には弥八郎と言う侍がおり、夫婦の中にはただ一人の娘がいました。その名前は静と言う。静は、朝顔の花が好きでした。14歳の時、しおり戸の側に、朝顔の蕾を見つけて、こんな歌を作った。いかんならん 色に咲くと あくる夜を 松のとぼその 朝顔の花 父は、この歌を短冊に書いて、妻に見せた。「あの小さな胸にどんな色に花が咲くであろうと、次の朝を待つ頃じゃ。」「はい、理に素直に歌われておりまする。」ところが、哀れなことに、娘の静和、この年の冬、風邪をひいて、短い命の花をちらしてしもうた。残された父と母は、毎日、心がうかなかった。
二人は、娘の思い出を語るのが慰めておった。夏も近いし、ある日のこと。
母が、何気なく娘の手箱を開けてみたら、
小さな紙包みが、いくつも入っていました。そして、どの包みにも細いきれいな字で桃色、空色、しぼり、などと、色の名前が書き記されていた。一色ずつ紙に丁寧に包み、朝顔の種である。(ああ、娘はこの種をまいて、色それぞれの美しい花を咲乃どんなにか見たかったであろう)
そう思うと、母は、たまらなく切なかった。
「せめては、この種をまいて、娘を弔いましょう。」母は庭にその種をまいた。日が経つと、つるが伸びて、蕾がついた。風の涼しい、夏の朝でした。あるじの弥八郎を送り出した後、母はふと、庭の朝顔を見た。すると、美しい1輪の花が咲いていました。そして、花の側には娘の静が立っていました。「おお、静。」母は思わず声をかけた。娘はこっちを向いて、うれしそうににっこりすると、そのまますーっと姿が消えてしまいました。夕方、弥八郎はまだ、しぼまずに、朝顔という美しい色の花が咲いてあった。(おしまい)
2013/03/29 (Fri) 09:39:51
2013/03/29 (Fri) 09:54:14
 視点を変えて見上げれば 永久に巣は出来上がりそうにもないところに巣作りしている 頻繁に材料をツガイで運んでいる
視点を変えて見上げれば 永久に巣は出来上がりそうにもないところに巣作りしている 頻繁に材料をツガイで運んでいる
カラスって賢いんやなかった?
ええ加減に諦めてえな 掃除が大変なんやから
Re: 気まぐれカラス - sisi
2013/04/11 (Thu) 18:10:29
 遅れてすいません、ありがとうございます。
遅れてすいません、ありがとうございます。
カラスの動きが素晴らしいですね。
私の仕事場の外で、時々、カラスよく来ますよ。
これは、犬がブルース歌っています、ワンワン。
Re: Re: 気まぐれカラス - sisi
2020/12/07 (Mon) 14:32:13
おもろい昔話です。
五郎びつ
栃木県
むかし、五郎という石屋がいました。
毎日、一本杉(今市市)の岩山で石を切り出してはかまどを作り、それを農家に売って暮らしを立てていました。
また、仕事の合間に大きな石の米びつを作り、秋になって米の収穫時となると米を買って、その中にどっさりと入れておきました。
「五郎やん、なんだって、そんな馬鹿でかい米びつ何か作ったんだ。第一お前さんとこじゃ、そんなに食いきれめえ。」
と尋ねました。あと尋ねますと、「いつ飢饉になるかわからないよー。」というのが五郎の返事でした。
人々はこれを五郎びつと呼ぶようになりました。
さて、ある時、二年ほど続いて、気候不順のため大凶作となり、米はおろか、山の木の実も草も枯れ、このあたりの農村の中には一村みな飢え死にしてしまう悲劇に見舞われる村もあったほどでした。
この時、五郎は自慢の大きな石びつの中にいっぱい蓄えてあった米を全部村の人たちに分け与え、「五郎やんはどうするんだ、てめえの食うのはあんかえ。」と心配そうに聞くのを、
「ああ、おらのことは心配ないよ。」
と言いながら、いつも石を切り出していたいわ山へさっさと上がってしまいました。
それから、いつになっても頃は家へ帰りませんでした。
中に入って、あの石室の米を村人に分け与え行った時のみんなの大喜びした姿をただひとつの思い出に、何も食べないで、神様に豊作を祈りながら、死んでしまいました。
それからの後、雨が降らないで困るときには、この石室に石を投げ込んで五郎の魂に雨を降らせてくれるように祈りますと、必ず雨が降って、枯れてしまいそうな農作物を救ってくれるそうでした。
(おしまい)
「化け燈籠」
栃木県上都賀郡
「やや、御同役油断めさるな。」
「おう、いかにも。」
二人の見まわりの武士はきっとなって、刀のつかに手をかけて身構えしました。一晩中と思っているだけの油を入れたことを確かめて灯をともしても、見まわりの武士が二度目にまわってくるときには、必ず灯が消えています。油ももちろんなくなっているのでした。
どこかわれめでもできていて、染み込んでしまうのじゃないかと言うので、よく調べたのですが、どこもなんともありません。それが証拠に、灯をともしてずっと見守っていると、他の所と同じようにいつまでもと思っています。おかしな所もあるものと、真夜中この燈籠のまわりを歩くのは、みんなあまりいい気持ちはしませんでした。今はその不思議な燈籠の灯がまさに消えようとしているところへ、見まわりの武士が出会った。
眼をこしらえてみると、笠のあたりに大きな狐らしい黒い影がおおいかぶさっています。
「えいっ。」
いかなる魔物も逃しはせぬと、二人の武士はほとんど同時に切りつけましたが、「はしっ。」と火花を散らして、カチーンと跳ね返されてしまい、狐らしい姿はどこにもありませんでした。そして、油はすっかりなくなっています。ところが、それがある時は大きな猿が油をなめているように見えたり、狸やムササビの影が見えたりします。
そのたびごとに、番士たちは切り付けるでは、ただ燈籠を傷つけ、刀を損傷するだけでした。
今も、日光の二荒山神社に、刀傷だらけの化け燈籠として伝えられています。
(おしまい)
ダイダラボウ
(栃木県塩谷郡
むかし、ダイタラボウ大荷物を背負ってやってきましたが、つまずいて転んでしまいました。その時の足跡が芦沼で、投げ出された荷物は羽黒山となりました。
その時、藤づるで荷物を背負ってきたものですが、それが切れて荷物を投げ出してしまったために、羽黒山には藤は入れません。
ダイタラボウの足跡は各処にあります。ある日、茨城の筑波山に腰をかけて、休んでいましたが、その時の足跡が下都賀郡大平町の磯山の近くのあし沼でした。
おしまい
尾張徳川の小牧猿
(愛知県小牧市の昔話)
むかし、尾張藩の藩祖義直公が可愛がっている俺と猿は木間木村がその飼育を託されておった。
その頃、このお猿様が、お城に出かけるときには、大勢の村の衆を供に仕立てて、出かけたもんだ。
ところが、このお猿様、なかなかのいたずらもので、道すがら、通りの店先に飛び込んで何でも欲しいものとってくるんだ。店のものが、「このやろう」と、棒切れで持って追っかけてくる。
今度は、供の衆が、「ひかえろ、ひかえろ、このお猿様は、藩公の愛猿であるぞ。ひかえろ、ひかえろ。」と、叫んでたそうな。そう言われると、店のものもどうすることもできなくて、「へへえ」というわけだ。家と言う訳だった。通りすがりの人にもずいぶんイタズラをしたらしいが,みんなやられ損で、「へへえ」だった。供の衆もずいぶんいい気なもんだ。
ところが、この猿、とうとう寿命で死んでしまった。このお話、ここで終わると思ったら、今度は、藩祖義直公直筆と言われるお猿様の絵が、小牧村に下げ渡された。
小牧村のイタズラ連中は、お猿様の供養と称して、その絵を旗に仕立て、飾り馬を引いて、何の衆をつけて、行列を作って、熱田神宮へ参拝に行くようにした。
その途中、このお猿様の絵に物を言わせて、今度は人間様がずいぶん乱暴したそうな。
こんなお話を聞きながら、私は、戦争中、恩師のタバコに手を触れたと言ういて、満員電車の中から乗客を引きずり下ろし、乗客をぶん殴った軍人さんと無抵抗であった乗客を思い出しました。小池又次郎
(おしまい)
扇でお日様を書いた話富山県
むかしむかし、あるところに、物持ちの大きな旦那さんの家がありました。
五月の頃、村の家々でみんな田植えを始めました。その旦那さんの家でも、たくさんの人を雇い、早苗を植えました。何しろ、大きくて広い田んぼばかりですから、ずいぶん手間取りました。やがてもう少しで終わる頃になり、お日様が虹の小山へ沈み、真っ暗になりました。
すると旦那さんが大きな大きな扇を持ちだしてきて、
「お日様帰れ、お日様帰れ。」と言って、仰ぎました。
不思議なことには、沈みかけていたお日様が、だんだん西の山の端から再び顔を出しましたので、どうにか田植えを済ますことができました。そのあとで、働いていた者たちがみんなで「めでたい、めでたい。」と言って、飲んだり歌ったり、お祝いの酒盛りをしました。その晩は、旦那さんも、働いていた人たちもみんな満足して、ぐっすり眠りました。
ところが明くる朝、起きてみると、またまた不思議なことには、昨日植えたはずの広い田んぼには、早苗が1本も残らず見えなくなっていました。
驚いた人たちは、
「これはきっと、扇でお日様を呼び返したもんやなぁ。お日様が怒らはったが。」
と言っていました。おしまい
閻魔さまと薬売り屋さん
富山上新川郡
富山といえば薬売り屋さんで有名ですが、
むかし、ある薬屋さんがどうした弾みなのか、死んでから地獄へ落ちてしまいました。地獄の門を入ると、たくさんの世界が来ていて、「よぉー、お前もか、お前もか。」と言っていました。
そこへ鬼が来て、大きい鉄棒でみんなを押しやって、釜の中へざらざらとさらいこんでしまいました。ぶくぶくとお湯が湧いてくると、みんな熱い熱いと苦しみながら入れました。すると薬売り屋さんが、釜の湯の中に何か薬を入れてぬるくしてしまいました。鬼はそんなことは少しも知りません。汗を流して焚き続きましたが、釜の中ではみんな平気な顔していて、「ええ湯だ、ええ湯だ、地獄の湯でもええ気持ち。これなら長くいけそう。」と笑いながら言いました。
とうとう鬼は、これでは手に生えないと、閻魔さまに知らせました。閻魔さまがそれを聞いて、カンカンと怒り出しました。
「よし、そんな奴らは針の山へ登れ!」
と言って、針の山へ登り追い上げました。山中の針だらけなので、みんな泣いていましたが、その中に手品師がいました。手品師は早速、薬屋さんどもをみんな背中に乗せて、「こりゃこりゃ。」と言って、針の山を上がったり下がったり遊んでいました。肩に乗った者は、こんな面白い眺めはまたとない。と言いながらはしゃいでいました。
鬼が起こった鉄棒で叩きましたが、今度は薬売り屋さんが、針の山の上から、パラパラと粉薬を撒き散らしました。それが鬼の目には一定音音と鳴き始めました。
閻魔さまはそれを見て、「みんな、これはどうなってるんだ! あいつは何者だ! この地獄の場所には居てはいかん!人間のいる場所へ戻るしかない!」と、ますますカンカンに怒った。
こうして、薬屋さんのおかげでみんなはぞろぞろと娑婆へ帰ってきました。
この薬売り屋さん、どんな薬を使っても大丈夫。
(おしまい)
もるどを恐れた虎と狼
富山
むかしむかし、春山に、婆さんが1人で暮らしていました。話し相手もない婆さんなので、鹿や狐どもがよく遊びに行きました。ある夜、虎と狼が1匹で婆さんの家にやってきました。そして、「朝からお腹がすいてる。今夜あの婆さんを食べてやらないか。」
と言いました。虎と狼がそっと家の中を覗くと、婆さんは、ほっとくと仏様へ参るところでした。それで、「婆様、今は仏様に参っているかい。参り終わってから食べてやろうか。」と言って、待っていました。婆さんは、虎と狼の様子がいつもと違っているので、何を考えているのかちゃんとわかりました。それで、どれだけでもお参りしていました。虎と狼は気がせいてなりません。
やがて婆さんのお参りが終わりましたが、今度は便所に行きました。虎と狼は、それでは便所から出たら食べてやろうと言って、待っていましたが、まぁさんはそれを知っていて、どれだけでも出てきません。そして、「オラのこた、虎や狼にちゃ少しも恐ろしい話なけれど、もるどにだけおろしてのぉ。」
と独り言のように言いました。モルトと言うのは雨漏りの事ですが、虎も狼もなんのことかわかりません。狼が、「ええ、おい。オラっちゃにちゃ恐ろしいなけれど、もるどにだけ恐ろしいとか。お前、もるどと言う何か知ってるか。」と言いますと、虎は、「そんなも知らない。そっやれど、オラっちゃここにいて、しまいにモールドに壊れたらどうするのか。「と言いました。その時、虎と狼が話している頭の上で、婆さんの持ち物でもとってやろうと思って、泥棒が覗いていました。あまり覗くのに夢中になりましたので、足を滑らせて屋根から落ちました。どこかに捕まろうと思って慌てて手を出したら、ちょうど狼のしっぽがありましたので、それにしっかりつかまりました。尻尾を掴まれた狼は、これがモルドかと思って、何にも見ずに逃げ出しました。狼が逃げだしたのは、虎も、さてはモールドが出たに違いないと、後に続きました。泥棒も、捕まったものが走り出したので、びっくりして逃げてしまいました。おしまい
お化けにあった富久造さん
愛知幡豆郡
むかし、西幡豆の富久造さんは、安泰寺の山でお化けにあっていた。
それは、ワシのおじいさんのおじいさんの頃で、200年も昔のことになるだがー。
富久造さんは漁師でした。母親が山を越えて桑畑の出だったで、桑畑の祭りの時は、家中で呼ばれてた。その年の夏祭りも、いつもの年のようにみんなして出かけておった。ところで、祭りっていうのはどこだって同じだと思うが、親戚の者たちが集まって、夜になると酒を飲んで騒いだもんでした。そんなことだって、富久造さんもしこたまをご馳走になった。
ところが富久造さん、明くる日はどうでも漁に出れなかった。それで、「まぁ遅いから、今夜泊まって、明日は行ったほうがいいよ。」ってみんなが止めたが、「何、帰って夜道の方が涼しくなるからええよ。」って、もらったうどんや寿司をしょこなって、夜道を1人でトコトコ帰ってきた。
三河の海から吹いてくるよかっでは、ほろ酔い気げんの富久造さんには、えろう気色が良かった。村ではのど自慢で知られた富久造さんだ。いい気分で盆歌を歌って歩いた。
ちょうど、東幡豆と西幡豆の境の安泰寺の山にさしかかった時だ。
1町ほど先のことが、急にぼーっと薄明るくなり、「おや?」と思って立ち止まった。
「なんだ?」
飯店の袖で目をこすって、その明かりを見つめた。すると、その明かりの中に、何やらゆらゆらと見える。
「はてな?」
もうちょっと近づかんとよう見えないと、2、3歩近づいた。今まで気色よかった海からの風が、変に生暖かくなってきた。と、そのゆらゆらするものが、ふあっと広がった。目の前が真っ白になってしもうた。
「うへぇー!」
富久造さん、声も出せんと、尻餅ついてしまった。すると、真っ白いものが、今度は、ゆらゆらゆらゆらと揺れながら、少しずつ小さく固まっていく。富久造さん、もう行とる心もちもせなんだ。
「なんまいだー、なんまいだー。」って心の中で念仏を唱えながら、それでも怖いもの見たさで、片目を開いてこわごわ見とった。やがて、小さく固まった白いものは、人間ぐらいの大きさでした。「げー!」
なんと、それは白い衣を着たお坊さんでした。富久造さん、何とか救われる気がしました。
「お坊さんにびっくりするなんて、ワシは酔ってしまったのか。」
照れ隠しに、そう独り言を言って断った。と、その途端、またそのお坊さんがゆらゆらと動き出した。「あれ。」と思ってるうちに、ぷくぷくぷくぷく膨れ上がり、一丈もあろうかっていう、どえらい大入道に変わってしまった。これには富久造さん肝を潰した。「うわー!」と、どえらい叫びを上げ、しょこなっとったうどんも寿司もほっかり出いて、山道を転げるようにして安泰寺の門の中に逃げ込んだ。「助けて!」その声にびっくりした安泰寺の坊さんが、提灯を下げて出てみると、駒止めの松の、根っこに、目を向いた富久道さんが、「お化けだ!お化けだ!」って、ひっくり返った。まぁ、後で村の者たちが、「桑畑の在所でもらった寿司の中に、油揚げ寿司でもへっとった。それはほしがった狐の悪さではねえのか。」
って言うのだが、富久造さんは、「ありゃ、狐や狸の仕業じゃねぇ。どうでもありゃ、安泰寺の山に住んでる化け物に違いないだ。」って、ちっともゆずらなんだってことだ。
まあ、何やらわからないが、そんなこともあったかもしれないだろう。ところで、安泰寺が出たで、安泰寺のことも聞かせよう。こんな話があるんだ。
むかし、家康様が、馬に乗ってこの山に登らせた。何の用で登らせたかそれは知らないが、その時は馬をつないだのが馬とめの松だなぁ。
さて、帰る時、「気分よく休むことができた。お礼に、お前の望むものをやろう。なんなりと申すがいい。」って、安泰寺のお坊さんに言いなすった。すると安泰寺の坊さんはちいと考えたが、
「それでは、藁の1束をいただきたいと思います。」
って言うだ。さぁ、これには家康様も呆れてしまいなすった。
「あははははは、藁を1束だと、これは欲のないこと。」って望み通り藁の1束を与えました。ところが安泰寺の坊さん、早速その藁をほぐすと、一本一本を地面に並べて,「この藁の並ぶだけの寺領を頂きとうございます。」
って言った。
藁を一本一本並び,とてつもない広さになる。だけど、将軍様だ。
いっぺん言ったことだ。
「これは一本やられた。」って、安泰寺の言うように、藁1束分の寺領をやりなすった。
それが広い安泰寺の山でした。
(おしまい)
Re: Re: Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/01/03 (Sun) 10:24:36
大阪の真田山の昔話があります。
私も大阪の真田山に何回も行ったことあります、でも過去といっても10年以上前までの事でした。
「真田山の狐」
(大阪府)
むかし、京都の近くの伏見に、徳地屋という穀物の問屋がありました。
ある日の朝、小僧さんの一人店先を掃除すると、大阪から淀川をのぼってきた舟から降りてきたばかりの、50歳くらいの女の人がやってきていました。「私は、これから京都へいくものですが、すみませんが、これを少しの間だけでも預かってくれませんか。ちょっと現場へ行きたいのですが、よろしいですか。」
そう言って大きな風呂敷包の中から、大事そうに藁の包みを取り出しました。「はい、お預かりしておきます。」小僧さんは笑の包みを受け取り、お店の片隅に置きました。ところが、いくらたっても、女の人は現れませんでした。お店の者たちが集まり、どうしたことか話し合い、主人が奥から出てきました。「まったく、しょうのないやつやな、知らん人のものを預かるとは、かるはずみなことや。ぐずぐずしていないで、みんなでその辺を探してみろ。」と、小僧さん達に言いましたが、とうとう、女の人を見つけることはできない。「藁の包みといっても、中に大切なものが入っているか、わからない。人様のものを見るわけにもいかない。家で預かったのだから、取りに来るまで、大事に置いておくのや。」主人はそう言って、勝手の土間のすみに、藁の包みを置きました。そして犬や猫がいたずらしないように、大きな桶をかぶせておきました。その夜10時ごろ。家の外にある厠へ行った手伝いの娘が、ふと、土間のすみに目をやって、ブルブルと震え上がりました。桶が、そろそろ動いているのでした、「あれ、桶が、歩き出した。」
娘はのけぞりながら、大声をあげた。
すると歩き出したオケは止まって、ふわりと宙に浮き上がった。娘の声を聞きつけたものたちが飛んできた時、浮き上がった桶のいたから、小坊主が顔を出した。小坊主は、藁の包みの中から出てきた。そして、七尺ほどの大入道になり、ニヤニヤ笑いながら、家の者たちを、茶碗ほどもある大きな目玉でにらんだ。
「きゃー、怖い!」
みんなが驚きながら引き下がると、店主人が小さい刀を手にして、大入道の前に飛び出ました。「この化け物。何の恨みがあって、我が家に来たのか、とっとと帰れや!さもないと切るで~!」
主人は脇差を振り上げて、大入道ににらみつけた。大入道は少しのひるみません。ナメクジのように、ニヤニヤを笑いながら、「ワイは、大阪の真田山に長年住んでいる狐や。この家のものが、3日前、我の住む巣穴を小便して怪我した。その仕返しに今朝ここへ来た。我の巣穴を怪我したものを出さねば、家中のものに仇をするぞ!」というのでした。
3日前に大阪へ出掛けたものといえば、
太次兵衛だ。店主人は早速、太次兵衛を呼んで、たずねた。
太次兵衛は、青い顔して、震えながら、
「まことに、おおせのとおり。大阪へ出た折、真田山のおかげで、何気なく小便をしました。そこに狐の巣穴があったとは、知りませんでした。どうか勘弁してくれ。」
と、深く頭を下げ、大入道に謝りました。「その通りや。知らんとは言え、悪いことをしたのは、確かや。謝っておるのだから、許してくれ。」
店主人が言うと、大入道は、「それなら、命を助けてやろう。そのかわり、我の住む巣穴に3日間、赤飯と油揚げを備えよう。」と言うのでした。「わかった、それやったらしましょう。」店主人が言うと、
「もし、途中で約束破ったら、その時、みんなの命はないと思えや。」とそう言って、大入道は足元の藁の包みと一緒に、煙のように消えていきました。徳地屋では、次の日の朝から3日間、 太次兵衛に赤飯と油揚げを持たせて舟に乗せ、大阪の真田山へ届けさせました。朝ばかりではない、夕方にも同じものを持たせて、真田山の狐の巣穴に備えました。3日間、徳地屋の主人は充分に礼を尽くして、そのためかどうか、徳地屋にも、太次兵衛の身の上にも、その後、何も起こらなかったのでした。
(おしまい)
Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/01/03 (Sun) 11:02:18
私は昨日、生駒へ軽く温泉行きました。
暖かく感じました。
温泉にふさわしい昔話ありました。
「なんでも溶かす食器」
(秋田県)
むかし、十和田湖の近くの山奥に、岳の湯小屋と言う、古い湯治場がありました。
ある夏、この小屋に、麓の村から泊まりがけにやってきた男がいました。夕食を終えて、あと片付けをしようとすると、食器の上に自分で作った食べ物が、まだ少し残っておりました。出てしまうのは、もったいないことだ。男は明日の朝、また食べることにして、小屋の炊事場の隅に置いてあった。古びたな食器をきれいに洗うと、その中に食べ物を移して棚の上に置きました。
するとまもなく、1匹小さいの蛇が炊事場の土間に入ってきた。
湯治にきた男は、奥の部屋で横になりながら、退屈紛れに蛇の動きを見ていました。笑は、鎌首を持ち上げながら、しばらくの間のあちこちを這いずり回っていました。そのうちに、棚の上に置いた、おかずの匂いでも鍵つけたのでしょうか。早く指をアンダー上を伝わって店に上り、おかずの入った食器の中に、頭を入れました。「おい、何するんだ。それを私の食べ物だ。「男は起き上がって、蛇を追い払おうとしましたが、蛇は突然、棚の上から土間へずり落ちて行きました。男は、ニヤリと笑い、お腹を吐かせた蛇が、慌てて重心を失い落ちたのかと思い、ところが、とんでもない。土間に落ちてうご向いている蛇には、なんと頭がないのでした。男はびっくりして棚の上に置いた食器を覗き込みました。
そこでまた、男は血の気が引くほど驚いて、立ちすくんでしまいました。食器の中には、何もありません。あると思った蛇の頭ばかりか、さっき入れたおかずの残りもきれいに消えています。食器の中には、わずかな水が溜まっているばかりでした。
食器に入れたものは、そこに描かれた青い渦巻きに巻き込まれて、みんなが解けて、水になってしまいましたというのでしょうか。湯治にきた男は、ガタガタ震えだした。
食器の中に描かれた青い渦巻きを見つめていると、自分も吸い込まれていくような気がします。男は不気味の悪い古ぼけた食器を、頭のない蛇が死んでいると前叩きつけると、一目散に山奥の湯治場から逃げ出した。
(おしまい)
Re: Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/01/03 (Sun) 18:22:34
「農牛と農鳥」
(山梨県北巨摩郡の昔話)
むかし、茅が岳の村々は昔から水飢饉に苦しんでいました。
毎年夏が来ると 、日照りが続いて田んぼも畑も枯れそうになるので、村の人たちは鳳凰山に雨乞いにのぼりました。
山の神様はこれを哀れんで、黒毛の農牛と、白斑(しらふ)の農鳥を呼んでいいつけました。
「お前たちはこれから入って池を掘ってこい。」
そこで、農牛と農鳥は夜なってから穂坂村の地内に行って池を掘り始めた。
「夜明けなったらお前が鳴けよ。それを合図に山へ帰ろう。」
そういう約束をして、二人は毎晩一生懸命に池を堀り、夜が明ける頃、農鳥が鳴くとそれを合図に二人早く引き上げて山に帰った。
こうして、2つの池は、だいぶできたが、ある晩二人はあまり熱心に働いていたため、夜明け頃になっても、農鳥が時を知らせるのを忘れていました。気がついたときもうすっかり明るくなっていて農業は山へ帰ることができません。
そのまま池の傍に石と化して、今も牛が寝た形の石が残っており村人は牛石と呼んでいます。 農鳥だけは急いで西山へ飛び帰りましたがこれで池を掘ることはどっちも中止となりました。今も牛池と鳥の小池は残っておりますが、この二つの池は、どんな日照りの年でも少しも水が減ることはありません。
また、この鳥が飛び帰った山は農鳥岳と呼ばれて、白根山のうちにそびえています。
毎年農業初めの頃になると、この山の雪が白鳥が首を伸ばした形に消え残り、次に牛の形が現れます。
春になると、鳥の形が山に現れると、百姓たちは、「早く農鳥を見えたで、苗の間を作らねば。」と言って、苗代に籾種をおろし、農牛の形が見えると畑に大豆や小豆をまきつけます。
また、農牛 の形は秋にも、現れることがあって、秋の農業が見えると秋農の麦まきがはじまり、この山の見える村人たちは言っています。
なお、この山の残りの雪は鍬などの農具の形に見えることもあるということでした。
(おしまい)と、こんな丑年にふさわしい昔話がありますよ。
Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/03/30 (Tue) 18:53:53
こんな面白い昔話もあります。
鶯の谷渡り
愛知県
昔の昭和15年4月から7月の頃、「鶯の谷渡り」っていびりがあります。兵舎には細いペットがたくさん並んであります。そして、ベッドの下をくぐります。ベッドとベッドの間に顔を出して、ホーホケキョーと鳴いて、また潜っては、次の間から顔を出しては、ホーホケキョーと、こういうやり方をやっています。はじまで行くとまた戻ってくる。そうすると、「今日の鶯、声が悪いな。」なんて古兵が言います。いいと言われるまでやります。
おしまい
Re: Re: Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/04/02 (Fri) 18:32:16
こんな動物の面白い話もあります。
きつねとたぬきの化かしっこ
愛知県
昔、きつねとたぬきが、「いやー、今日は、化け合いをしようじゃないか。」と言うことで、狐が、「それじゃあ、俺が、先に化けるんだ。」と言って、きれいな嫁さんになって、キラキラと光りながら出てきた。
そしたら、たぬきがいうことに、「やあ、ダメだ、ダメだ。しっぽが見えてるぞ。」と言った。それから、今度は、たぬきが、「今度は俺の番だぞ。」って、ほういって、戸だなん中へ入っていった。まぁ、いくら待っても、待っても、出てこないようだ。「やいやい、まんだかまんだか。」と言ったが、黙ってちょっとでも出て来ません。まぁ、あんまり待ちかねたものなので、戸を、かーいっと開けたらおりません。「どこへ行ったが。」と言ったが、さっぱりしません。ほったら、一つ高いたなに、ぼたもちが、お皿にいっぱい盛り上がっております。「いや、こりゃあ、いいもの見つけた。ひとつ、野郎、おらんうちに、食べてやれ。」ちょっと取って、食べようとしたら、「よせよせ、よせよ。俺だに、よせよう。」と言うことで、たぬきの方が、化けるのに上手だったと言う。
そんな化け合いお話なのでおしまい。
おしまい
干支頭 徳島県海部郡
むかし、猫が悪いのはね、元旦に早くいったものが、干支頭になる言うてね、いったんですわ。猫が行き寄ったらね、可愛らしいもんがちょこちょこと出てきてね、「背中に乗せて連れてってくれ。「それから連れてって、閻魔さんの前へ行って、ぽーいとネズミが飛び降りたんですわ。そんでね、干支頭に、「ねー。」と書いてね、ネズミが干支頭になってね。ほいて怒ってね、猫が食うてしもうたんですわ。閻魔さんが怒ってね、「そういう残酷なことをするもんは、干支頭の中には入れてやらん。」と言うてね、はやけんども干支頭には、ネズミがついた、言う話も聞いたですわ。それも、まぁ、年寄りの話でした。
干支頭というのは、十二支の最初に来る動物のことである。
おしまい
Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/12/31 (Fri) 14:36:40
今日は2021年最後の日となります。あと半日で2022年の幕が開きますね。
タイの芽 鳥取県
むかしむかし。
ある山里に、じいさんとばあさんの家に、1人の馬鹿息子がいました。ある時、息子は町へ魚を買いに行くと、魚屋さんの店先には、大きなタイが並べてありました。そこで息子は、早速、「魚屋さん、この魚、見事なものやな。一体どうやって食べたら1番おいしいかな。」魚屋さんは、それを聞くと、「タイは何といっても、作り身に限る。作って食うのが、一番良い。」息子はそこで、タイを買って帰ってきたが、「さあ、おいしい魚、買うてきた。作って食わせてやるからな。」と、早速、タイを下げて、くわを担ぐと、山の畑行って作っておきました。明くる朝になると、早く山へ行ってみたが、タイはまだ腐っておりません。その明くる日も、またその明くる日も、何ともなっていませんでした。ようやく4日に見ますと、タイは腐って、目だけが残った。これを見ると、馬鹿息子は、「ほーれ、目が出たぞ。」と、大喜びをしました。これを聞いたじいさんは、呆れ返って、「この大馬鹿者め!作って食えっていうのは、骨と身を離して、身だけ食えって言うことなんじゃ。」と言って、大笑いをしたそうな。
(おしまい)
Re: 気まぐれカラス - sisi
2021/12/31 (Fri) 16:09:50
ミズケエ鳥のいわれ
宮崎県
むかしむかし、親孝行しない、ずーそ息子がおった。年取ったお母さんは、そんげな息子のことを心配するあまり寝込んでしもうた。お母さんは、「水が飲みたい、飲みたい、水を飲ませてくれ。」と言うて、頼まれた。だけど、そのずーそ息子は、そのたんび、薪の燃えさしのおき火を、火箸で挟んだ、お母さんのもとに突きさすじゃ。そんげ酷(なげ)ぇことばかりして、死ぬまで水飲ませた。
お母さんは、ミズケエ鳥(水恋鳥、赤ショウビンの別称)に生まれ変わった。ミズケエ鳥を見てみない、くちばしが赤くなったか、。だけど、水は飲もうとすれば、くちばしの赤いとこが、水じゃうつって、それが火のごと見え、水が飲めなかった。だけど、ミズケエ鳥が水を飲むことができるとは、五月ながし(梅雨のこと)の、大きな雨で、木の胴腹を水が流れる時だけでした。毎日、水が飲みたい、水が恋しいという思う鳥でした。ミズケエ鳥の話だ。 おしまい
猪狩り犬をかわいがった猟師の話
宮崎県
むかし、猪狩り名人が、オブチとコブチという、良い猪狩り犬を引いて、猪狩りにいきました。その日は日々と違うって、猪が取れた、暗くなっても、猪狩りは深く追ぇしたものか、イノシシの通り道をはぐれたもんか、きたのでした。猪狩り名人は、「オブチ、コブチよ、来い。」と言って、めいめいの犬の名前を叫びました、一生懸命になり、めいめいの脚絆の片ぽうが外れて、なくなるのもわからない、猟場を捜しまわった。それで、とうとう猟師は死んじゃいました。毎年、お盆の頃になると、山の八合目より上で、この猟師の亡き魂が鳥にのりうつって、オブチ、コブチコーンと言うて叫んだ。その鳥を見た母の話でした、脚の片方に脚絆がなくなったこと、毛がなくなった。今では、山の木にも少なくなって、この叫び声を聞くことを少ないが、あれは仏法僧という鳥でした。これが叫ぶと、はやり病や死人が出ると言って、嫌うところもありました。
おしまい
Re: 気まぐれカラス - sisi
2022/03/02 (Wed) 23:49:09
この時期、桃の節句です。
「雛の夜ばやし」 (静岡県の昔話)
むかし、天城山の北の麓に、大きな家があった。
この家の門の中へ、ゲガをしていた一人の老人が苦しそうに倒れた。
家のばあさんが気づくと、老人を助けおこして、話を聞いた。
老人は、「助けてください、私は旅のものじゃ。」
ばあさんは、召使いにてつだわせて、わらじを脱がせて、傷の手当をした。どうやら、矢に当たった深い傷のようでした。
しばらくの前の頃、修善寺から離れ、戦いがあった噂があり、もしかして、落人かと思ったばあさんは、何も聞かずに,こっそりと、人に知れないように、家の蔵の中のひと間に老人を寝かせてやりました。老人は安心してすっかり、気が緩み、熱を出し、幾日も幾日も苦しみ続けました。
ばあさんは、老人の看病を繰り返しすると、熱がだんだんとすっかり良くなりました。
ある日、ばあさんが、蔵座敷に入ってみると、老人は、ゴザの上に座り、何か木を彫りました。 「あらら、すっかり元気になったね。 何をしてるんですか。」
すると、老人は、「わしは見知らぬまま、長い間お世話になったから、何かお礼したいけど、元々は鎌倉の彫り師をやったから、雛でも彫ろうと思いまして。」
「そうでしたか、それはありがたい気持ちで、もうすぐ春の節句ですね。」
やがて、美しい雛たちが出来上がり、まるで生きてるような人形でした。
「この雛たちは、わしのゆかりの者たちに,よく似てきてしもたが、春ごとに、どうぞ飾ってください。」と、老人は言い残し、ある晩、旅人である老人は、天城を越えて、行き去りました。
桃が咲いて、蔵座敷から出した雛たちを飾りました。
老人が作り残した雛たちは、見るほど美しかったので、ばあさんは、感動した。
ある年の春、ばあさんは、桃の節句を供え、麹をねかせて、甘酒を作った。甘酒は甘いから、鼻がツンとくるいい匂いだ。
ばあさんは、そろそろ、雛を出そうと思い、急に熱を出しました。熱はなかなか、下がらず、とうとう、雛の日が来ても、具合が悪く、起きられませんでした。
雛の入れた箱は、一年間ほこりかぶったままだ。蔵の板敷きの隅に置かれていました。
その晩の夜中、蔵座敷でうつらうつらと、眠っていたばあさんは、何かゴソゴソと動く気配に目を覚ました。
ふすまを隔てた隣部屋から、誰かヒソヒソと声が聞こえる。
「今日は桃の節句じゃ。」「はい。」「ばあさんは雛を忘れたかも。」「忘れたはずかなー。」「一年の間、押し込められるのは辛い。」「今年は、日のめは、終わりかも。」
すると、しくしく泣いている女の声が聞こえた。別の声が言いました。「 姫が泣いてる。」「殿も寂しくなったな。」「雛の夜というのに、はてさて、箱の中とは、窮屈だが、ひとつなぐさみに、夜ばやしでもやりますか。」「それがいい、今年は甘酒のいい匂いがするからな。」ガヤガヤ騒ぐ音がしばらく聞こえた。やがて、しょうの響きと、鼓の音、ひちりきのはやしにつれて、その調べは、ばあさんがいつも琴で弾く音とわかりました。ばあさんはしばらくの間うっとりと聴き惚れていましたがやがて起き上がってそばにあったことを引き寄せておはやしの響きに合わせて弾き始めました。「 琴が聞こえる。」「良い調べじゃ。」「窮屈な箱め。」
という声がして、箱のやぶれる音がした。弓をならし、銚子をとる音もする。
ばあさんは,琴を弾いても夢中になり、やがて、疲れてしまい、琴の上にうつ伏せて眠っていました。
朝になり、召使いは、ばあさんの具合を見にいくと、夕べ、ネズミが箱をやぶいて荒らしたと思って、驚いた。
「ばあさまは、体調は良いみたいで、夕べはおはやしの音がすると思ったが、もしかして、琴を弾いたのか。」
ばあさんは起きて、召使いに、「今日は、雛を出すから、手伝ってな。」
「雛祭りはもう終わりました。」
「でも、年に一度は、雛を出してやらんと、雛が泣きよりますよ。」ばあさんはそう言って、みんなに手伝わせて、壊れた雛の箱を母屋に運び、桃の花に甘酒を供えて飾りました。それからというもの、この家では春になると早々と雛を飾ることを忘れませんでした。「もし,雛を飾らないと,雛が泣いてしまう。その年は,ろくなことが起きるよ。 」と言い伝えられました。 今もこのあたりでは、雛祭りに雛を出してやらないと、雛が泣くという伝えでした。 (おしまい)
Re: 気まぐれカラス - sisi
2022/06/12 (Sun) 08:24:05
庄五郎と狸 滋賀県
むかしむかし、田植えが終わると,田の水の入り具合の見回り役の人がいた。その名は庄五郎でした。
田植えもすっかり終わり、まだ間もないときやったそうな。かんかん照りの暑い日のこと。
庄五郎が、田の水を見て回り、川筋を、ぶらぶら上がって来ると、墓地のとこの一本松の下に狸が昼寝した。
暑い日で、なんとなく気がむしゃくしゃした庄五郎は、昼寝中の狸を見ると、少しイタズラして、脅かそうと思った。まわりを見回すと,ちょうど、そばに、薪木が積んだので、そのわり木を一本抜いて、ポイと狸の方へ掘らはった。そしたら、上手に狸のお尻に、割り木が、ポンと当たった。いい気持ちで寝ていた狸は、びっくりして、ぴょんと飛び上がり、目をキョロキョロさして、庄五郎をジロジロとにらみ、3枚の奥の森の方へ、逃げて行ったそうな。「狸のやつ、びっくりしたわい。はははは。」庄五郎は、それっきり別に気にもしないで、鼻歌を歌いながら、家に戻った。
晩飯を食べて、寝ると,なんやら表が騒がしくなってきたので、庄五郎は目を覚まして、戸の隙間から外を覗いてみた。月夜で明るく、外の様子がよく見えた。村はずれの方から、大勢の狸が、ぽんぽこぽんぽこぽこぽんと、腹づつみを打って、やってきた。「こりゃ、こりゃ、どうしたことだ。」じっと見ると、庄五郎の家の方へやって来て,家の前で、狸が、歌を歌いながら、腹づつみを打って、踊りだした。
割り木尻あて庄五郎。
一反(約10アール)引き上げた心の良さは、何とも言えない。なおも不服なら、もう一反と引き上げようか。庄五郎は、びっくりした。
さては今日,割り木をあてた狸が、仕返しをしにきた。けれど仕方ない、夜のことと思って、あんまり気にせず、また、そのまま寝てしまいました。
夜が明けて、早速田んぼを見に行ったら庄五郎の田んぼの稲が、全部抜かれてしまいました。
(おしまい)
子猫と子ネズミ - sisi
2023/10/14 (Sat) 06:20:44
むかし、じいさんが畑仕事の帰り道に可哀想な子猫を拾った。
じいさんとばあさんは子猫を自分の子供のように可愛がって暮らした。
ところが納屋の穴から小判の音がなった。納屋でぐっすり眠っている子猫のそばに子ネズミが袋からそっと豆一つ取り納の穴へ帰ろうとすると、子猫が子ネズミの尻尾を手で止めた。子ネズミが子猫にわけを話すと、母が重い病で豆を栄養取らないといけない。とこねずみは泣きながら言った。子猫はこねずみの尻尾を放して、病の母に豆をあげて元気に戻った。納屋での次の日、豆のお礼にネズミたちが小判を運んだ。子猫が小判一枚ずつくわえて老夫婦に見せた。老夫婦は小判をみて驚き、末長く暮らしたそうな。
おしまい
Re: 気まぐれカラス - sisi
2023/12/13 (Wed) 00:31:36
来年は辰年です。
龍の淵 宮崎県日向市
むかし、日向の米良の山奥に、漆かきの兄弟がおった。
兄は違う山奥へ漆かきに行く時、大事な鎌が岩にぶつかり、淵の水の中へ落ちてしまった。「しまった!」と、あわてて兄は淵の水の中へ潜って泳ぎ、そこにある窯を見つけた時、何やら不思議な穴があった。それはべとべとした漆の汁でした。「これは神様が山に雨が降ってきて淵に漆の汁がこぼれた違いない。」と兄が竹筒に漆汁を入れて弟には秘密として独り占めで持って上がり、小判がザクザク帰りました。家に帰り、小判もちの兄を見てびっくりした弟は「兄ちゃん、その小判どうしたのだ」「悪かったな、最後の一本の漆の汁の木だから、もう、他の木はないから、諦めるしかない、また来年生えるしかない」と兄が弟に嘘ついて言った。それでも、弟はおかしいと思い、納得できず、翌朝早く兄が一人で外出る時、弟は隠れながら、兄に見つからず、そっとついて行った。兄が淵に潜ったことを弟は見てしまった。弟が夜、兄が寝ているうちに淵の中に潜った。潜ると、淵底の漆汁を取って上がり、小判ザクザクで家に帰り、兄に見つからず、そのまま寝てしまった。また翌朝早く、まだ寝ている弟が小判を持ったままを見つかり、とうとう怒った。兄は、また弟が淵に入るかもしれないため、仕返しで、弟が寝ているうちに恐ろしい龍を木で彫り、淵の水へ沈めて、弟を怖がって、取らないため見守りながら置いた。また、弟は淵に入り、漆汁を取ろうとしたが、龍の木彫りを見て怖がって、逃げ帰った。兄は漆汁は自分のものとして成功して、一生幸せできた。ところが、兄はまたまた淵へいつもの漆汁を取ろうとしたが、龍の希望が、まさか目を光らせ、彫り物から動いて、逆に兄を襲ってきた。「こ、こっちからくる!助けて!」と叫び怖がって、逃げ帰ってしまいました。(おしまい)
Re: 気まぐれカラス - sisi
2023/12/30 (Sat) 09:17:19
 「おいせまいりわんころう」
「おいせまいりわんころう」
(大阪府大阪市の昔話)
むかしむかし、えどじだい、まだ おとこが
ちょんまげを ゆうていたころ、だいみょうも びんぼうにんも、おとこも おんなもこどもや いぬまでみ~んなでかけたといういっせいちだいのたび「おいせまいり」がだいりゅうこう。
ふりだし、ここは おおさか せんばの こめどんや。すごろくや、ちゅうて けっこう はんじょうしてまんねん。
わいのなまえは わんころう。
なんぞ おもろいこと おまへんか。
このごろ こいちゃんが ちいとも あそんでくれまへんねん。「わんころう わんころう こっちおいで」
あ、こいちゃんが よんだはる。おやつのたまごやきかな。
だんさん、こいちゃんがよしよししながら ゆうた。
「わんころう、おとうはんがこめだわら かついだまんましりもちついてしもてね、
それから はんつきもふせったまんま。
おいしゃのせんせにみてもろたけど、いっこも ようなりはらへん。おいせさんにかみだのみしたら ええって、おみせのもんが いうのやけど、わたしは かんびょうがあるさかい、おまえ、かわりに いてきてくれへん?」
もちろん いきまっせ。こいちゃんのたのみや。
たびのしたく、おいせさんの ひしゃくをくびにつけてもろてあとは おいせまいりのひとにくっついていったら ええのやて。ほな、いてさんじます。
たまつくり、こっから おいせまいりの しゅっぱつや。 たまつくりはすごいひと、 おみせも ぎょうさん でてるがな。
くらがりとうげ、えらいくらいとこ でてきたな。だんだんみちも けわしなってきて、 こころぼそうになってきた。
おひいさんも にしのそらに かたむいてしもて、にくきゅうもパンパンや。
ああ〜、おなかすいたなぁ~ くうわ~ん。
あ、むこうに あかりがみえる。
ふるいちのやど、ワンワン、こんばんは こんばんは。
「あーら、かわいい わんこさん、おいせまいりのひしゃくをつけたはる。 どうぞおあがり、 あったかい だんごじるも できてますえ」 おなかもふくれて ええあんばい。 ほな、おやすみなさい。
いせかいどう、つぎのあさ、やどのおねえさんが おべんとうをもたせてくれた。「あんさんも おいせまいりでっか。 ほな、いっしょに いきまひょか」 たびのひとが さそうてくれる。そうやって、つぎのひも またつぎのひも わいは どんどんあるいた。
つらいときは こいちゃんのかおを おもいうかべながら。
しちどぎつねのもり、わんころうのおしっこが、しちどぎつねのあたまにかかる。ここは、やられたら、しちへんだましてかえすという しちどぎつねのおるもりや。
ふるやどで、つちとわらじのぞうすい。きゅうにひがくれ、こえだめおちる。にげてもがいこつがおってくる。あわててとびだし、うわばみにぶつかる。やさしいねえさんのひざまくらがぐるぐるろくろくび。じぞうのくびがとび、みみにかまれる。おおにゅうどうのとうせんぼがしっぽかまれる。
くしだがわ、おっきい うみや。いや、これかわか。
どうやって わたったら ええのやろう。
と、「だれかたすけてー ぼんが かわにながされた!」
えらいこっちゃ!! わいは むちゅうで とびこんで、ぼんのきものをくわえ、ひっしのパッチでかわぎしまで およぎきったんや。
びぜんや、ぼんのおとつつあまは たいそうよろこんで、ごちそうやおどりで もてなしてくれた。「さぁ、たーんとおたべ」おしゃみのねいろにあわせて、ちとしゃんしゃん ちりとてちん。
いせじんぐう、ワオーン!
とうとう いせじんぐうに とうちゃくや。
わ~ おっきいなー。
てまえのはしを わたれば、ええんやな。
「ちょっとまてい。ここは しんせいなる
かみさまの おられるところ、いぬちくしょうを とおすわけにはいかぬ」
もんばんに とめられた。
そんな せっしょうな。
あまてらす、すると、あたりいちめん きりで かきくもった。
とおもたら、あらわれでたんが………。
「わらわは あまてらすおおみのかみなるぞ。くしだがわにて こどものいのちを
すくった おこないに めんじて、とくべつに さんけいをゆるす。すごろくやのぐあいも よくなるであろうぞよ」
そういうと またきりとともに すがたをけした。ふしぎなことも あるもんや。
こうしてなんとか、おまいりをすることが できたんやけど。
かわさきのみなと、ほな もう、はよ かえろ。
こいちゃんが まってるさかい。
かえりは ふねにのったら ええって、 やどのおきゃくが いうとったな。 「おつ、いせまいりの おいぬさんや、にをおろして ちょうど おおさかへ もどるところ、おまえさんも のんなはれ」せんどうさんが、こえをかけてくれた。
てんぼうさん、そうして、ふねはなつかしい おおさかのみなとについたんや。 クンクン ああ、おおさかのにおい、 すごろくやの こいちゃんの においがする。 こいちゃ〜ん。
すごろくや、「ああ、わんころうや よう ぶじで おかえり」
「わんころう おかえりやす」
「ああ、わんころう ええこや ええこや」
みんながそろって おでむかえや。
「あら、おとうはん いつのまに?」
わんころうの げんきなすがたを みたくって、だんなさんの こしも すくっと たちあがった。
あがり、「わんころう、ありがとう」
こいちゃんに ぎゅっと だきしめられて、 わんころう おもいっきり しっぽをふった。
めでたしめでたし。(おしまい)
カバ - sisi
2013/11/02 (Sat) 10:35:25
Re: カバ - SISI
2020/12/11 (Fri) 14:27:55
こんな話あります。
鬼子
屋久島
屋久島の不思議な話の一つです。
「女一人、山の中に入るな。」といわれます。
もしそうしたら、女は山の中で、しきりに眠くなったり、紅色の異人の夢を見たり、その子を身篭るということです。
生まれた子は、普通とあまり違わず、すくすくと育つけれども、ただ生まれた時から、必ず白い歯が揃い、赤い髪を振り乱して、よく走るといわれます。そんな子を鬼子と言います。
人々は鬼子を生むこと、非常に嫌われて、もし生まれたら、柳の小枝を鬼子の口にくわえさせて、大木の枝に吊しておくことです。そして、一夜が開ければ、不思議なことに必ずその姿は、跡形もなく消えていきます。楠川に鬼子所というところがありますが、そこも昔は鬼子を吊るした場所だそうです。
さてむかし、安房村(あんぽうむら)に鬼子が生まれた。ちょうどその頃、京都の侍が罪を得て、安房村に島流しになっていました。
ところが、性質荒く、それに、心もよくない悪人でしたので、人々から非常に憎まれていた。
屋久島ではむかしから、大悪人があるときは、必ず神の怒りがあって、何か起こる、といわれています。
人々は、「あの悪人侍を見れ。何かが起こるぞ。」
と、噂し合いました。ところがある日、ガジュマルの大木の下を通っていたその侍を見て鬼子が叫びました。
「山の神様、あのガジュマルの木で、悪人を殺してたもれ。」
すると、ガジュマルの大木が突然、バリバリバリーと音を立てて、道いっぱいに広がって倒れました。そして悪人侍はその下敷きになって死んでしまいました。人々は、あまり突然なので、
「あっ。」
と息をのんで、その有り様を見ていました。そして次の瞬間、ふと気づいたときは、鬼子の姿がかき消えてしまって、どこにもいませんでした。そして、再び現れることはありませんでした。
「これはきっと御岳の神様が鬼子の姿を借りて来やったに違いない。そしてあの悪人をこらしめたのじゃろう。」
人々は噂しました。
おしまい
逆立ち幽霊
嘉手納の民話
昔、成仏できのない女が、化けて出ると言うような逆立ち幽霊の話、聞いたことありますか。恨みを持って出てくると言う逆立ち幽霊。お侍の端で綺麗な人がいたわけ。で、その侍が病気になり、もう死ぬかもしれないと言うふうな状態になったわけですが、そしたら、そのときお侍が、「わしはもうこれで死ぬかもしれない。しかし、お前くらいの美人が、わしが死んだ後、また再び嫁入りするんじゃないかと、私はもうたまらなく心配だ。」と言うふうな意味のことを言ったわけですが、「私は、そういうふうな事はありません。」と。「そんなに心配するんで、それであれば、そういう事は無い証拠あぁとして、私の鼻を削ってあれしましょう。「と鼻を削ってしまったわけ。鼻を削れば美人でなくなる。今度、その旦那は死なないで行ったんだよ。そうしたらもう、鼻のない女たら美人どころじゃないでしょう。今度はそれ、疎ましく思って殺して、そして今度は、これ化けて出るはずだからといい、足に五寸釘を打ち込んで葬式をしたわけ。足に五寸釘を打ち込んだもんだから歩けない、逆立ちして出てくるわけ。逆立ちして出てきて、そして、出てきた所をお侍に見られて、「なんでそういう格好で出てくるのか。」と言われて、実はこうこう、こうこうと。
「あーそうか。」と、「じゃぁ、わしが助けてやるから。」と言って、釘を抜いてあげたら立って歩くようになって、そして、仇を打ったと言う物語でした。
おしまい
イタテカイ
滋賀県
むかしむかし、平方の天神に、人身御供というて、毎年近くの村から、ひとりずつ娘を供えるちゅうならわしがあった。
ある年、平方の近くの村一番の木の強い若者が、
「毎年毎年、綺麗な娘をさらって行きよるやつは、どんなやつやろ。いっぺん見届けたろ。」
ちゅうて、この天神の境内の大きい松の木のかげに隠れておった。
そして、人身御供の娘の乗り物カゴを、村人が天神のお堂の前に置いといて、帰って2、3時間したころや。夜もふけて、乗りもん中の娘の泣き声と、そのとき、突然、天神の後ろのお堂の方の琵琶湖が、なんやらざわざわしてきた。
なんだか知らん、正体のわからない化け物が、湖から上がって来よった。
まわりは暗いし、あたりは生臭あい風が、吹き出しよった。いくら気の強い若者かって、怖いわいな。はやけんど、怖いもん見たさのなんとかや。じっと目をこらしてみたんや。けんど何にも見えない。ただなんとなく化け物の声らしいものだけが聞こえてくる。よう聞いたけど
、「平方のメッキにいうなよ。平方のメッキにいうなよ。」ていうて聞こえた。
化け物は、人身御供の娘を抱えると、湖のほうへ行ってしもうた。
あくる日、若者は、平方の天神へ行ってみた。そして昨夜聞いた。
「平方のメッキてなんやろ。」
て村の中を聞いてまわった。ほれが「メッキ」ちゅうのは、平方の、野瀬の長者の飼っている「メタテカイ」ちゅう犬のこっちゃとわかったんや、それは強い犬で、いかい犬やったそうな。
ほんで、若者は、長者のとこへ行って、ゆんべのことをしゃべったんや。
ほして、
「神様が、人身御供食わはるんやったら、しょうがない。けんど、神様でもあらへん化け物が、人身御供がほしがるとは、もってのほかや『平方のメッキ』いうなとは、メタテカイが怖いちゅうこっちゃ、長者はん、来年はすまんが、犬を隠してください。ワテが退治しますさかい。」
と申し込んだ。
長者も喜んで、犬を貸すちゅう約束したんや。
次の年、また人身御供が上がることになった。若者は、メタテカイを連れて、化け物のあられるのを待ってた。
化け物は、去年と同じように出て来よった。メタテカイは、その化け物に飛びかかって、2時間ちかくも戦った。ほして、両方とも、倒れてしもうた。
その化け物を、よく見ると、大きなカワウソちゅうやったこっちゃ。
そのメタテカイを祀ったのが、天神のはたの石垣の中にある丸い石や。
触ると、歯が痛くても治ってしまうということでした。
ただ丸い石が、ころんと置いたるけんど、こんなお話があるんだ。
(おしまい)
おくらつつみ
山形県村山市
むかし、大倉の里は今の村山市、東の山の麓から、ダラダラと西に広がっておったから、雨が降り続くと、山から水がどっと流れだして大水になるし、日照りになると、すぐかわの水が枯れてしまう。村人たちは、よるとさわると、「雨が振り続いても、大水が出ないようにするには、大きな溜池を作ることだ。」「そうだ、水をためておく、大きなため息があれば、少しくらいの日照りでも、田んぼに水がひける。」と、話しておった。だが、大倉の里は、東から南にかけ、ぐるっと山が続いており、西のほうは、ダラダラと、低くなっているから、山から水を引いても、すぐ西に流れて流れこんでしまう。ため息を作るといっても、難しいことだ。かといって、いくら話あってばかりいても、どうにもならない。村人たちは、思い切って、北から西のほうに、堤防作ることにした。男も女も力を合わせて土を掘って、運んだ。とても大変なことだったが、あけてもくれても村人たちは、歯をくいしばり、体が粉になるほど働いた。
やがて、三年経った。
山と堤防に囲まれて、沼のように広がった大きなため息が、見事に出来上がり、水がいっぱいになった時は、村人たちは抱き合って、涙を流して喜んだ。もうこれで、大水の出ることも、日照で田んぼがカラカラになる心配もなくなった。大倉の里が、このあたりで一番米の取れる村になると、喜んでおった。
だが、思いがけないことが起こった。
溜池の出来上がった明くる年、大雨が降り続き、水が溢れるほどになった。村人たちは、まさかの溜池の水が、溢れて大水になる事はあるまいと、安心しておった。ところが、どうしたわけか、溜池を囲む堤防の1カ所が、あっという間に切れてしまい、水は鉄砲水になって、どっと流れだした。村人たちは、必死になって、堤防の切れ目を防いで、何とか大水になるのを防いだ。雨がやんだ後、村人たちは、もうこんな事にならないように、堤防の切れたところを、念入りに固め直した。だが、どうしたわけか、次の年、その次の年、同じところが切れて、村中の田んぼが、水浸しになってしまった。村人たちは、どうしたものかと、すっかり頭を抱え込んでしまった。そしてある年、その年も大雨が降り続き、溜池の水が、今にも溢れそうになった。するとまた、堤防の同じところが、切れかかってきた。
村人たちは、激しい雨の中で、泥んこになって、今にも切れそうになっている堤防を固めていた。この池の近くに、16歳になったばっかりの、おくらと言う娘と、長い病気で寝ている母親が住んでいた。村人たちは、みんな堤防を守るために、働いているけれど、おくらの家では、手伝いに行くことができない。おくらの母は、床の中で手を合わせ、「オラはいつも手伝いもできなくて、村の衆にすまねぇ。」と、涙を流していた。「おっかあの代わりに、私が行く。」
おくらには、蓑と笠で身を固めて、外に飛び出した。
何か手伝わしてくれ、と言うおくらを、村人たちは、「お前の力では、どうにもならないから、邪魔だからあっちいけ!」
と、押しのけてしまった。村人たちは、堤防を守るのに必死で、おくらなどに、かまっておれなかった。
「こりゃあ、池の主のたたりじゃー。若い娘を人柱に立てて、池の主を沈めるより他にない。」
村の老人が言った。
いくら堤防を固め直しても、いつも同じところだけ切れてしまうのは、池の主のたたりとしか思えない。でも、誰が人柱に立つのか。村人たちは顔見合わせた。その時、「お願いします。どうか私を人柱に立ててください。」と、おくらが叫んだ。
「おくら、お前のおっかあが病気だから、そんなことはできねえ。」
びっくりした村人たちは、口々に止めたが、「村が助かるなら、喜んで人柱になります。ただ、残ったおっかさんを、どうかよろしくお願いします。」おくらは手を合わせると、引き止める村人の手を振り切って、今にも切れそうな、堤防の泥水の中に、自分で入っていった。泥水は、ズブズブと、おくらの小さな体を飲み込み、あっという間に、おくらの姿は見えなくなってしもうた。
「おくら、すまねえ。」
村人たちは、おくらの沈んでいったあたりに、涙を流しながら土を入れ、石を入れた。すると、不思議なことに、あれほど強くなって降っていた雨が止み、ために池の水も、嘘のように静まってきた。やがて、堤防は、しっかり固まり、それからはどんな大雨でも、もう二度と切れる事はなかった。
村は、おくらのおかげで、豊かな村になり、この堤防は、おくらつつみと呼ばれ、村の名もおくらの名をとって、大倉というようになりました。
おしまい
Re: Re: カバ - sisi
2021/01/05 (Tue) 23:14:51
こんなタフのある英雄のような昔話がありました。
「三平長嶺(さんぺいながね)」
(岩手県東山町の昔話)
むかし、岩手は東山町の猿沢というところから江刺の田原へこえる境に両方の村の入会山があり、その山は、藩の抱える山で、村人誰でも自由に入ることができた。
村人たちは、その入山で草と芝を刈る暮らしとして役立った。ところが、その境が入会山の中にあったことから、両方の村の間に境をめぐり、人と人のもめごとが耐えなかった。
両方の村の村長や名主たちは困った。
「怪我なければなー。」
「んー、血は流れることでもなりかねぇな。」と、すっかり頭を抱えた。
ところで猿沢には三平という義理がたい百姓がいました。村一番の評判でした。
ある夏、いつも早起きで同じ時刻の三平は、ふと見るともう、多く村人が入りこんだ。
これは驚きの田原村の百姓たちが境を越し、猿沢の草地に入り、随分と草を刈りました。
三平は、「田原の百姓さんたちは、よその土地のこと知って入ってくるのは、ひどいじゃないか。刈った草は置いていけとは言わないで、ただ、オラの目に着いた以上は引き取ってくれないか。」と穏やかに言った。
田原の百姓たちは、こちら大勢なのに願い事は聞こえないとばかり、しらを切り、逆にこれ見よとばっかり、せっかく草を借りだしたからたまらない。
三平は仁王立ちになりながら、百姓らに向かってじっとこらえた。
すると、田原の百姓老人が、「そうか、境をお貸したというが、この境を線で引いてるのか。このあたりは、どうせ変わらない土地で、そんな草刈って何が悪い。はっきり言って早いもん勝ちしかない。」
いくら多くの田原の百姓が頼んでも、三平の足元にツバを吐いた。
「誰が通用するか。この長嶺路(ながねじ)が決まってる境だ。この道を越すお前らがオラところへ入った以上は覚悟あるところだ。穏やかに話しても無駄なら、オラ一人の力づくて相手にしてやるぞ。」と三平は身構えた。
「上等だ!面白いじゃないか、オラたちが喧嘩で力づいてやるぞ!」
田原の百姓たちは草刈りがまをきらめかして切りかかった。
これを合図に血は流れまくり、三平にめがけて、切りかかりました。
村の動物たちも三平にめがけた。
なんと三平は全身血がまみれても立ったまま退けはしなかった。
「オラが死んでも一歩も動かねえ!人の草を刈りたいなら、オラのシカバネを越えていけ!」と切られっぱなしのままの三平は、とうとう命を失った。田原の百姓たちと動物たちは悪夢からさめたようなぼう然となった。
それからというもの、両方の村から立あい人を出し、長嶺路が境をすることを正確にした。
この道を三平長嶺と名付けた。
(おしまい)
Re: カバ - sisi
2021/01/19 (Tue) 21:06:26
 第二次世界大戦終戦前の昔話あります。
第二次世界大戦終戦前の昔話あります。
炭を焼いた脱走兵
(群馬県高崎市の昔話)
むかし、第二次世界大戦の終戦になる一年前ぐらいの頃でしたかな。群馬は多野郡の一番奥の上の村に、木枯しが吹き始めた。
山また山の上野村は世の中から置き忘れているような村だったけど、男衆が戦地に取られたり東京から疎開の衆が入ってきたり,村の農家がいつのまにか、軍服や軍の雨合羽のボタン付けする、にわか工場に変わったりして、「やっぱり戦争でたんだな。」って、村に残されたものも、身にされるようになった。それでも町のものに比べたら、どんなに呑気でたまにアメリカの飛行機が空の上を飛んでいても、「あれが B 29だ。」「この頃はよく飛ぶね。」というぐらいで怖がることもなく空を眺めた。
村には、山とわずかな畑があるだけで、家もろくに寝てない。アメリカ人たちもこんなところに爆弾落としたりはしない。こんな村に、ある日、騒ぎが持ち上がった。署の巡査と憲兵が7、8人にして村にやってきた。けしばんだ顔からして、ただ事じゃない。「一体何かあったのだ。」と聞きますと、「高崎の連隊を脱走した兵隊が村に逃げ込んでいる、それを捕まえなければならない。」と言ってる。村の人たちはびっくりして、連隊の兵隊といえばこれから戦地へ出て、国のために戦わなければならないのに逃げ出すとはもってのほかのことだ。それが、よりにもよって、上野村へ逃げ込むとは、迷惑もはなはだしい村の名前にかけても脱走兵をとっ捕まえれなければならない。「山がりするから手の空いてるものはみんな出てきて。」巡査と憲兵は目ん玉を三角にして村の衆を集めました。村の消防団に動員がかかったけど頼みのおやじや若者連中は、あらかた戦争に入ってる消防団といってもじいさん、ばあさん、お母さん、お姉さんのよせ集めでした。
「脱走兵も命がけだ。捕まれば、軍法会議行きだから、見つかったら、必死の抵抗してくる、よって、発見したら遠まきにして、急報すること、無理をすると怪我のもとだ。」
憲兵の訓辞を受け、村の衆はとび口や竹槍もって、山がり始めたけど、これが見つかるものではない。なんたって、山深いから至るところに洞穴がある。逃げ場には事欠かないわけでした。
村の衆は、こしべんとうで、山をしらみつぶしにあたっているけど、4、5日たっても見つからず、山がりは、一週間のうえも続いた。
「もう、よそ村へ逃げたかもしれないぞ。」と、山がりはあきらめました。憲兵も巡査も引き上げて行って、しばらくすると、
「な、何!わしの家だ。軒下の吊し柿がない。」
「うちとこも切り干し芋がない。」
「わしとこも卵5個がない。」
「卵ならいいが、あんたところのニワトリがやられた。」
村のあちこちでそんな話が、ささやかれだして、後を絶たないようになってしまった
。
「みんなあいつの仕業じゃないの,。脱走兵に間違いない。」「村じゅうに泥棒を買っとくようなものだ、切り干しやつるし柿やニワトリ小屋を荒らされるくらいならいいが、これ以上なると、ほっとくわけにはいかない。もう一度、山がりするしかない。」
そういう人もあったけど村の衆の大方は前の山がりは懲りていたし被害も大したことではなかったから、そっとしといた。正月過ぎて2月過ぎて脱走兵は捕まらなかったけど3月の中頃だったが峠の道を通りかかった村のじいさんが山の中腹に煙が立っているのを見つけた。
「あんなところに煙のたつわけがない、ひょっとしたら連隊を逃げ出した兵隊の居所かもしれない。」
そこは、ひと昔前に掘られたトンネルでしたけど、土砂崩れがひどく片っぽ、ふさがっているものですから、ほったらかしにされていた。じいさんの通報で、巡査や憲兵がやってきて、張り込むと、次の朝、トンネルの入り口にやせて目ばかり光った。ボウボウなひげ男が現れた。
巡査や憲兵がとびかかると、男はわめき、棒ふりまわしの暴れたけど、何も食わなかったから、力が尽きて、手錠をはめられてしまった。
男はやっぱり連隊の脱走兵でした。その時は散々殴られたので戸板にのせられて山を降りたんだが、それから幾日もたたないうちに息を止めました。連隊の取り調べが、よっぽど厳しかった。村の衆がトンネルの入り口に入ってみるとトンネルの中に炭焼きがまがあり、炭が入っていた。
「炭を焼いて売りに行けるわけではないし、バカなことをしたもんだ炭を焼いた煙が目について,それで捕まっちゃったんだ。」
脱走兵がどうして炭を焼いたのか村の主は不思議に思ったけどそのうちにとなり村の木こりだったということがわかった。山仕事の他には何もできない男だったと聞いてやっと納得できた。
「戦の稽古により、炭が焼きたいばかりに脱走したんだな。」と言った。
それから半年が経ちました、戦争が終わりまして、村の衆は切り干し芋や吊し柿やニワトリや卵を取られたことを忘れてもスッキリした。
「もうしばらく、隠れ通しても死にたくはないから、山仕事がいくらでもできる。」と、脱走兵には申し訳ない気持ちでした。
(おしまい)
Re: カバ - sisi
2022/06/04 (Sat) 08:56:46
おはようございます。こういうお話もあります。
白鷺の滝
(群馬県みなかみ町の昔話)
むかし、谷川岳あたりには雪が降り、越後から上州へ進む3人の山伏が歩いておりました。山道さしかかろうとしたところ、日が暮れて、足が順調に進んでいます。ところが、歩いていた山道が突然迷ってしまい、その山道は真っ暗で見えませんでした。南無妙法蓮華経と書いてあった白装束だけが白く見えます。厳しく積み重ね続いた3人の山伏が心細くなった。滝の流れる音と家小屋が一軒なく、深い山の中に引き込まれそうな場所で、それはもう、心地は感じませんでした。
そのとき、歩き進む道が、何やら光が照らし、近寄る滝壺の近くに、銀色の光を放ち、1羽の白鷺が飛んでいた。その白鷺の光が眩しいほど輝き、谷のまわりには、一行についてくるようでした。
3人の山伏は、銀色の光の白鷺のとおりに、山道を下り始めた。3人の山伏は南無妙法蓮華経という読経をしながら、山のまわりに力を強く感じた。
こうして、3人の山伏は、山里の土合部落に無事到着し、白鷺のおかげで礼をし、法華経のお札を足に結び、この白鷺をこれからの守りとして祈りました。
それからというもの、谷川岳の西黒沢から流れる滝のことを白鷺の滝と呼ぶそうな。 (おしまい)
Re: カバ - sisi
2022/06/04 (Sat) 22:59:34
すってん天狗
東京都の昔話
むかしむかし、山の神様は天狗どんのことだ。日照りが続き、作物は枯れてしまい、自分のうちわひとふり、雨雲を呼び寄せ、田んぼや畑を緑で潤す。悪い病気が流行っても、てんぐのうちわをひとふりすれば、流行病を追い払う。それはありがたい神様でした。
天狗どんの住む山の頂上の大きな木の下には、「天狗様、子供を授けてくだされや。」「商売繁盛がなりますように。」と、いつもお供え物がたくさん。おかげさまで、天狗どんは毎日ご馳走を食べて顔が真っ赤でした。ところが、何年も長生きしている間に山の様子がだんだんと変わり、そんなある年の事、隣山におみやができました。それからというもの、もう誰も天狗どんの見向きもしなくなった。供え物はだんだん来なくてもご馳走は食べれない。天狗どんはみるみる痩せてきて、顔色も青くなり、しまいには自慢のうちわも枯れてしまいました得意の術も使えなくなってしまいました。
これからどうするのか、天狗どんは人間の町へ行って何か仕事でもしようと考えた。働いたらきっと、ご馳走が食べれるかもしれません。考えた天狗どんは、山を降りて町へと向かいました。町ではいろんな人が働いており、天狗どんには珍しいことばかりでした。
天狗どんは早速、左官の仕事を始めました。もともと神様だった天狗どんは仕事の覚えは早い、いる間に壁の裏にかかったのはいいが、長い鼻が邪魔をして、塗り立ての壁をずりずりとこすり、これでは左官の仕事はとてもかなわない。
次は畳の仕事を始めた。ところが、ひと針ごとに鼻は畳をこすって、針生ポツリ、鼻をヒリヒリぷっつり、ヒリヒリぷっつりヒリヒリと、自慢の鼻を傷だらけになりました。
床屋の仕事しても、呉服屋の仕事しても、豆腐屋の仕事しても、傘屋の仕事しても、染物屋や籠運びや刀鍛冶や提灯屋や石屋屋台ガラス吹きの仕事しても、長い鼻が、邪魔ばかりで仕事はうまくいかない。
困ったこの長い鼻は、これでは町にも進めない。さりとて、あれ放題の天狗山へ帰って見てもどうにもならない。
さてこれからどうなるか、天狗どんは、町の中をあっちとぼとぼ、こっちへフラフラすると、天狗どんの横をぴゅーんと、走る抜けたものが降りました。それは手紙を運ぶ飛脚でした。走ることの得意な、後はこれを見て、思いつきました。その時から、天狗どんは飛脚になり、長い鼻の先に手紙の箱を結びつけて走りました。それにすっかり元気になり、天狗どんの顔は顔は元のようにつやつやの真っ赤になりました。今でも手紙を入れる郵便受けは天狗どんのように真っ赤なつやつやではありませんか。おしまい
(参考出典:「すってんてんぐ」木曽秀夫/著、1984年、サンリード刊)
Re: カバ - sisi
2022/06/05 (Sun) 19:51:16
七夕の1ヵ月前をサプライズしてごめんなさい。こういうお話がありますよ。
「七夕さま」
(大阪府枚方市の昔話)
むかしむかし、そのまたむかし。
天の川の流れる東に織姫が住んでおり,毎日,機織りをして、トンカラリン、トンカラリンと音を立てて織るのが得意でした。
いつも機織りの音が聞こえてたまらない西に住む彦星という牛飼いの男がいて、織姫のことをずっと一目惚れをした。
というわけで、織姫と彦星は、織姫の父である天に住む帝さまの許しを受けてから嫁入りにしました。
それから経つと、織姫と彦星は、毎日毎日、仲のいい夫婦になりました。織姫の作った朝、昼、晩の飯が天下一ほど美味しかった。
数年に経ち、織姫と彦星の間に元気な男の子が産まれました。三人家族になってから、段々と幸せに暮らした。
だが、それを見て天からのぞく帝さまが、織姫と彦星の仲が良すぎて、困り果てて怒りだした。
天から降りた帝さまが、「お前ら、いつも、うちの娘と仲が良すぎるぞ!いいか、そんなに会いたいなら、年に一度の七月七日の夜だけ会ってやろう。」という厳しい約束をしてしまい、帝さまと織姫は天に戻って別れてしまい、西に居る彦星と子供を残した。
それから、彦星は織姫に会う出発のために、天の川に渡る天津橋(あまつばし)を作り、船や歩きの両方で渡れる逢合橋(あいあいばし)を作り、悪い天気の場合、川の水かさが増えた時に、カササギの羽根を広げながら背中を渡るカササギ橋といった3つの橋を完成した。
また、羽衣を着ていた織姫は天の川の上流に羽衣橋(はごろもばし)も完成した。
やっと、七月七日の晩の一年一度を迎え、天の川で、織姫と彦星は楽しく出会えました。
天の川での夏の夜の星空に輝く七夕のはじまりでした。
(おしまい)